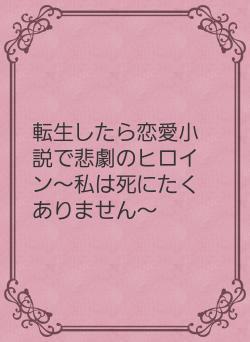「恵美、…本当にすまなかった、ずっと、ずっと会いたかったよ。」
その男性は、私の手を両手で握り、瞳には涙を溜めている。
初めて見る男性なのに、不思議と懐かしい。
私も何故か目の奥が熱くなり、涙が溢れて頬に流れた。
「…お父さん…お父さん…ですよね。」
「あぁそうだよ…私が恵美の父だ。許してくれ。」
親子とは不思議なものなのかも知れない。
初めて会うのに、とても懐かしく温かい気持ちになる。
父は私を抱きしめてくれた。
なんとも言えない安心感と心地よさだった。
父は着替えを済ませると、リビングで私の隣に座った。
しばらく無言だった父が、私の頭に優しく手を置いた。
「…恵美、お母さんから聞いたかも知れないけれど、家の都合でいろいろとすまない事をしてしまったね。」
「大丈夫です…お父さん。私は今まで育ててくれた両親がとても大切にしてくださいました。だからずっと幸せでしたよ。」
父は静かに大きく頷いた。
そしてまた目には涙を浮かべている。
「お前を手放す時、お母さんはかなり取り乱していたよ。暫くは食事もとれない程だったんだ。」
あんなに落ち着いて見える母が、そんなに取り乱すとは想像もできない。
父は目を閉じてゆっくりと話し出した。
「今まで皆に黙っていたけれど、私は恵美を遠くから時々見ていたんだよ。学校で元気に笑う君を見て安心していたんだ。」
お父さんが、私を見に来ていたなんて信じられない。
でも、なんだかその話を聞くと嬉しくなる。
「恵美、神宮司家に伝わるお告げでの話はもう聞いたかい?」
父は私に申し訳なさそうな表情をみせた。
「…はい。そのお告げの話は、お母さんから聞いています。」
「…恵がこうなってしまった今、恵美に頼むしかないんだ…許してくれ。」
「…はい。お話を聞いても、まだ信じられませんが、それが私の運命なのですよね。」
「すまない…でも、これだけは言っておくが、龍崎も早乙女も恵美のことは、とても大切に思っている。お前が小さい頃から、私と同じ様にあの二人はお前も見守って来ているんだ。」
龍崎と早乙女が私を小さい頃から知っているとは驚いた。
そして、見守ってくれていたという。
それを聞いて、一つ思い出したことがあった。
幼稚園の頃、私は道路に飛び出してしまい、トラックに轢かれそうになったことがあった。
しかし、奇跡的に無傷だったのだ。
ずっと夢だと思っていたが、トラックとぶつかる瞬間に、誰かに抱き上げられた感触をうっすら覚えていたのだ。
今思えば、あれは龍崎か早乙女がだったのかも知れない。
私は昔から守られていたのだ。