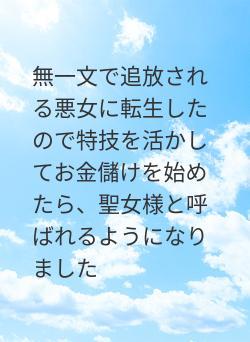「ようこそ、ルシアン様。そして御令嬢、お待ち申し上げておりました」
スーツを着用した大柄な男性が2人を出迎えた。男性は小柄なイレーネにとっては見上げるほどの大男だった。
「まぁ……なんて大きな方なのでしょう」
イレーネは男性を見上げ、思ったままの言葉を口にする。
「う……ゴホン! イレーネ。彼はこの城の執事、メイソンだ。メイソン、彼女は俺の婚約者である、イレーネ・シエラ。よろしく頼む」
ルシアンは咳払いすると、2人を引き合わせた。
「イレーネ様でいらっしゃいますか? はじめまして、執事のメイソン・タイラーと申します。どうぞ、お気軽にメイソンとお呼び下さい」
そしてメイソンはニコリと笑みを浮かべる。
「私はイレーネ・シエラと申します。こちらこそ、よろしくお願いいたします」
2人が挨拶を交わしたところで、ルシアンはメイソンに尋ねた。
「メイソン。早速祖父に御挨拶したいのだが……今何処にいる?」
「はい、旦那様は書斎にいらっしゃいます」
恭しく返事をするメイソン。
「では早速行こう。彼女の荷物を頼む」
「はい、お部屋に運んでおきます」
するとイレーネはメイソンに声をかけた。
「あの、荷物なら自分で運びますわ」
「え?」
その言葉にメイソンは目を見開く。
「い、いや! 荷物はメイソンにまかせておこう。それよりも早く祖父の元へ行かないと」
ルシアンは慌てたようにイレーネの手を引くと、歩き出した。
「え? ルシアン様?」
何故ルシアンが慌てているのか、訳も分からないままイレーネは手を引かれてその場を後にした――
****
「イレーネ。以前にも話しただろう? 貴族女性はむやみやたらに荷物を持つものではないと」
ルシアンはイレーネの手を引きながら話しかけてきた。
「あ、そうでしたね。私ったらついうっかりしておりました。申し訳ございません」
「い、いや。忘れてしまっていたなら仕方がない。だが、今後は気をつけるようにな。特に祖父の前では」
素直に謝るイレーネに、ルシアンは声のトーンを落とす。
「それにしても、本当にお城に住んでらしたのですね……床が大理石ですし、豪華なシャンデリアですねぇ」
イレーネがうっとりした様子で周囲を見渡す。
「そうか? あまり感じたことはないがな」
その後、書斎に行くまでの間に2人は多くの使用人たちとすれ違った。彼らは深々とおじぎをしながらも、好奇心いっぱいの視線でイレーネを見つめている。
「ルシアン様、何だか私随分注目を浴びているようですね」
小声で話しかけてくるイレーネ。
「それは当然だろう。何しろ俺がここに女性を連れてくるのは君が初めてなのだからな」
「まぁ、そうだったのですね。でしたら私も気を引き締めなくてはなりませんね」
「ああ。是非ともそう願いたいものだ」
それはルシアンの本心からの言葉だった。
その後もルシアンはイレーネの手を引いたまま、祖父の待つ書斎へ向かった。
……自分が未だにイレーネの手を握りしめているという自覚もなしに。
****
「よし、着いた。ここが祖父のいる書斎だ。今から入室するぞ?」
ルシアンが白塗りの扉の前で足を止めた。ドアノブは金色に輝いている。
「まぁ、ドアノブが金で出来ているのですね? 分かりやすいお部屋ですわね」
これから祖父と対面することに緊張するルシアンに対し、イレーネはドアノブに興味を示している。
「ドアノブなんかどうでもいい。いいか? この扉を開けると、いよいよマイスター家の現当主……祖父が待ち受けているんだぞ? 分かっているのか?」
「ええ。勿論分かっております。ルシアン様は随分緊張なさっているようですね? まずは深呼吸してみてはいかがでしょうか?」
「あ、ああ……分かった。深呼吸だな?」
ルシアンはイレーネに言われた通り、深呼吸する。緊張がピークに達しているルシアンは立場が逆転していることに気づいてもいない。
「よ、よし。では入るぞ。いいか? イレーネ」
ルシアンは改めて声をかける。
「はい、ルシアン様。どうぞ」
イレーネに促され、ルシアンは頷くと扉をノックした。
――コンコン
『入れ』
扉の奥から、くぐもった声が聞こえてくる。
「失礼いたします」
――ガチャッ
《《イレーネの手を握りしめたまま》》扉を開けるルシアン。
すると部屋の中に、窓を背にスーツ姿の老人がこちらを向いて立っている。
「来たか、ルシアン」
老人の声が部屋に響く。
「はい、ジェームズ・マイスター伯爵」
ルシアンは緊張気味に返事をした――
スーツを着用した大柄な男性が2人を出迎えた。男性は小柄なイレーネにとっては見上げるほどの大男だった。
「まぁ……なんて大きな方なのでしょう」
イレーネは男性を見上げ、思ったままの言葉を口にする。
「う……ゴホン! イレーネ。彼はこの城の執事、メイソンだ。メイソン、彼女は俺の婚約者である、イレーネ・シエラ。よろしく頼む」
ルシアンは咳払いすると、2人を引き合わせた。
「イレーネ様でいらっしゃいますか? はじめまして、執事のメイソン・タイラーと申します。どうぞ、お気軽にメイソンとお呼び下さい」
そしてメイソンはニコリと笑みを浮かべる。
「私はイレーネ・シエラと申します。こちらこそ、よろしくお願いいたします」
2人が挨拶を交わしたところで、ルシアンはメイソンに尋ねた。
「メイソン。早速祖父に御挨拶したいのだが……今何処にいる?」
「はい、旦那様は書斎にいらっしゃいます」
恭しく返事をするメイソン。
「では早速行こう。彼女の荷物を頼む」
「はい、お部屋に運んでおきます」
するとイレーネはメイソンに声をかけた。
「あの、荷物なら自分で運びますわ」
「え?」
その言葉にメイソンは目を見開く。
「い、いや! 荷物はメイソンにまかせておこう。それよりも早く祖父の元へ行かないと」
ルシアンは慌てたようにイレーネの手を引くと、歩き出した。
「え? ルシアン様?」
何故ルシアンが慌てているのか、訳も分からないままイレーネは手を引かれてその場を後にした――
****
「イレーネ。以前にも話しただろう? 貴族女性はむやみやたらに荷物を持つものではないと」
ルシアンはイレーネの手を引きながら話しかけてきた。
「あ、そうでしたね。私ったらついうっかりしておりました。申し訳ございません」
「い、いや。忘れてしまっていたなら仕方がない。だが、今後は気をつけるようにな。特に祖父の前では」
素直に謝るイレーネに、ルシアンは声のトーンを落とす。
「それにしても、本当にお城に住んでらしたのですね……床が大理石ですし、豪華なシャンデリアですねぇ」
イレーネがうっとりした様子で周囲を見渡す。
「そうか? あまり感じたことはないがな」
その後、書斎に行くまでの間に2人は多くの使用人たちとすれ違った。彼らは深々とおじぎをしながらも、好奇心いっぱいの視線でイレーネを見つめている。
「ルシアン様、何だか私随分注目を浴びているようですね」
小声で話しかけてくるイレーネ。
「それは当然だろう。何しろ俺がここに女性を連れてくるのは君が初めてなのだからな」
「まぁ、そうだったのですね。でしたら私も気を引き締めなくてはなりませんね」
「ああ。是非ともそう願いたいものだ」
それはルシアンの本心からの言葉だった。
その後もルシアンはイレーネの手を引いたまま、祖父の待つ書斎へ向かった。
……自分が未だにイレーネの手を握りしめているという自覚もなしに。
****
「よし、着いた。ここが祖父のいる書斎だ。今から入室するぞ?」
ルシアンが白塗りの扉の前で足を止めた。ドアノブは金色に輝いている。
「まぁ、ドアノブが金で出来ているのですね? 分かりやすいお部屋ですわね」
これから祖父と対面することに緊張するルシアンに対し、イレーネはドアノブに興味を示している。
「ドアノブなんかどうでもいい。いいか? この扉を開けると、いよいよマイスター家の現当主……祖父が待ち受けているんだぞ? 分かっているのか?」
「ええ。勿論分かっております。ルシアン様は随分緊張なさっているようですね? まずは深呼吸してみてはいかがでしょうか?」
「あ、ああ……分かった。深呼吸だな?」
ルシアンはイレーネに言われた通り、深呼吸する。緊張がピークに達しているルシアンは立場が逆転していることに気づいてもいない。
「よ、よし。では入るぞ。いいか? イレーネ」
ルシアンは改めて声をかける。
「はい、ルシアン様。どうぞ」
イレーネに促され、ルシアンは頷くと扉をノックした。
――コンコン
『入れ』
扉の奥から、くぐもった声が聞こえてくる。
「失礼いたします」
――ガチャッ
《《イレーネの手を握りしめたまま》》扉を開けるルシアン。
すると部屋の中に、窓を背にスーツ姿の老人がこちらを向いて立っている。
「来たか、ルシアン」
老人の声が部屋に響く。
「はい、ジェームズ・マイスター伯爵」
ルシアンは緊張気味に返事をした――