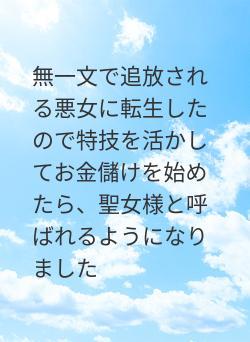「そういえば買い物に気を取られていてお昼のことを忘れていたな。もう14時を回っている」
ルシアンは腕時計を見た。
「まぁ、14時を過ぎていたのですね? 買い物が楽しくて、すっかり時間を忘れていましたわ」
「そうか? そんなに楽しかったのか?」
イレーネの言葉にまんざらでもなさそうにルシアンが頷く。
「はい、『コルト』に住んでいた頃は洋品店の窓から店内を覗くだけでしたから。実際に買い物をすることなど滅多にありませんでしたので」
「あ、ああ……何だ。そっちのほうか……」
落胆した声でボソリとつぶやくルシアン。
「え? 今何かおっしゃいましたか?」
「いや、何でも無い。それでは少し遅くなってしまったが、何処かで食事でもしていかないか? この通りには様々な店が立ち並んでいるからな」
「はい、そうですね」
そこで2人は馬車から降りると、通りを歩いてみることにした――
**
「ルシアン様、このお店はいかがですか? なかなかの盛況ぶりですよ?」
イレーネが駅前の噴水広場の正面にある店の前で足を止めた。
「……あ。この店は……」
ルシアンは店をじっと見つめる。
「どうかしましたか? このお店のこと御存知なのですか?」
「ああ……知っている。ここは開業してまだ5年目程の料理屋なのだが、元王宮料理人が開いた店で貴族達の間で人気の店なんだ」
「まぁ。そんなに有名なお店だったのですか」
「そうだ。……以前は俺も良くこの店に通っていたのだが……」
そこでルシアンは言葉を切る。
「どうかされましたか? ルシアン様」
「い、いや。何でも無い」
首を振るルシアン。
(そうだ、あれからもう4年も経過しているんだ。……多分大丈夫だろう)
ルシアンは頭の中を整理すると、再びイレーネに声をかけた。
「それでは……この店にしてみるか?」
「はい、そうしましょう」
笑顔で答えるイレーネ。
そこで店の中へ入ると、すぐに笑顔のウェイターが現れて2人を窓際のボックス席へ案内をした。
「イレーネ、どれでも遠慮せずに好きな料理を頼むといい」
メニューをじっと見つめているイレーネにルシアンは声をかけた。
「ありがとうございます。まあ……どれも美味しそう」
(随分楽しそうだな……)
楽しそうにメニューを選んでいるイレーネを見ていると、ルシアンはまるでこれが本当のデートのように思えてきた。
「う〜ん……これだけ沢山のお料理があると迷ってしまいますね」
「だとしたらレディースセットにしてみるか?」
「そうですね。それが良さそうです」
「よし、では……そこの君。注文を頼む」
ルシアンは近くに待機しているウェイターに声をかけた。
「はい、お客様」
ウェイターは近くに来ると笑顔で返事をする。
「本日のお薦めと、レディースセットを頼む」
「かしこまりました。……ところでもしや……お客様、マイスター伯爵様でいらっしゃいませんか?」
「そうだが……?」
「やはり、そうだったのですね? 何処かでお見受けしたお顔だと思っておりましがが……それではこちらの女性はベアトリス様ですね?」
「!」
その言葉に、ルシアンは血の気が引く。しかし、一方のイレーネは気にする素振りもなく首を振る。
「いいえ、私はイレーネと申します」
「あ! こ、これは大変失礼いたしました。で、では少々お待ちください!」
ウェイターは慌てた様子で頭を下げると、逃げるようにその場を去っていった。
気まずい思いをしたルシアンと、呑気なイレーネをその場に残し――
ルシアンは腕時計を見た。
「まぁ、14時を過ぎていたのですね? 買い物が楽しくて、すっかり時間を忘れていましたわ」
「そうか? そんなに楽しかったのか?」
イレーネの言葉にまんざらでもなさそうにルシアンが頷く。
「はい、『コルト』に住んでいた頃は洋品店の窓から店内を覗くだけでしたから。実際に買い物をすることなど滅多にありませんでしたので」
「あ、ああ……何だ。そっちのほうか……」
落胆した声でボソリとつぶやくルシアン。
「え? 今何かおっしゃいましたか?」
「いや、何でも無い。それでは少し遅くなってしまったが、何処かで食事でもしていかないか? この通りには様々な店が立ち並んでいるからな」
「はい、そうですね」
そこで2人は馬車から降りると、通りを歩いてみることにした――
**
「ルシアン様、このお店はいかがですか? なかなかの盛況ぶりですよ?」
イレーネが駅前の噴水広場の正面にある店の前で足を止めた。
「……あ。この店は……」
ルシアンは店をじっと見つめる。
「どうかしましたか? このお店のこと御存知なのですか?」
「ああ……知っている。ここは開業してまだ5年目程の料理屋なのだが、元王宮料理人が開いた店で貴族達の間で人気の店なんだ」
「まぁ。そんなに有名なお店だったのですか」
「そうだ。……以前は俺も良くこの店に通っていたのだが……」
そこでルシアンは言葉を切る。
「どうかされましたか? ルシアン様」
「い、いや。何でも無い」
首を振るルシアン。
(そうだ、あれからもう4年も経過しているんだ。……多分大丈夫だろう)
ルシアンは頭の中を整理すると、再びイレーネに声をかけた。
「それでは……この店にしてみるか?」
「はい、そうしましょう」
笑顔で答えるイレーネ。
そこで店の中へ入ると、すぐに笑顔のウェイターが現れて2人を窓際のボックス席へ案内をした。
「イレーネ、どれでも遠慮せずに好きな料理を頼むといい」
メニューをじっと見つめているイレーネにルシアンは声をかけた。
「ありがとうございます。まあ……どれも美味しそう」
(随分楽しそうだな……)
楽しそうにメニューを選んでいるイレーネを見ていると、ルシアンはまるでこれが本当のデートのように思えてきた。
「う〜ん……これだけ沢山のお料理があると迷ってしまいますね」
「だとしたらレディースセットにしてみるか?」
「そうですね。それが良さそうです」
「よし、では……そこの君。注文を頼む」
ルシアンは近くに待機しているウェイターに声をかけた。
「はい、お客様」
ウェイターは近くに来ると笑顔で返事をする。
「本日のお薦めと、レディースセットを頼む」
「かしこまりました。……ところでもしや……お客様、マイスター伯爵様でいらっしゃいませんか?」
「そうだが……?」
「やはり、そうだったのですね? 何処かでお見受けしたお顔だと思っておりましがが……それではこちらの女性はベアトリス様ですね?」
「!」
その言葉に、ルシアンは血の気が引く。しかし、一方のイレーネは気にする素振りもなく首を振る。
「いいえ、私はイレーネと申します」
「あ! こ、これは大変失礼いたしました。で、では少々お待ちください!」
ウェイターは慌てた様子で頭を下げると、逃げるようにその場を去っていった。
気まずい思いをしたルシアンと、呑気なイレーネをその場に残し――