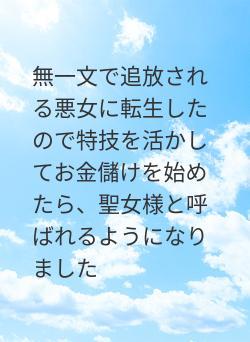その日の夕食の後――
「本当に大したお方ですね、イレーネさんは」
書斎に紅茶を淹れに来たリカルドがルシアンと話をしている。
「何が大したお方だ。ブリジット嬢と友達になったと聞かされて俺がどれだけ驚いたと思っている。全く……これでは心臓がいくらあっても足りなくなりそうだ」
しかめた顔で紅茶を飲むルシアン。
「で、ですが……まさかイレーネさんが、ルシアン様だけでなくブリジット様まで懐柔してしまうとは……クックックッ……」
リカルドは肩を震わせ、左手で顔を覆い隠している。
「リカルド……お前、面白がっているだろう? 大体、懐柔とは何だ? 俺は別にイレーネに懐柔されてなどいないが?」
「そう、そこですよ。ルシアン様」
「何だ? そことは?」
「イレーネさんのことをそのように呼ぶことですよ。今までどの令嬢全てにおいても敬称つきで呼ばれていたではありませんか? ……あの方を除いては」
「……」
その言葉に黙り込んでしまうルシアン。
(しまった。少し余計なことまで口にしてしまったかもしれない)
黙り込んでしまったルシアンを見て、リカルドは慌てたように話題を変えた。
「そ、それにしても私たちがほんの3日留守にしていただけなのに、イレーネさんは既にこの屋敷で自分の地位を築き上げていたようですね。使用人たちが口を揃えて言っておりましたよ? イレーネ様はルシアン様の不在中、立派な女主人を務めておりましたと」
「……まぁ、彼女はあんな細い身体なにのに、肝は据わっているからな」
「ええ。ですからきっと現当主様はイレーネさんのことを気に入ると思いますよ」
「だといいがな。だが、気に入られなくても構うものか。どうせ彼女は1年限りの契約妻なのだから」
(そうだ、一刻も早くマイスター家当主に認めてもらうためにもイレーネを祖父に会わせなくては……)
そして再びルシアンは紅茶を口にした――
****
――翌朝、朝食の席
「え? 来週、ルシアン様のお祖父様に会いに行くのですか?」
フォークを手にしていたイレーネが目を見開く。
「ああ、そうなる。祖父に俺を次期当主に認めてもらうには結婚相手である君を引き合わせなくては話にならないからな。祖父は気難しい男だ。不安なこともあるかもしれないが……」
「御安心下さい、ルシアン様。何も不安に思うことはありませんわ」
「は? い、いや。俺が言ってるのは……」
その言葉に、フォークを手にしていたルシアンの動きが止まる。
「この私にお任せ下さい! お年寄りのお相手なら、慣れておりますので。何しろ私は物心がついた頃から祖父と暮らしていたのですから。おそらく、ルシアン様のお祖父様と私の祖父は同年代だと思われます。その年代の方々の趣味嗜好は大体似たようなものでしょう。どうか私に任せて、ルシアン様は大船に乗ったつもりで構えていて下さい!」
饒舌にペラペラと語るイレーネ。
「ちょ、ちょっと待ってくれ。俺が言いたいのは君が不安に思っているのではないかということで……」
「私が不安に思っているか? ですか? いいえ、それどころかワクワクしております。今からルシアン様のお祖父様にお会いするのが楽しみですわ」
そして料理を美味しそうに口に運ぶイレーネ。
その様子を見ていると、ルシアンは自分が悩んでいるのが馬鹿らしくなってきた。
「はぁ……分かった。もういい。とにかく、来週には出発するから……色々と準備が必要だな」
「準備ですか?」
首を傾げるイレーネ。
「ああ、準備だ。とりあえずまずは……ドレスの買い足しだな」
「え? ドレスですか? この間10着以上も買い揃えましたけど?」
「たったあれだけでは全然足りない。何しろ我々はマイスター家の当主に会うのだから、それなりの装備が必要になるだろう?」
「装備……なるほど、確かに仰るとおりかもしれませんね」
イレーネはルシアンの言葉を真に受け、頷く。
「今からオーダーメイドは間に合わないからな……今回は試着してサイズが合うドレスを買うことにしよう。という訳でイレーネ」
「なんでしょうか?」
「今日、食後すぐに出かけるぞ」
「はい! ルシアン様」
2人が出かけるという話は瞬く間に使用人たちの間に広がった。
そしてルシアンとイレーネが初デートをするという話で盛り上がるのだった――
「本当に大したお方ですね、イレーネさんは」
書斎に紅茶を淹れに来たリカルドがルシアンと話をしている。
「何が大したお方だ。ブリジット嬢と友達になったと聞かされて俺がどれだけ驚いたと思っている。全く……これでは心臓がいくらあっても足りなくなりそうだ」
しかめた顔で紅茶を飲むルシアン。
「で、ですが……まさかイレーネさんが、ルシアン様だけでなくブリジット様まで懐柔してしまうとは……クックックッ……」
リカルドは肩を震わせ、左手で顔を覆い隠している。
「リカルド……お前、面白がっているだろう? 大体、懐柔とは何だ? 俺は別にイレーネに懐柔されてなどいないが?」
「そう、そこですよ。ルシアン様」
「何だ? そことは?」
「イレーネさんのことをそのように呼ぶことですよ。今までどの令嬢全てにおいても敬称つきで呼ばれていたではありませんか? ……あの方を除いては」
「……」
その言葉に黙り込んでしまうルシアン。
(しまった。少し余計なことまで口にしてしまったかもしれない)
黙り込んでしまったルシアンを見て、リカルドは慌てたように話題を変えた。
「そ、それにしても私たちがほんの3日留守にしていただけなのに、イレーネさんは既にこの屋敷で自分の地位を築き上げていたようですね。使用人たちが口を揃えて言っておりましたよ? イレーネ様はルシアン様の不在中、立派な女主人を務めておりましたと」
「……まぁ、彼女はあんな細い身体なにのに、肝は据わっているからな」
「ええ。ですからきっと現当主様はイレーネさんのことを気に入ると思いますよ」
「だといいがな。だが、気に入られなくても構うものか。どうせ彼女は1年限りの契約妻なのだから」
(そうだ、一刻も早くマイスター家当主に認めてもらうためにもイレーネを祖父に会わせなくては……)
そして再びルシアンは紅茶を口にした――
****
――翌朝、朝食の席
「え? 来週、ルシアン様のお祖父様に会いに行くのですか?」
フォークを手にしていたイレーネが目を見開く。
「ああ、そうなる。祖父に俺を次期当主に認めてもらうには結婚相手である君を引き合わせなくては話にならないからな。祖父は気難しい男だ。不安なこともあるかもしれないが……」
「御安心下さい、ルシアン様。何も不安に思うことはありませんわ」
「は? い、いや。俺が言ってるのは……」
その言葉に、フォークを手にしていたルシアンの動きが止まる。
「この私にお任せ下さい! お年寄りのお相手なら、慣れておりますので。何しろ私は物心がついた頃から祖父と暮らしていたのですから。おそらく、ルシアン様のお祖父様と私の祖父は同年代だと思われます。その年代の方々の趣味嗜好は大体似たようなものでしょう。どうか私に任せて、ルシアン様は大船に乗ったつもりで構えていて下さい!」
饒舌にペラペラと語るイレーネ。
「ちょ、ちょっと待ってくれ。俺が言いたいのは君が不安に思っているのではないかということで……」
「私が不安に思っているか? ですか? いいえ、それどころかワクワクしております。今からルシアン様のお祖父様にお会いするのが楽しみですわ」
そして料理を美味しそうに口に運ぶイレーネ。
その様子を見ていると、ルシアンは自分が悩んでいるのが馬鹿らしくなってきた。
「はぁ……分かった。もういい。とにかく、来週には出発するから……色々と準備が必要だな」
「準備ですか?」
首を傾げるイレーネ。
「ああ、準備だ。とりあえずまずは……ドレスの買い足しだな」
「え? ドレスですか? この間10着以上も買い揃えましたけど?」
「たったあれだけでは全然足りない。何しろ我々はマイスター家の当主に会うのだから、それなりの装備が必要になるだろう?」
「装備……なるほど、確かに仰るとおりかもしれませんね」
イレーネはルシアンの言葉を真に受け、頷く。
「今からオーダーメイドは間に合わないからな……今回は試着してサイズが合うドレスを買うことにしよう。という訳でイレーネ」
「なんでしょうか?」
「今日、食後すぐに出かけるぞ」
「はい! ルシアン様」
2人が出かけるという話は瞬く間に使用人たちの間に広がった。
そしてルシアンとイレーネが初デートをするという話で盛り上がるのだった――