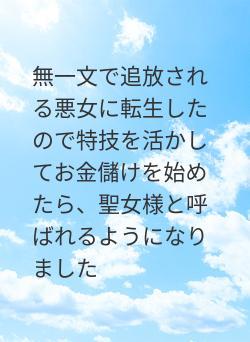(何だか……今朝は随分給仕の人数が多いな)
ルシアンはダイニングルームで給仕をする使用人たちを見渡した。普段なら給仕の人数は1人、ないし2人。
それなのに今朝に限っては違った。
2人のフットマンに、3人のメイドまでいるのだ。全員、明らかにイレーネを意識しているのは明白だった。
「紅茶はいつお持ちしますか?」
メイドがイレーネに尋ねる。
「そうですね、ルシアン様はいつお飲みになっておりますか?」
突然話をふられたルシアンは戸惑いながらも答えた。
「え? 俺は普段は食後にもらっているが?」
(あのメイドは何故そんなことを聞いてくるのだ? 普段は何も言わずに食後に紅茶を淹れてくるはずなのに! 大体、どこで俺とイレーネ嬢が朝食を一緒にとることがバレてしまったんだ? リカルドは何をしている!)
一言、リカルドに文句を言ってやりたいところだが肝心の彼は生憎不在だ。
(くそ! ここ最近、勝手な真似ばかりしおって……後で呼び出して説教してやらなければ……!)
ルシアンのどこか落ち着きのない様子をみて、イレーネが首を傾げる。
「ルシアン様、どうかされたのですか?」
「え? あ……何でも無い。ただ……何故、今朝に限ってこんなに給仕が集まっているのか不思議に思ってな」
その言葉に、使用人たちが一斉に肩をビクリとさせる。
「もう、全ての料理を並べ終えたのだろう?」
傍らに立っているフットマンに尋ねるルシアン。
「は、はい。ルシアン様。食事は全て提供させていただきました」
「そうか……なら、お前たちはもう席を外してくれ。彼女と2人きりで食事をしたいからな」
ルシアンはゆっくり、全員の顔を見渡した。
「分かりました……それでは我々は一旦席を外させていただきます……」
使用人たちはチラチラとイレーネに視線を送りながら、ダイニングルームを出て行った。
――パタン
扉が閉じられるとルシアンはため息をついた。
「全く……好奇心旺盛な使用人たちだ。さて、それでは食べようか」
「私も好奇心旺盛ですよ? それにしてもこのマイスター家には大勢の人たちが働いていらっしゃるのですね。私の働く隙もないほどです。……まぁ! 本当にこちらのお食事は美味しいですね」
料理を口にし、笑みを浮かべるイレーネ。
「そうか、口にあって何よりだ。だが、メイドの仕事は考えないでくれ。君の役目は俺の妻を演じることなのだから。実は……まだ使用人たちには君が妻になることを報告していないのだ。何しろ、この結婚は1年間という期間限定の契約婚だからな。かと言って、本当のことを話すわけにもいかないし……」
「本当のことは話さずに、私と結婚するとお話すれば良いのではありませんか?」
「それは確かにそうなのだが……しかし、1年で離婚することになるからな。自分の評判は落ちても構わないが……女性であるイレーネ嬢には……少々堪えることになるかもしれない」
「私のことはお気になさらずに結構ですよ? 以前も申し上げましたが、心配する身内もおりません。もとより落ちぶれて借金も抱えている私を娶ろうとするもの好きな男性はおりませんから。……あ、申し訳ございません。決してルシアン様がもの好きと言っているわけではありませんので」
奇妙な顔つきで自分を見つめるルシアンに、イレーネは自分が失言してしまったかと思い、謝罪した。
「いや。別に気にしていなから謝る必要はない。大体、この結婚は本当のものではないからな。あくまで1年間の契約婚だから」
「はい、勿論です。御安心下さい。1年後は後腐れないようにすっきり離婚致しますので。私とルシアン様はいわゆる雇用関係を結ぶようなものですから」
「ま、まぁ……確かにそうとも言えるな」
返事をしながらルシアンは複雑な気持ちを抱えていた。
(なんで、あんなに割り切ることが出来るのだ? つまり、俺は……イレーネ嬢からは男として全く見られていないということなのだろうか?)
それが妙に面白くない。
「あの、それでルシアン様……先程のお金の件ですが……」
「そうだったな。使用人たちが料理を運んできたから中断してしまっていたな。前借りとは一体何に使うのだ?」
「はい、服を買いたいのです」
「服を?」
「はい、見ての通り私はこのような服しか持ち合わせがなくて……ルシアン様の妻を演じるのであれば、それなりの服を着なくてはなりませんよね? そこで新しく新調したいと思いまして」
その言葉にルシアンは目を見開く。
「君は一体何を言ってるんだ!? 服ぐらい俺がいくらでも買ってやるに決まっているだろう!?」
「え? ですが……お給料までいただくのに、この上服まで買って頂くわけには……」
イレーネは何故ルシアンが興奮しているのか分からなかった。
「全く君って女性は……」
頭を抱え、深いため息をつくとルシアンは顔を上げた。
「いいか? 俺は君の1年間という時間と、さらに3年は再婚出来ないという結婚の権利を奪ってしまうんだ。だから俺と婚姻期間を設けている間は、必要な物なら全て買うつもりでいる。これも当然の報酬として受け取ってくれ」
(しかし……遠慮して拒絶されたらどう言って説得しよう……)
しかし、その考えは杞憂に終わった。
「本当ですか!? ありがとうございます、ルシアン様!」
笑顔でお礼を述べるイレーネ。
金銭的要素が絡んでくると、遠慮が無くなるイレーネは笑顔で返事をする。
何しろ、彼女はそれだけ貧しかったのだ。
「あ、ああ……お礼を言われるほどでは無い」
(そうだった。彼女はこういう女性だったんだ。だが、好意を笑顔で素直に受け取ってくれるのは……悪くないな)
美味しそうに食事を口に運ぶイレーネをルシアンはじっと見つめるのだった――
ルシアンはダイニングルームで給仕をする使用人たちを見渡した。普段なら給仕の人数は1人、ないし2人。
それなのに今朝に限っては違った。
2人のフットマンに、3人のメイドまでいるのだ。全員、明らかにイレーネを意識しているのは明白だった。
「紅茶はいつお持ちしますか?」
メイドがイレーネに尋ねる。
「そうですね、ルシアン様はいつお飲みになっておりますか?」
突然話をふられたルシアンは戸惑いながらも答えた。
「え? 俺は普段は食後にもらっているが?」
(あのメイドは何故そんなことを聞いてくるのだ? 普段は何も言わずに食後に紅茶を淹れてくるはずなのに! 大体、どこで俺とイレーネ嬢が朝食を一緒にとることがバレてしまったんだ? リカルドは何をしている!)
一言、リカルドに文句を言ってやりたいところだが肝心の彼は生憎不在だ。
(くそ! ここ最近、勝手な真似ばかりしおって……後で呼び出して説教してやらなければ……!)
ルシアンのどこか落ち着きのない様子をみて、イレーネが首を傾げる。
「ルシアン様、どうかされたのですか?」
「え? あ……何でも無い。ただ……何故、今朝に限ってこんなに給仕が集まっているのか不思議に思ってな」
その言葉に、使用人たちが一斉に肩をビクリとさせる。
「もう、全ての料理を並べ終えたのだろう?」
傍らに立っているフットマンに尋ねるルシアン。
「は、はい。ルシアン様。食事は全て提供させていただきました」
「そうか……なら、お前たちはもう席を外してくれ。彼女と2人きりで食事をしたいからな」
ルシアンはゆっくり、全員の顔を見渡した。
「分かりました……それでは我々は一旦席を外させていただきます……」
使用人たちはチラチラとイレーネに視線を送りながら、ダイニングルームを出て行った。
――パタン
扉が閉じられるとルシアンはため息をついた。
「全く……好奇心旺盛な使用人たちだ。さて、それでは食べようか」
「私も好奇心旺盛ですよ? それにしてもこのマイスター家には大勢の人たちが働いていらっしゃるのですね。私の働く隙もないほどです。……まぁ! 本当にこちらのお食事は美味しいですね」
料理を口にし、笑みを浮かべるイレーネ。
「そうか、口にあって何よりだ。だが、メイドの仕事は考えないでくれ。君の役目は俺の妻を演じることなのだから。実は……まだ使用人たちには君が妻になることを報告していないのだ。何しろ、この結婚は1年間という期間限定の契約婚だからな。かと言って、本当のことを話すわけにもいかないし……」
「本当のことは話さずに、私と結婚するとお話すれば良いのではありませんか?」
「それは確かにそうなのだが……しかし、1年で離婚することになるからな。自分の評判は落ちても構わないが……女性であるイレーネ嬢には……少々堪えることになるかもしれない」
「私のことはお気になさらずに結構ですよ? 以前も申し上げましたが、心配する身内もおりません。もとより落ちぶれて借金も抱えている私を娶ろうとするもの好きな男性はおりませんから。……あ、申し訳ございません。決してルシアン様がもの好きと言っているわけではありませんので」
奇妙な顔つきで自分を見つめるルシアンに、イレーネは自分が失言してしまったかと思い、謝罪した。
「いや。別に気にしていなから謝る必要はない。大体、この結婚は本当のものではないからな。あくまで1年間の契約婚だから」
「はい、勿論です。御安心下さい。1年後は後腐れないようにすっきり離婚致しますので。私とルシアン様はいわゆる雇用関係を結ぶようなものですから」
「ま、まぁ……確かにそうとも言えるな」
返事をしながらルシアンは複雑な気持ちを抱えていた。
(なんで、あんなに割り切ることが出来るのだ? つまり、俺は……イレーネ嬢からは男として全く見られていないということなのだろうか?)
それが妙に面白くない。
「あの、それでルシアン様……先程のお金の件ですが……」
「そうだったな。使用人たちが料理を運んできたから中断してしまっていたな。前借りとは一体何に使うのだ?」
「はい、服を買いたいのです」
「服を?」
「はい、見ての通り私はこのような服しか持ち合わせがなくて……ルシアン様の妻を演じるのであれば、それなりの服を着なくてはなりませんよね? そこで新しく新調したいと思いまして」
その言葉にルシアンは目を見開く。
「君は一体何を言ってるんだ!? 服ぐらい俺がいくらでも買ってやるに決まっているだろう!?」
「え? ですが……お給料までいただくのに、この上服まで買って頂くわけには……」
イレーネは何故ルシアンが興奮しているのか分からなかった。
「全く君って女性は……」
頭を抱え、深いため息をつくとルシアンは顔を上げた。
「いいか? 俺は君の1年間という時間と、さらに3年は再婚出来ないという結婚の権利を奪ってしまうんだ。だから俺と婚姻期間を設けている間は、必要な物なら全て買うつもりでいる。これも当然の報酬として受け取ってくれ」
(しかし……遠慮して拒絶されたらどう言って説得しよう……)
しかし、その考えは杞憂に終わった。
「本当ですか!? ありがとうございます、ルシアン様!」
笑顔でお礼を述べるイレーネ。
金銭的要素が絡んでくると、遠慮が無くなるイレーネは笑顔で返事をする。
何しろ、彼女はそれだけ貧しかったのだ。
「あ、ああ……お礼を言われるほどでは無い」
(そうだった。彼女はこういう女性だったんだ。だが、好意を笑顔で素直に受け取ってくれるのは……悪くないな)
美味しそうに食事を口に運ぶイレーネをルシアンはじっと見つめるのだった――