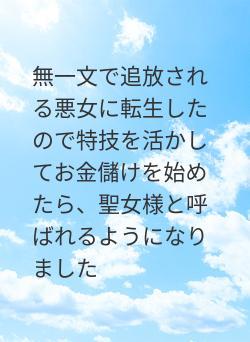――翌朝6時
朝早くからリカルドはルシアンの部屋に呼び出しを受けていた。
「ルシアン様、こんなに朝早くから呼び出しとは一体どの様な御要件でしょうか?」
スーツ姿に身を包んだリカルドが尋ねる。
「今日、イレーネがあの空き家に行くことは知っているな?」
着替えをしながら問いかけるルシアン。
「ええ、勿論です。昨日の話ではありませんか」
「なら話は早い。リカルド、ここの仕事はしなくて良いから今日は1日イレーネに付き合え。一緒にあの家に行き、片付けの手伝いをするように」
「ええっ!? な、何故私も一緒に行かなければならないのです? 今日は私も大事な用事があるのですよ? 倉庫の茶葉の在庫管理をしなくてはならないのですから!」
「そんな仕事は他の者に任せろ、何はともあれイレーネを最優先にするのだ」
ルシアンはネクタイを締めると、リカルドをジロリと見る。
「何故です!? 第一、イレーネさんは付き添いは不要と仰っていたではありませんか!」
「ああ。確かに彼女はそう言った。だがな……考えても見ろ! あの屋敷……彼女が出ていった後、そのままの状態だったじゃないか!」
「いいえ、そのままの状態ではありませんよ? あの方のドレスや化粧品……私物類は全て持っていかれましたから。残されているのはマイスター家で用意した家財道具一式です」
「屁理屈を抜かすな! そんなことを言っているのではない! もし、万一……いいか、万一だぞ? 彼女の痕跡が何処かに残っていたらどうするのだ! 持ち忘れた私物や何かがあるかもしれないだろう!? それをイレーネに見つかる前に探して処分しろ!」
あまりにも無茶振りを言ってくるルシアンにリカルドは悲鳴じみた声を上げる。
「ええ!? 無茶を仰らないで下さい! そんなことはルシアン様でなければ分かるはずないじゃありませんか! ルシアン様が行って下さい!」
「行けるものならとっくに行ってる! だがな、今日はどうしても外せない商談があるんだ! 今更キャンセルさせて下さい、とは言えない相手なんだよ!!」
「そんな! あまりにも横暴です! どうして私なんですか!?」
何としても引き受けたくないリカルドは必死で首を振る。
「お前以外に誰に頼めるというのだ! この屋敷で働く者はお前以外、誰も彼女の存在を知りもしないのだぞ!」
「うっ! で、ですが……」
思わず言い含められそうになるリカルドだが、あることに気づく。
「別によいではありませんか? イレーネさんに、あの方のことを知られても」
「何だと?」
ルシアンの眉が上がる。
「そもそも、今回のお二人の御縁はルシアン様を当主にする為に契約を結んだ関係なのですよ? お互いに恋愛感情があるわけではありませよね? 第一、もう終わった関係ではありませんか?」
「……確かに、そうだな……」
リカルドの言葉にルシアンは頷く。
(そうだ、確かにリカルドの言う通りだ。俺とイレーネは互いの利害関係で契約を結んだだけの関係……なのに何故だ? 何故……俺はイレーネに彼女のことをしられたくないと思っているのだろう……)
リカルドの言う通りではあったが、それでもイレーネには知られたくないという気持ちが勝っていた。
「ええ。ですから仮にあの女性の痕跡が残されていて、それをイレーネさんが発見しても何も問題はないということです」
すると……。
「リカルド……お前というやつは本当に薄情な男だったのだな」
ルシアンがため息をつく。
「ええっ!? こ、今度は一体何ですか!?」
「考えても見ろ? イレーネは今日から暫くの間、あの屋敷に寝泊まりするのだぞ? そのために沢山荷物を運ぶはずだ」
「はい……恐らくそうでしょうね」
「お前はあんなか弱い女性に、たった1人で屋敷まで荷物を運ばせるつもりか?」
別にイレーネがか弱いとは思っていない。むしろ逞しいくらいなのだが、あえてルシアンはリカルドに揺さぶりをかける。
「う!」
痛い所をつかれるリカルド。
「可哀想に……イレーネはあんな細腕なのに、たった1人で荷物を運んで掃除までするのか……イレーネはお前が選んだ相手だというのに……」
「そ、それは……」
「俺はどうしても行けないから、お前に頼んでいるというのに……イレーネのことを散々心配しているような口ぶりのくせに、実際に行動には移せないのだな」
「分かりました! 行きます! イレーネさんと一緒に本日、お屋敷に行ってまいります!」
まるで脅迫のような言葉に、とうとうリカルドは折れてしまった。
「そうか。快く引き受けてくれて感謝する。流石はリカルドだ、助かるよ。今回の件については後で特別手当を出そう」
ルシアンはニコニコしながらリカルドに礼を述べる。
「いいえ……私の主はルシアン様ですから……当然のことではありませんか……ハハハハ……」
リカルドは引きつった笑みを浮かべるのだった――
朝早くからリカルドはルシアンの部屋に呼び出しを受けていた。
「ルシアン様、こんなに朝早くから呼び出しとは一体どの様な御要件でしょうか?」
スーツ姿に身を包んだリカルドが尋ねる。
「今日、イレーネがあの空き家に行くことは知っているな?」
着替えをしながら問いかけるルシアン。
「ええ、勿論です。昨日の話ではありませんか」
「なら話は早い。リカルド、ここの仕事はしなくて良いから今日は1日イレーネに付き合え。一緒にあの家に行き、片付けの手伝いをするように」
「ええっ!? な、何故私も一緒に行かなければならないのです? 今日は私も大事な用事があるのですよ? 倉庫の茶葉の在庫管理をしなくてはならないのですから!」
「そんな仕事は他の者に任せろ、何はともあれイレーネを最優先にするのだ」
ルシアンはネクタイを締めると、リカルドをジロリと見る。
「何故です!? 第一、イレーネさんは付き添いは不要と仰っていたではありませんか!」
「ああ。確かに彼女はそう言った。だがな……考えても見ろ! あの屋敷……彼女が出ていった後、そのままの状態だったじゃないか!」
「いいえ、そのままの状態ではありませんよ? あの方のドレスや化粧品……私物類は全て持っていかれましたから。残されているのはマイスター家で用意した家財道具一式です」
「屁理屈を抜かすな! そんなことを言っているのではない! もし、万一……いいか、万一だぞ? 彼女の痕跡が何処かに残っていたらどうするのだ! 持ち忘れた私物や何かがあるかもしれないだろう!? それをイレーネに見つかる前に探して処分しろ!」
あまりにも無茶振りを言ってくるルシアンにリカルドは悲鳴じみた声を上げる。
「ええ!? 無茶を仰らないで下さい! そんなことはルシアン様でなければ分かるはずないじゃありませんか! ルシアン様が行って下さい!」
「行けるものならとっくに行ってる! だがな、今日はどうしても外せない商談があるんだ! 今更キャンセルさせて下さい、とは言えない相手なんだよ!!」
「そんな! あまりにも横暴です! どうして私なんですか!?」
何としても引き受けたくないリカルドは必死で首を振る。
「お前以外に誰に頼めるというのだ! この屋敷で働く者はお前以外、誰も彼女の存在を知りもしないのだぞ!」
「うっ! で、ですが……」
思わず言い含められそうになるリカルドだが、あることに気づく。
「別によいではありませんか? イレーネさんに、あの方のことを知られても」
「何だと?」
ルシアンの眉が上がる。
「そもそも、今回のお二人の御縁はルシアン様を当主にする為に契約を結んだ関係なのですよ? お互いに恋愛感情があるわけではありませよね? 第一、もう終わった関係ではありませんか?」
「……確かに、そうだな……」
リカルドの言葉にルシアンは頷く。
(そうだ、確かにリカルドの言う通りだ。俺とイレーネは互いの利害関係で契約を結んだだけの関係……なのに何故だ? 何故……俺はイレーネに彼女のことをしられたくないと思っているのだろう……)
リカルドの言う通りではあったが、それでもイレーネには知られたくないという気持ちが勝っていた。
「ええ。ですから仮にあの女性の痕跡が残されていて、それをイレーネさんが発見しても何も問題はないということです」
すると……。
「リカルド……お前というやつは本当に薄情な男だったのだな」
ルシアンがため息をつく。
「ええっ!? こ、今度は一体何ですか!?」
「考えても見ろ? イレーネは今日から暫くの間、あの屋敷に寝泊まりするのだぞ? そのために沢山荷物を運ぶはずだ」
「はい……恐らくそうでしょうね」
「お前はあんなか弱い女性に、たった1人で屋敷まで荷物を運ばせるつもりか?」
別にイレーネがか弱いとは思っていない。むしろ逞しいくらいなのだが、あえてルシアンはリカルドに揺さぶりをかける。
「う!」
痛い所をつかれるリカルド。
「可哀想に……イレーネはあんな細腕なのに、たった1人で荷物を運んで掃除までするのか……イレーネはお前が選んだ相手だというのに……」
「そ、それは……」
「俺はどうしても行けないから、お前に頼んでいるというのに……イレーネのことを散々心配しているような口ぶりのくせに、実際に行動には移せないのだな」
「分かりました! 行きます! イレーネさんと一緒に本日、お屋敷に行ってまいります!」
まるで脅迫のような言葉に、とうとうリカルドは折れてしまった。
「そうか。快く引き受けてくれて感謝する。流石はリカルドだ、助かるよ。今回の件については後で特別手当を出そう」
ルシアンはニコニコしながらリカルドに礼を述べる。
「いいえ……私の主はルシアン様ですから……当然のことではありませんか……ハハハハ……」
リカルドは引きつった笑みを浮かべるのだった――