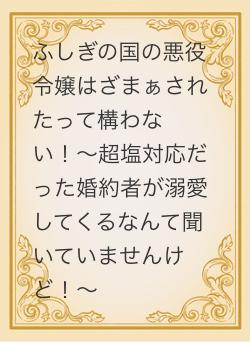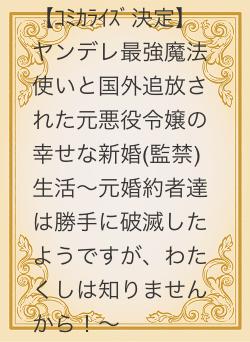「あの……そんな風にしていただかなくても、もう十分ですわ」
「もしかして何か気に入らないことがあっただろうか?」
「い、いえ! 贅沢できてありがたいのですが少々やりすぎではないでしょうか?」
フランソワーズの言葉にステファンはこれでもかと、目を見開いている。
シュバリタイア王国では宝玉を守るのは当然のことだった。
正直、ここまで感謝されているとこちらも腰がひ意味がフランソワーズにはわからない。
「フランソワーズ、君は僕たちを苦しめていた悪魔を祓ってくれたんだ」
「わたくし、そんな大したことはしておりません。あの程度の悪魔は……」
聖女だと当たり前に祓えるような気もしたのだが、フランソワーズは実際に他の聖女の力を見たことがないことを思い出す。
王妃には宝玉の抑え方を教わっていたが、フランソワーズ一人で大丈夫だということがわかると、一緒に祈ることもなくなってしまった。
それにステファンも聖女に頼んだことがあると言っていたが、この悪魔は祓えなかったと言っていた。
(わたくしは聖女としての力が強い方だとしても、マドレーヌには敵わないでしょうし……)