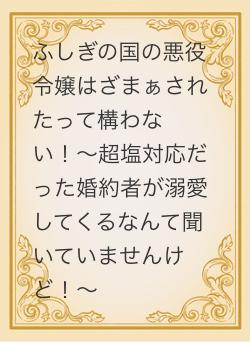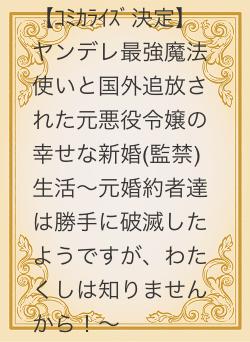「簡単なことですわ。セドリック殿下。パーティー会場でこのような大見得を切って〝嘘〟だなんて、ありえませんわよねぇ?」
狼狽えるマドレーヌとは違い、煽られたセドリックの額には青筋が浮かんでいる。
今までフランソワーズにこのように言われたことがないからだろう。
フランソワーズは何があっても、ただ黙ってすべてを受け入れていた。
どれだけ尽くしても彼女は愛されることはないのに。
「……いいだろう」
「ま、待ってください! セドリック殿下」
「どうした? マドレーヌ、自らの身の潔白を証明するチャンスだぞ?」
「そんなことやらなくても……本当に、わたしはっ! 信じてください。セドリック殿下っ」
「もちろん俺はマドレーヌを信じている。だからこそ真実を明らかにして、フランソワーズが悪なのだと、証明しなければならないのではないのか?」
「……っ!」
口ごもるマドレーヌを見るのは気分がいい。
今まで何をされても黙り続けていたフランソワーズのまさかの反撃に彼女はたじろいでいる。
そしてこの会話やマドレーヌの反応で大体、勘がいいものは気づき始めるだろう。
これが茶番劇であると……。
狼狽えるマドレーヌとは違い、煽られたセドリックの額には青筋が浮かんでいる。
今までフランソワーズにこのように言われたことがないからだろう。
フランソワーズは何があっても、ただ黙ってすべてを受け入れていた。
どれだけ尽くしても彼女は愛されることはないのに。
「……いいだろう」
「ま、待ってください! セドリック殿下」
「どうした? マドレーヌ、自らの身の潔白を証明するチャンスだぞ?」
「そんなことやらなくても……本当に、わたしはっ! 信じてください。セドリック殿下っ」
「もちろん俺はマドレーヌを信じている。だからこそ真実を明らかにして、フランソワーズが悪なのだと、証明しなければならないのではないのか?」
「……っ!」
口ごもるマドレーヌを見るのは気分がいい。
今まで何をされても黙り続けていたフランソワーズのまさかの反撃に彼女はたじろいでいる。
そしてこの会話やマドレーヌの反応で大体、勘がいいものは気づき始めるだろう。
これが茶番劇であると……。