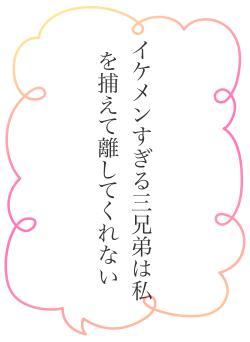哀が甘い声で耳元で囁く。
「紫乃がここに居ることが幸せだ。好き、大好き。紫乃が足りない」
「待ってっ……」
私が勢いよく哀を押した。
すると、気がついた時には体のバランスが崩れていっていて、勢いよく私たちはソファから転げ落ちてしまった。
バターンっと二人で床に倒れ込んだ。
抱きしめる手はまだ緩まない。
そのまま私を強く抱き締めて、私の顔にもう一度重ねる。
もっと甘い、深くてとろけるようなキスだ。
苦しいけど、それが愛を感じられて嬉しかった。
深夜三時、私は彼の溺愛度を知りました---。
「紫乃がここに居ることが幸せだ。好き、大好き。紫乃が足りない」
「待ってっ……」
私が勢いよく哀を押した。
すると、気がついた時には体のバランスが崩れていっていて、勢いよく私たちはソファから転げ落ちてしまった。
バターンっと二人で床に倒れ込んだ。
抱きしめる手はまだ緩まない。
そのまま私を強く抱き締めて、私の顔にもう一度重ねる。
もっと甘い、深くてとろけるようなキスだ。
苦しいけど、それが愛を感じられて嬉しかった。
深夜三時、私は彼の溺愛度を知りました---。