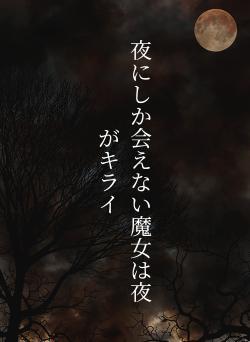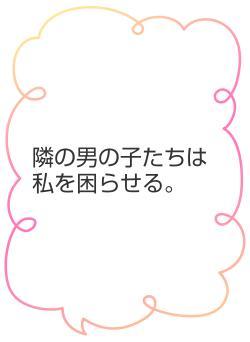「あの時ね…、もう本当に終わりだと思ったの。これで楽になれるんだって思った、もう終わりでもいいって…」
きゅってお母さんが力を入れる。
握られた手に熱を帯びる。
「だけどね、浮かんで来たのは千和の顔だった」
私の手を握って、ぎゅーって強く握って、涙を流しながら私の顔を見てた。
「ごめんね千和…っ、お母さんこんなだから千和にいっぱい辛い思いさせて千和のことたくさん悲しませて」
「…っ」
「千和のこと全然考えてあげられなかった、ひどい事も言ったし、傷つけたよね…っ」
頬を伝って涙が流れていくのがわかった。
表情も追い付かなくて瞬きさえ出来ない、ただただ涙が流れていく。
「ありがとう、千和」
繋いでいた手の上にさらにお母さんが手を重ねる。
両手で私の手を包んで、優しくなでた。
「千和が救急車呼んでくれたのね」
すごくやつれた顔をしていた。
すごく力のない声をしていた。
お母さんがお母さんじゃないみたいだった。
だけど、私はずっとずっとこうしてお母さんと話がしたかった。
「お母さん…っ!」
ガタンッと椅子が後ろに倒れた、勢いよく立ち上がったから。
お母さんの胸の中に飛び込むように、ぎゅって抱きしめられたくて。
もう私のことなんてどうでもいいんだって思ってた。
もう私を見てくれることなんてないんだって思ってた。
だけど、私は捨てられなかったから。
捨てたくなかった。
「千和っ、ごめんね…ごめんね」
「…っ」
「1番大事だったはずなのに、千和が1番大事だったのに…っ」
「お母さん…っ」
いっぱいいっぱい言いたかったことがあったはずなのに、泣くばっかりで何も言えなくて。
抱きしめられた腕の中があったかくて、背中をなでてくれる手が懐かしくて、私の名前を呼ぶ声が変わらなくて。
お母さん、私ここにいるの。
ずっとここにいるの。
「お母さん、死なないで!ずっとずっと私といてっ、私のこと置いてかないで…!」
気付いてくれた?
やっと見てくれるの?
私、さみしかったよ…っ
「うん…っ、ごめんね」
お母さんの背中に手を回してきゅうっとパジャマを掴む。
力いっぱい、離れたくなくてもう絶対離したくなくて。
「ごめんね…っ、お母さん間違ってたね…」
わんわんと泣いた。
子供みたいに、声を出しながら…
でも私子供だし、まだまだ全然子供だもん。
だからお母さんずっとそばにいて、私のこと諦めないで。
もうどこにも行かないで。
きゅってお母さんが力を入れる。
握られた手に熱を帯びる。
「だけどね、浮かんで来たのは千和の顔だった」
私の手を握って、ぎゅーって強く握って、涙を流しながら私の顔を見てた。
「ごめんね千和…っ、お母さんこんなだから千和にいっぱい辛い思いさせて千和のことたくさん悲しませて」
「…っ」
「千和のこと全然考えてあげられなかった、ひどい事も言ったし、傷つけたよね…っ」
頬を伝って涙が流れていくのがわかった。
表情も追い付かなくて瞬きさえ出来ない、ただただ涙が流れていく。
「ありがとう、千和」
繋いでいた手の上にさらにお母さんが手を重ねる。
両手で私の手を包んで、優しくなでた。
「千和が救急車呼んでくれたのね」
すごくやつれた顔をしていた。
すごく力のない声をしていた。
お母さんがお母さんじゃないみたいだった。
だけど、私はずっとずっとこうしてお母さんと話がしたかった。
「お母さん…っ!」
ガタンッと椅子が後ろに倒れた、勢いよく立ち上がったから。
お母さんの胸の中に飛び込むように、ぎゅって抱きしめられたくて。
もう私のことなんてどうでもいいんだって思ってた。
もう私を見てくれることなんてないんだって思ってた。
だけど、私は捨てられなかったから。
捨てたくなかった。
「千和っ、ごめんね…ごめんね」
「…っ」
「1番大事だったはずなのに、千和が1番大事だったのに…っ」
「お母さん…っ」
いっぱいいっぱい言いたかったことがあったはずなのに、泣くばっかりで何も言えなくて。
抱きしめられた腕の中があったかくて、背中をなでてくれる手が懐かしくて、私の名前を呼ぶ声が変わらなくて。
お母さん、私ここにいるの。
ずっとここにいるの。
「お母さん、死なないで!ずっとずっと私といてっ、私のこと置いてかないで…!」
気付いてくれた?
やっと見てくれるの?
私、さみしかったよ…っ
「うん…っ、ごめんね」
お母さんの背中に手を回してきゅうっとパジャマを掴む。
力いっぱい、離れたくなくてもう絶対離したくなくて。
「ごめんね…っ、お母さん間違ってたね…」
わんわんと泣いた。
子供みたいに、声を出しながら…
でも私子供だし、まだまだ全然子供だもん。
だからお母さんずっとそばにいて、私のこと諦めないで。
もうどこにも行かないで。