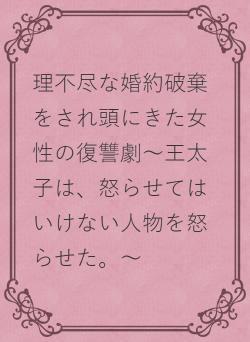晴れてアヤメと恋人関係になれた俺は、とある人物のいる部屋に来ていた。そして、部屋のドアをノックすると部屋の主から入出許可をもらい入った。
「いきなりすみません、今お時間よろしいですか、アドマンス夫人」
「えぇ、構わないわ」
そう、俺が会いに来たのはアヤメの母君、メルティアナ・アドマンス夫人だ。
さ、座って。と夫人の座ったソファーの向かいに座らせてもらった。
「実は、つい先程アヤメさんとお付き合いする事になりました」
「あら、タクミ君とアヤメちゃんが?」
「はい」
「あらあらお似合いじゃな~い! さては、タクミ君一人で来たって事はアヤメちゃん恥ずかしがっちゃって止められちゃった?」
「まぁ、はい、そんな所です」
さっきアヤメには、周りに言うのはまだいいんじゃない? とはぐらかされてしまった。
でも、さすがに俺らはここに連れてきてもらってる身だから、嘘ついてるような事は出来ないだろ。というか耐えられない。
最初に誘ってくれたのはアヤメだったとしても、ここに来てもいいと許可をしてくださったのは夫人。だから夫人のお陰で俺らはこうして干からびずに済んでるんだ。
しかも、首都に帰るのまだ1週間以上もあるんだぜ? 無理。ごめん、アヤメ。ほんとに。
「じゃあタクミ君が言った事は絶対言わないわ。炊飯器の話をしたって事にしましょ!」
「はい、助かります」
なんかすごくノリノリだな、まぁいいか。
「そっかぁ、アヤメちゃんがねぇ~。そういう話ってアヤメちゃん中々してくれないのよ~、恋バナを娘とするのはちょっと夢だったのにぃ。ほら、ウチってあの息子だけだったじゃない? しかも可愛げが全くないわ全然帰ってこないわでほんっっっと面白くないのよ。一体誰に似たのかしら」
なんか、夫人スイッチ入った? 中々話が止まらないぞ……?
「タクミ君から告白したの?」
「あ、はい」
「あら~、何て言ったの? どんな感じ? もうチューした?」
「え”っ」
「あ、彼女のお母さんだから話しづらいかしら? ごめんねぇ、つい嬉しくって。アヤメちゃんから聞くから許してね」
「……」
……俺、何て言ったらいいんだ?
なんか、きゃーきゃー楽しそうなんだが。
「も~アヤメちゃんたらこんなカッコいい美男子イケメン捕まえっちゃって~! しかもお料理に関してはプロよプロ! 顔も良くて性格も良くてお料理も完璧なんて優良物件じゃない! 毎日愛情たっぷりで美味しいお料理が食べられるなんて幸せじゃな~い!」
あの、恥ずかしいのでこの辺で勘弁してくださいませんか。
「あの、夫人?」
「ねぇねぇタクミ君、私達の馴れ初めの話してもいいかしら?」
「え? あ、はい、どうぞ」
「ありがと♪ じゃあね~、私がこの国の国王の妹、元王女だって知ってるかしら?」
「はい、聞いてます」
「バートと結婚する前にね、私には婚約者がいたの。あ、違う人よ。まぁ、気が合わないし私の事ちゃんと見てくれない人だったわ。顔見ただけで虫唾が走るくらいね」
夫人って、こんな事言う人だったのか。てか、いいのか、俺これ聞いて。
「当時バートは近衛騎士団長だったからよく王宮で会う事があったの。まぁ色々あってね。好きだったから猛アタックしてたんだけど表情を変えずに全部スルー。でもめげずに頑張ったのよ? でも、結婚式が来ちゃってね~。そんな事言ってられなくなっちゃったの。
でもね、結婚式の1週間前、バートが言ってくれたのよ。
全然表情を出さなかったくせして、その時は本当に困った顔で赤くしててね。『私は姫様の前だと我慢がきかないみたいです。姫様の結婚が心から喜べません』って。
私には、それだけで十分だったわ」
「え……じゃあ、」
「そ。この人と結婚したいって駄々こねちゃった♪」
「えぇえ!?」
え、駄々こねた? 婚約者との結婚式前に? でもそれで通っちゃったって事か……いいのか?
てか、表情を出さない人? 俺らの知ってる公爵様って表情豊かだろ? あ、そういえばアヤメのお兄さん、そんな感じだったな。なるほど、あんな感じか。
「この国の王女を婚約者からぶん取っても、今騎士団総括という地位に付けてる。それはそれだけバートに力があったという事よ。私もこうやって幸せでいられる。
じゃあ、タクミ君は?」
「……え?」
「タクミ君の強さとは何かしら」
俺の、強さ……?
「貴方達は生まれた国も、星すらも違うわ。それにアヤメちゃんは異世界人だから、勿論色々と苦難、苦労も沢山ある。悩む事も、傷付くこともある。それを分ってて来てくれたのよね?」
「……はい」
アヤメは異世界人、そりゃ勿論絶対苦労する事は分かってる。それでも、アヤメの特別でいたくてああ言った。
ここに来て、その気持ちは大きくなったんだ。
『あの兄妹、アヤメお嬢様と馴れ馴れしすぎないか?』
『確かに、タメ口だぜ?』
『あぁ、あの方達貴族なんですって』
『マジ? でも他国のだろ』
『でも、あの人達の祖父がアヤメお嬢様と同じ故郷の人なんだって聞いたわ。家族みたいな感じ?』
『あぁ、そういうね。確かに髪とか瞳の色とか一緒だもんね』
『い~な~』
こんな話を偶然聞いた。確かに、最初は親近感があって接してきたけれど、決して家族のような気持ちで接してきたわけじゃない。
兄のような気持ちになった事だって、たったの一度もない。
アヤメを異世界人としか見てない奴らが送ってきた釣書の件だって、あの伯爵子息の件だって、我慢ならなかった事は分かってるけれど、そういう気持ちから来てるわけじゃない。
『えっ、アヤメお嬢様って故郷では貴族じゃなかったのか?』
『だって。普通の家庭で育ったみたい』
『ふぅん』
『何、狙ってるの? やめときな、以前は平民でもここではアドマンス家のご令嬢よ?』
『うん、まぁそうなんだけどさぁ』
友達って言われたけれど、俺は違った感情で見てほしかった。
アヤメにどこにも行ってほしくなかった。
周りなんて見ないで、ただ俺だけを見ていてほしかった。
でもこれを言ったら今までの関係が壊れてしまうと分かっていたけれど、我慢が出来ずに言ってしまった。
だけど、
『私も一緒』
そう言ってくれて、今まで苦しかったものが一気に消えた様な気がした。
それと同時に、使命感にも駆られた。恋人という存在がいる事でアヤメを守れる事が一つだけでもあるのであれば、俺は絶対に守りたい。
そう、思ってしまった。
「私達は、アヤメちゃんの幸せを一番に考えてるわ。自分達の娘なんですもの、当たり前の事よ。だから、どこの馬の骨かも分からない腰抜けや骨なしの奴らから守ってあげたいの。でもその役目を、アヤメちゃんが選んだタクミ君がしてくれるのなら、私は嬉しいわ。
だからタクミ君、自分の強さを見つけて成長してちょうだい。アヤメちゃんを守れて、幸せに出来る力をね」
「……はい!」
何かあったら言ってちょうだい、と夫人の言葉を頂いて、部屋を退出した。
俺は外国生まれだから別れてちょうだい、とか言われんじゃないかって思ってはいたけれど、まさかああ言って下さるとは思ってなかった。てか、夫人の衝撃的事実を目の当たりにしてしまったけど、俺が聞いていいものだったのだろうか。
でも夫人があんな人だったのかと吃驚もしてる。
俺の強さ、か。
俺の強さとは何だろうか。俺に出来る事、料理か。ついさっき俺らの作る料理食うと幸せな気持ちになる、なぁんて言ってたな。夫人の言ってたそれとは違うと思うけど、自分の料理でアヤメを幸せにする自信はある。
異世界人のアヤメを守る為には、どうしたらいいのか。
まぁ、それはゆっくり考えよう。そろそろ夕飯の準備始めないと。食いしん坊な誰かさんが美味しいご飯をご所望だしな。
「いきなりすみません、今お時間よろしいですか、アドマンス夫人」
「えぇ、構わないわ」
そう、俺が会いに来たのはアヤメの母君、メルティアナ・アドマンス夫人だ。
さ、座って。と夫人の座ったソファーの向かいに座らせてもらった。
「実は、つい先程アヤメさんとお付き合いする事になりました」
「あら、タクミ君とアヤメちゃんが?」
「はい」
「あらあらお似合いじゃな~い! さては、タクミ君一人で来たって事はアヤメちゃん恥ずかしがっちゃって止められちゃった?」
「まぁ、はい、そんな所です」
さっきアヤメには、周りに言うのはまだいいんじゃない? とはぐらかされてしまった。
でも、さすがに俺らはここに連れてきてもらってる身だから、嘘ついてるような事は出来ないだろ。というか耐えられない。
最初に誘ってくれたのはアヤメだったとしても、ここに来てもいいと許可をしてくださったのは夫人。だから夫人のお陰で俺らはこうして干からびずに済んでるんだ。
しかも、首都に帰るのまだ1週間以上もあるんだぜ? 無理。ごめん、アヤメ。ほんとに。
「じゃあタクミ君が言った事は絶対言わないわ。炊飯器の話をしたって事にしましょ!」
「はい、助かります」
なんかすごくノリノリだな、まぁいいか。
「そっかぁ、アヤメちゃんがねぇ~。そういう話ってアヤメちゃん中々してくれないのよ~、恋バナを娘とするのはちょっと夢だったのにぃ。ほら、ウチってあの息子だけだったじゃない? しかも可愛げが全くないわ全然帰ってこないわでほんっっっと面白くないのよ。一体誰に似たのかしら」
なんか、夫人スイッチ入った? 中々話が止まらないぞ……?
「タクミ君から告白したの?」
「あ、はい」
「あら~、何て言ったの? どんな感じ? もうチューした?」
「え”っ」
「あ、彼女のお母さんだから話しづらいかしら? ごめんねぇ、つい嬉しくって。アヤメちゃんから聞くから許してね」
「……」
……俺、何て言ったらいいんだ?
なんか、きゃーきゃー楽しそうなんだが。
「も~アヤメちゃんたらこんなカッコいい美男子イケメン捕まえっちゃって~! しかもお料理に関してはプロよプロ! 顔も良くて性格も良くてお料理も完璧なんて優良物件じゃない! 毎日愛情たっぷりで美味しいお料理が食べられるなんて幸せじゃな~い!」
あの、恥ずかしいのでこの辺で勘弁してくださいませんか。
「あの、夫人?」
「ねぇねぇタクミ君、私達の馴れ初めの話してもいいかしら?」
「え? あ、はい、どうぞ」
「ありがと♪ じゃあね~、私がこの国の国王の妹、元王女だって知ってるかしら?」
「はい、聞いてます」
「バートと結婚する前にね、私には婚約者がいたの。あ、違う人よ。まぁ、気が合わないし私の事ちゃんと見てくれない人だったわ。顔見ただけで虫唾が走るくらいね」
夫人って、こんな事言う人だったのか。てか、いいのか、俺これ聞いて。
「当時バートは近衛騎士団長だったからよく王宮で会う事があったの。まぁ色々あってね。好きだったから猛アタックしてたんだけど表情を変えずに全部スルー。でもめげずに頑張ったのよ? でも、結婚式が来ちゃってね~。そんな事言ってられなくなっちゃったの。
でもね、結婚式の1週間前、バートが言ってくれたのよ。
全然表情を出さなかったくせして、その時は本当に困った顔で赤くしててね。『私は姫様の前だと我慢がきかないみたいです。姫様の結婚が心から喜べません』って。
私には、それだけで十分だったわ」
「え……じゃあ、」
「そ。この人と結婚したいって駄々こねちゃった♪」
「えぇえ!?」
え、駄々こねた? 婚約者との結婚式前に? でもそれで通っちゃったって事か……いいのか?
てか、表情を出さない人? 俺らの知ってる公爵様って表情豊かだろ? あ、そういえばアヤメのお兄さん、そんな感じだったな。なるほど、あんな感じか。
「この国の王女を婚約者からぶん取っても、今騎士団総括という地位に付けてる。それはそれだけバートに力があったという事よ。私もこうやって幸せでいられる。
じゃあ、タクミ君は?」
「……え?」
「タクミ君の強さとは何かしら」
俺の、強さ……?
「貴方達は生まれた国も、星すらも違うわ。それにアヤメちゃんは異世界人だから、勿論色々と苦難、苦労も沢山ある。悩む事も、傷付くこともある。それを分ってて来てくれたのよね?」
「……はい」
アヤメは異世界人、そりゃ勿論絶対苦労する事は分かってる。それでも、アヤメの特別でいたくてああ言った。
ここに来て、その気持ちは大きくなったんだ。
『あの兄妹、アヤメお嬢様と馴れ馴れしすぎないか?』
『確かに、タメ口だぜ?』
『あぁ、あの方達貴族なんですって』
『マジ? でも他国のだろ』
『でも、あの人達の祖父がアヤメお嬢様と同じ故郷の人なんだって聞いたわ。家族みたいな感じ?』
『あぁ、そういうね。確かに髪とか瞳の色とか一緒だもんね』
『い~な~』
こんな話を偶然聞いた。確かに、最初は親近感があって接してきたけれど、決して家族のような気持ちで接してきたわけじゃない。
兄のような気持ちになった事だって、たったの一度もない。
アヤメを異世界人としか見てない奴らが送ってきた釣書の件だって、あの伯爵子息の件だって、我慢ならなかった事は分かってるけれど、そういう気持ちから来てるわけじゃない。
『えっ、アヤメお嬢様って故郷では貴族じゃなかったのか?』
『だって。普通の家庭で育ったみたい』
『ふぅん』
『何、狙ってるの? やめときな、以前は平民でもここではアドマンス家のご令嬢よ?』
『うん、まぁそうなんだけどさぁ』
友達って言われたけれど、俺は違った感情で見てほしかった。
アヤメにどこにも行ってほしくなかった。
周りなんて見ないで、ただ俺だけを見ていてほしかった。
でもこれを言ったら今までの関係が壊れてしまうと分かっていたけれど、我慢が出来ずに言ってしまった。
だけど、
『私も一緒』
そう言ってくれて、今まで苦しかったものが一気に消えた様な気がした。
それと同時に、使命感にも駆られた。恋人という存在がいる事でアヤメを守れる事が一つだけでもあるのであれば、俺は絶対に守りたい。
そう、思ってしまった。
「私達は、アヤメちゃんの幸せを一番に考えてるわ。自分達の娘なんですもの、当たり前の事よ。だから、どこの馬の骨かも分からない腰抜けや骨なしの奴らから守ってあげたいの。でもその役目を、アヤメちゃんが選んだタクミ君がしてくれるのなら、私は嬉しいわ。
だからタクミ君、自分の強さを見つけて成長してちょうだい。アヤメちゃんを守れて、幸せに出来る力をね」
「……はい!」
何かあったら言ってちょうだい、と夫人の言葉を頂いて、部屋を退出した。
俺は外国生まれだから別れてちょうだい、とか言われんじゃないかって思ってはいたけれど、まさかああ言って下さるとは思ってなかった。てか、夫人の衝撃的事実を目の当たりにしてしまったけど、俺が聞いていいものだったのだろうか。
でも夫人があんな人だったのかと吃驚もしてる。
俺の強さ、か。
俺の強さとは何だろうか。俺に出来る事、料理か。ついさっき俺らの作る料理食うと幸せな気持ちになる、なぁんて言ってたな。夫人の言ってたそれとは違うと思うけど、自分の料理でアヤメを幸せにする自信はある。
異世界人のアヤメを守る為には、どうしたらいいのか。
まぁ、それはゆっくり考えよう。そろそろ夕飯の準備始めないと。食いしん坊な誰かさんが美味しいご飯をご所望だしな。