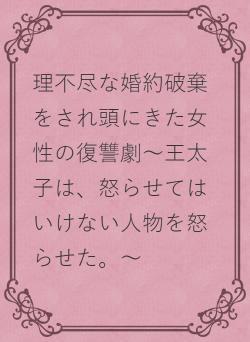ナカムラ家に生まれた俺達は、小さい頃から厨房に立っていた。
卵の割り方とか、そういうのから覚えていって。と言っても、じいさんの料理を作る姿が不思議で後ろから覗いてた、の方が正解か。
じいさんは当たり前だが、父さんも料理上手。この二人を屋敷内で探すなら取り敢えず厨房を見ろって言われてた。
でも、ばあさんも叔父さんも料理は苦手だった。ばあさんに関しては絶対に厨房に立たせるなと言われるくらいだった。じいさんが言うには、消し炭にする、だそうだ。
長男であるマサオミ兄さんは、料理を作る事は得意だけれどあまり好きじゃなかった。それよりも、食材の方に興味があった。だから俺がじいさんから沢山教わった。
2つ下のナナミも、生まれて大きくなってから一緒になって教えてもらってた。というより、誰も遊んでくれないから、って感じだったか。
俺らが大きくなってから、父さんは結婚話だとかお見合い話だとか言い出してきた。ここは男爵領、例え名声があったとしても爵位は下級貴族だからそれを思っての事だったんだと思う。
でも、それが嫌だった俺は違う国に行きたいと言い出した。
カーネリアン王国は、ちょっと遠いけれど食文化が全然進んでないと聞いたから、ウチの商会長である叔父さんが今度取引をしたいと考えていたらしくて。なら、いっその事店を出したらいいじゃんと俺が自分で言い出した。俺がやるって。
じいさんは好きにしろって言ってくれたけれど、父さんはだいぶ渋ってた。でも母さんは、何も言わなかった。じいさんと同じ考えだったんだと思う。
「タクミはもう19なんだ、若いもんはもっと冒険した方がいいだろ」
結局は、そんなじいさんの一言で俺はカーネリアン王国に行く事を許された。ついでに、お兄ちゃんが行くなら私も行く、とナナミも付いて来たけど。
でも、現実はそんなに甘くない。やっとの思いで店を出したけれど、客足は全然伸びなかった。他国の食文化なんだから、そうなるのは分かってた。けど、それでも全然伸びなくて。これじゃじいさん達に笑われる、と焦りすら出てたと思う。
けど、そんな時彼女が現れた。
「は、はじめまして。アヤメ・アドマンスです。あ、以前の名前は、〝奥村菖〟です」
俺らと同じような容姿の女性だったから、とても不思議だった。
俺んちの家族の中で、黒髪黒目はじいさんと俺しかいなかったから、とても新鮮だった。と言ってもじいさんはすぐ真っ白になったけど。それに、女性って所もあったからだと思う。
しかも、ウチのじいさんと一緒の日本人。じいさんと同じ故郷で生まれた異世界人だった。
だからつい、他に食いたいもんはないかって聞いてしまった。そしたら、茶漬けって言われて。え、そんなんでいいの? って聞き返しそうになった。まぁ、食いたいんならいいけど。
でも、すんごく美味そうに食べていた。ずっと和食が食べたかったって事か? それとも、単に俺らが作るご飯が気に入ったって事? ま、どっちでもいいけど美味しく食べてくれるならいいや。
久々に、美味しく食べてくれる人がいて本当に嬉しかった。
また来てくれるかな、と思いつつお土産を用意してた。下心とかじゃない。ただあの食べっぷりがまた見たくなっただけ。
と、思っていたら。
「その、私、機械? 以外で炊いたこと、なくて……」
え? 米、炊いた事ないのか? じいさん、日本人なら誰だって炊けるって言ってたけど。でも、じいさんとこの人は生きていた時代が違うから、そのせいか。
でも、そのお陰なのか、彼女の母親がこう言った。
「じゃあ、作っちゃったらどう?」
「え?」
「炊飯器、魔道具で作ったらいいじゃない。ほら、今レスリート郷にお願いしてるでしょ? 一緒に作ってもらいましょうよ」
魔道具、なんてこっちじゃあんま作られていない。
それは、国内に魔石の採掘場所が殆どないからだ。例え魔道具が作れたとしても、魔石がなければ動かせない。他国から輸入となると、魔石の場合関税が他より倍以上高くなる。だからスフェーン王国では魔術師はいても魔道具技術は発展しなかった。
それに代わってこの国、カーネリアン王国じゃ、魔道具技術はこの大陸一だと聞いた。こんな簡単に言うなんて本当に出来るのかと一瞬疑ったけど、この国でなら本当に出来るんじゃないかって思ってしまった。
もしそれが完成したら、きっとスフェーン王国の料理がこの国に広がる第一歩になるんじゃないかって思った。
そんな事があって、炊飯器? の製作と一緒に、この国のアドマンス公爵家の支援も受けることが出来た。しかも、彼女達が店に訪れた事によって客足も増えた。あの人が来てくれたお陰で、こんなに凄い事が起きてしまったという事だ。
感謝より前に、驚いてしまった。
「ほんっと、美味そうに食べるよな」
「ほんとね~、良い食べっぷりよね」
こっちに来てまだ全然経ってないのに、自分のブランドを立ち上げたって聞いた。ほんと、凄いやつだ。異世界人だから? いや、違う気がする。
確かに、俺らにはない知識をアヤメは持っている。でも、それをこっちで実現させるのは大変な事だ。アヤメ自身の力なんだと思う。
「あ、そういえばわさび聞かなかった」
ナナミが海鮮丼に最後に乗せる直前で気がついた。店内の方に頭を出していて。ほらやっぱり、さび抜きだ。この前からしを避けてたの見てたし。
「辛いの苦手だなんてアヤメちゃん可愛いな~。ね?」
「俺に振るな」
ったく、煩いな。さっさと洗い物終わらせろ。
「お兄ちゃん、良かったね」
「何が?」
「だって、食べてもらいたかったんでしょ? 海鮮丼」
「……まぁ、この国じゃ生の魚食わないみたいだから、アヤメは食べてなかったって事だろ? それに、折角新鮮な魚持ってきてくれたってのに俺らの賄いだけじゃ勿体ないだろ」
「ほんとに~?」
「他に何があるんだよ」
「さ~ね~?」
あれから、アヤメの発案で完成した炊飯器は、商会では結構人気が出てるらしい。そのお陰でこっちの特産品である米もどんどん売れ行きが伸びてる。母国でも欲しい人が何人もいるらしい。
まぁ、自分の代わりに勝手に炊いてくれるんだ。放っておいててもいいんだし、しかもタイマー付きで設定した時間に炊き上がるようになってる。そんな優れものなんて、皆欲しいに決まってるよな。
ほんと、アヤメには感謝しかないな。
でも、感謝だけじゃない事は俺もちゃんと気づいてる。彼女に違った感情を抱いている事は自分がよく分かってる。気付いてるけれど、言うつもりはない。ただ、彼女には俺の作った飯を美味そうに食ってくれればそれでいい。
「あ、そういえば従業員の件。リカルドとナオが来るって。まだ先になりそうだっては言ってたけど」
「……」
「……」
「……ナオかぁぁぁぁ……」
まぁ、今忙しすぎて従業員が足りないからお願いしたのはこっちだけどさ。ナオかぁ……
絶対何か起きるに決まってる。……何とかなる、か?
卵の割り方とか、そういうのから覚えていって。と言っても、じいさんの料理を作る姿が不思議で後ろから覗いてた、の方が正解か。
じいさんは当たり前だが、父さんも料理上手。この二人を屋敷内で探すなら取り敢えず厨房を見ろって言われてた。
でも、ばあさんも叔父さんも料理は苦手だった。ばあさんに関しては絶対に厨房に立たせるなと言われるくらいだった。じいさんが言うには、消し炭にする、だそうだ。
長男であるマサオミ兄さんは、料理を作る事は得意だけれどあまり好きじゃなかった。それよりも、食材の方に興味があった。だから俺がじいさんから沢山教わった。
2つ下のナナミも、生まれて大きくなってから一緒になって教えてもらってた。というより、誰も遊んでくれないから、って感じだったか。
俺らが大きくなってから、父さんは結婚話だとかお見合い話だとか言い出してきた。ここは男爵領、例え名声があったとしても爵位は下級貴族だからそれを思っての事だったんだと思う。
でも、それが嫌だった俺は違う国に行きたいと言い出した。
カーネリアン王国は、ちょっと遠いけれど食文化が全然進んでないと聞いたから、ウチの商会長である叔父さんが今度取引をしたいと考えていたらしくて。なら、いっその事店を出したらいいじゃんと俺が自分で言い出した。俺がやるって。
じいさんは好きにしろって言ってくれたけれど、父さんはだいぶ渋ってた。でも母さんは、何も言わなかった。じいさんと同じ考えだったんだと思う。
「タクミはもう19なんだ、若いもんはもっと冒険した方がいいだろ」
結局は、そんなじいさんの一言で俺はカーネリアン王国に行く事を許された。ついでに、お兄ちゃんが行くなら私も行く、とナナミも付いて来たけど。
でも、現実はそんなに甘くない。やっとの思いで店を出したけれど、客足は全然伸びなかった。他国の食文化なんだから、そうなるのは分かってた。けど、それでも全然伸びなくて。これじゃじいさん達に笑われる、と焦りすら出てたと思う。
けど、そんな時彼女が現れた。
「は、はじめまして。アヤメ・アドマンスです。あ、以前の名前は、〝奥村菖〟です」
俺らと同じような容姿の女性だったから、とても不思議だった。
俺んちの家族の中で、黒髪黒目はじいさんと俺しかいなかったから、とても新鮮だった。と言ってもじいさんはすぐ真っ白になったけど。それに、女性って所もあったからだと思う。
しかも、ウチのじいさんと一緒の日本人。じいさんと同じ故郷で生まれた異世界人だった。
だからつい、他に食いたいもんはないかって聞いてしまった。そしたら、茶漬けって言われて。え、そんなんでいいの? って聞き返しそうになった。まぁ、食いたいんならいいけど。
でも、すんごく美味そうに食べていた。ずっと和食が食べたかったって事か? それとも、単に俺らが作るご飯が気に入ったって事? ま、どっちでもいいけど美味しく食べてくれるならいいや。
久々に、美味しく食べてくれる人がいて本当に嬉しかった。
また来てくれるかな、と思いつつお土産を用意してた。下心とかじゃない。ただあの食べっぷりがまた見たくなっただけ。
と、思っていたら。
「その、私、機械? 以外で炊いたこと、なくて……」
え? 米、炊いた事ないのか? じいさん、日本人なら誰だって炊けるって言ってたけど。でも、じいさんとこの人は生きていた時代が違うから、そのせいか。
でも、そのお陰なのか、彼女の母親がこう言った。
「じゃあ、作っちゃったらどう?」
「え?」
「炊飯器、魔道具で作ったらいいじゃない。ほら、今レスリート郷にお願いしてるでしょ? 一緒に作ってもらいましょうよ」
魔道具、なんてこっちじゃあんま作られていない。
それは、国内に魔石の採掘場所が殆どないからだ。例え魔道具が作れたとしても、魔石がなければ動かせない。他国から輸入となると、魔石の場合関税が他より倍以上高くなる。だからスフェーン王国では魔術師はいても魔道具技術は発展しなかった。
それに代わってこの国、カーネリアン王国じゃ、魔道具技術はこの大陸一だと聞いた。こんな簡単に言うなんて本当に出来るのかと一瞬疑ったけど、この国でなら本当に出来るんじゃないかって思ってしまった。
もしそれが完成したら、きっとスフェーン王国の料理がこの国に広がる第一歩になるんじゃないかって思った。
そんな事があって、炊飯器? の製作と一緒に、この国のアドマンス公爵家の支援も受けることが出来た。しかも、彼女達が店に訪れた事によって客足も増えた。あの人が来てくれたお陰で、こんなに凄い事が起きてしまったという事だ。
感謝より前に、驚いてしまった。
「ほんっと、美味そうに食べるよな」
「ほんとね~、良い食べっぷりよね」
こっちに来てまだ全然経ってないのに、自分のブランドを立ち上げたって聞いた。ほんと、凄いやつだ。異世界人だから? いや、違う気がする。
確かに、俺らにはない知識をアヤメは持っている。でも、それをこっちで実現させるのは大変な事だ。アヤメ自身の力なんだと思う。
「あ、そういえばわさび聞かなかった」
ナナミが海鮮丼に最後に乗せる直前で気がついた。店内の方に頭を出していて。ほらやっぱり、さび抜きだ。この前からしを避けてたの見てたし。
「辛いの苦手だなんてアヤメちゃん可愛いな~。ね?」
「俺に振るな」
ったく、煩いな。さっさと洗い物終わらせろ。
「お兄ちゃん、良かったね」
「何が?」
「だって、食べてもらいたかったんでしょ? 海鮮丼」
「……まぁ、この国じゃ生の魚食わないみたいだから、アヤメは食べてなかったって事だろ? それに、折角新鮮な魚持ってきてくれたってのに俺らの賄いだけじゃ勿体ないだろ」
「ほんとに~?」
「他に何があるんだよ」
「さ~ね~?」
あれから、アヤメの発案で完成した炊飯器は、商会では結構人気が出てるらしい。そのお陰でこっちの特産品である米もどんどん売れ行きが伸びてる。母国でも欲しい人が何人もいるらしい。
まぁ、自分の代わりに勝手に炊いてくれるんだ。放っておいててもいいんだし、しかもタイマー付きで設定した時間に炊き上がるようになってる。そんな優れものなんて、皆欲しいに決まってるよな。
ほんと、アヤメには感謝しかないな。
でも、感謝だけじゃない事は俺もちゃんと気づいてる。彼女に違った感情を抱いている事は自分がよく分かってる。気付いてるけれど、言うつもりはない。ただ、彼女には俺の作った飯を美味そうに食ってくれればそれでいい。
「あ、そういえば従業員の件。リカルドとナオが来るって。まだ先になりそうだっては言ってたけど」
「……」
「……」
「……ナオかぁぁぁぁ……」
まぁ、今忙しすぎて従業員が足りないからお願いしたのはこっちだけどさ。ナオかぁ……
絶対何か起きるに決まってる。……何とかなる、か?