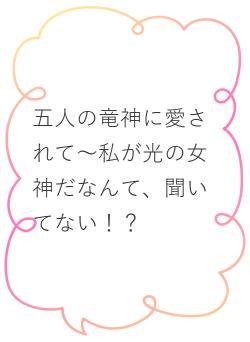「ん? なんだろ、ここ」
辺りをきょろきょろと見て、私は自分が立っている場所が遊園地であることに気がついた。
いつから私がここにいたのか、なんでこんな所にいるのかも分からない。
ガシャンッ、ガシャンッ。
私が首を傾げていると、私のすぐ隣にレールを走る小さなローラーコースターみたいなのが停止した。
すでに客が何人も乗っているみたいで、私が乗るまでそのローラーコースターは動こうとはしない。
「えっと、乗っていいのかな?」
私がそう言ってローラーコースターを見ると、ローラーコースターに乗っていた可愛らしいファンシーな小人がうんうんと頷いてくれた。
「あ、可愛い」
私は思わずそんな言葉を漏らしてから、楽しい気分になってローラーコースターに乗り込んだ。
なんで急に遊園地にいるのかは分からないけど、せっかくなら楽しまないとね。
私はシートベルトをしてから、他にどんな人が乗っているのか気になって振り向く。
あっ、クラスメイトの英治君だ。
なんでこんな所にいるんだろ?
「おーい、英治君―!」
私は手を振って呼び掛けてみたのだが、英治君は一切顔を上げようとはしなかった。
気づいていないのかな? ていうか、やけに暗い顔してない?
いつもの明るさが感じられないことを疑問に思っていると、ローラーコースターはゆっくりと走り出した。
……まぁ、ローラーコースターから下りてから話せばいいか。
そう思って、私は走り出したローラーコースターを楽しむことにした。
しかし、ゴトゴトッ揺れるローラーコースターはジェットコースターと呼ぶにしてはスピードも上がらないし、高い所から落ちたりもしなかった。
なんか凄い地味なローラーコースターだ。
『次は、風船~、風船~』
「風船?」
そんなことを考えていると、音質の悪い館内放送みたいなアナウンスが聞こえてきた。
風船って、一体どういう意味?
気になって辺りを見渡したとき、私は違和感に気がついた。
なんかみんな雰囲気暗すぎない?
遊園地の乗り物に乗っているというのに、みんな俯いたままで顔を上げようとはしない。
それどころか、項垂れて頭を抱えている人までいる。
「……どういうこと?」
私が不審に思って振り向くと、いつの間にか小人たちが立って英治君の席の近くに移動していた。
「ちょ、ちょっと、小人さん! 危ないよ!」
いくら速度が出てないと言っても、振り落とされてしまう。
そう考えた私は、小人たちに向かって大声でそう言った。
すると、小人たちは俯いていた顔を上げて私をちらっと見る。
「うわっ! ……え?」
私は小人たちの顔を見て、驚く声を上げてしまった。
小人の顔は初めに見たファンシーな顔とは対照的な、この世のものではないバケモノのような顔をしていたから。
ぎょろっとした目つきで睨まれた私は、慌てて顔を逸らす。
え、なに今の!? 怖過ぎでしょ!!
何かを見間違いしたのかと思ってちらっと視線を戻すと、そこでは目のぎょろっとした小人たちが英治君の口に太いストローみたいなのを無理矢理咥えさせていた。
すると、一人の小人が笑いながら咥えさせた方とは別のストロー口に口をつけると、勢いよく息を吹き込んだ。
それを見て爆笑している小人たちと変わったりしながら、ただ一方的に英治君に息を吹き込んでいく。
英治君の体はどんどんと膨らんでいって、着ていた服が弾けて、体がパンパンに膨らんでいった。
「え、だ、ダメ! 英治君が死んじゃうよ!」
私は大声でそう言ったが、私の声は小人の笑い声でかき消されてしまった。
助けようとしても、シートベルトのせいで上手く動くことができない。
そして、私の制止を無視するように息を吹き込まれ続けた英治君の体は限界を迎えたらしい。
パンっという音が聞こえた次の瞬間に、英治君の体は弾け飛んでそこからいなくなってしまった。
「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!」
私は衝撃的過ぎる光景を前にして、悲鳴を上げた。
「えっと、本田さん大丈夫?」
「え? あ、あれ?」
次の瞬間、私は学校の教室で立っていた。
荒くなった息をそのままに辺りを見渡してみると、クラスメイトたちが驚く目を私に向けていた。
「え、な、何が起きたの?」
さっきまで遊園地にいたのに、なんで今度は学校にいるんだろう?
私が取り乱していると、隣の席の恵美ちゃんが私の服をくいくいっと引く。
「奈々ちゃん。大丈夫? 怖い夢でも見た?」
「え、夢?」
「うん。奈々ちゃん、ずっと居眠りしてたと思ったら、急に立ち上がって叫び出したんだよ?」
「居眠り……」
恵美ちゃんにそう言われて、私は自分が授業中にウトウトしていたことを思い出した。
そういえば、授業がプールの後だったから眠くなっちゃったんだっけ?
「本田さん、怖い夢でも観ちゃったかな?」
授業をしている先生はそう言うと、クスっと小さく笑う。
そんな先生の言葉を聞いて、クラスで少し笑いが起きた。
その中には、夢に出てきた英治君も笑みを浮かべている。
私は少し恥ずかしがりながら、首筋に垂れていた冷や汗をぬぐった。
「んー、それはサル夢だね」
「サル夢?」
帰り道、私は恵美ちゃんと一緒に帰りながら今日見た夢のことを話していた。
私の話を聞き終えた恵美ちゃんは気まずそうに頬を掻いてから、言葉を続ける。
「有名な怖い話だよ。少し私が知っている内容とは違うけどね」
恵美ちゃんはそう言ってから、サル夢について教えてくれた。
ある人が夢の中で電車に乗ったとき、私と同じような状況に巻き込まれたらしい。
そして、館内放送のようなアナウンスで『次は活け造り~』と言われた後に、乗り合わせた乗客は小人に活け造りのようにされて、『えぐり出し~』と言われた後に、別の乗客が小人に目玉をえぐり出されたとのこと。
そして、最後に『次はひき肉~』とアナウンスされた後、夢を見た人はひき肉にされそうになったとか。
その夢を見た人は二回ともその夢を見たが、なんとか逃げ出したらしい。
しかし、夢から目覚めるときに『逃げるんですか? 次で最後ですよ』と言われたとのこと。
恵美ちゃんはそんなサル夢と私が今日見た夢が似ていると言っているのだ。
「なにそれ、怖すぎるんだけど」
私は恵美ちゃんの話しを聞いて、震えが止まらなくなってしまった。
似ている。というよりも、ほとんど同じだ。
「え、恵美ちゃん! 私どうすれば助かるのかな!?」
「あ、安心して奈々ちゃん。これって、ただのフィクションだから」
「で、でも、」
「多分、奈々ちゃんは知らないうちにどこかでこの話を聞いたんだと思うよ。それで、たまたま夢を見ちゃっただけだってば」
私が縋るような目を向けると、恵美ちゃんは私を安心させるように頭を撫でてくれた。
私は徐々に落ち着いてきて、震えが小さくなっていくのを感じた。
「そ、そうだよね。夢、なんだもんね」
「そうだよ。夢だからね。あっ、でも、うちの学校っていろんな噂があるから、気になるなら授業中に寝るのは控えた方がいいかもね」
恵美ちゃんに聞いて初めて知ったが、うちの学校は幽霊が出ることでちょっと有名な所らしい。
いよいよ、笑えなくなってきた。
恵美ちゃんは気にする必要はないと言っていたけど、今後は学校で練ることは控えよう。
私はそんな決意をして、恵美ちゃんと分かれて家に帰った。
その翌日、英治君は交通事故で亡くなった。
暴走する車に潰されて、死因は内臓破裂だったらしい。
「あ、あれ? ここって……」
ガタゴトと揺れるローラーコースターに乗せられて、私は不気味な音楽が流れる遊園地にいた。
このローラーコースター、見覚えがある。
あの日に見た衝撃的な夢を忘れるはずがない。
なんで? 学校では寝ないようにって、あれから気をつけてたのに!
ガチャガチャっとシートベルトを外そうとしても、どうやってもシートベルトはハズレない。
恐る恐る振り返ると、そこには目をぎょろっとさせた小人たちが私の一つ後ろの席まで来ていた。
「ひっ!」
そして、そこにいたのはまた見覚えのある顔だった。
「由紀! 由紀ちゃん! しっかりして!」
私のクラスメイトの由紀ちゃんが虚ろな目をして、顔を俯かせてローラーコースターに座っていた。
焦点が合っておらず、私に気づく気配もない。
このままだと由紀ちゃんが危ない!
そう思った私は何とかシートベルトを外して助けようとするけど、シートベルトはただ音を立てるだけで外れる気配がない。
どうしよう! このままだと英治君の二の舞になる!
何度も呼び掛けてみても声が届かなくて、私が焦っていると館内放送のようなアナウンスが聞こえてきた。
『次は、花火~、花火~』
「は、花火?」
花火ってどういうこと?
私が訳が分からずに困惑していると、いつのまにか小人たちが大量の花火を抱えていたことに気がついた。
そして、流れ作業のように色んな花火に火をつけると、それを無理やり由紀ちゃんの口に押し込んでいく。
「あ、危ないよ! 由紀ちゃん!」
パンパンッ!
しかし、私の声は由紀ちゃんには届かず、大きな花火が爆発する音がさく裂した。眩し光から逃れるように、私は慌てて手で目を覆う。
そして、その音と光が止んだ頃に目を開けると、そこにいたはずの由紀ちゃんの姿はなくなっていた。
代わりに力なくだらんと垂れていた黒焦げた物体を見て、私は悲鳴を漏らす。
「う、うわぁぁぁぁぁぁぁ!!」
「ほ、本田さん?」
「え? あ、あれ?」
次の瞬間、私は学校の教室で立っていた。
教壇では、先生が私を見て戸惑っているようだった。
「はぁっ、はっ……」
ちらっと隣にいる恵美ちゃんを見ると、恵美ちゃんは口元を手で覆っていた。
多分、私の状態から私がサル夢を見たことを察したのだろう。
恵美ちゃんは信じられないものを見る目で私を見つめていた。
「ゆ、由紀ちゃんは!?」
私が慌てて由紀ちゃんの方を見ると、由紀ちゃんは急に名前を呼ばれたことにただ驚いている様子だった。
「えっと、居眠りもほどほどにね」
そんな先生の言葉で、少しだけ教室に笑いが起きる。
私は強く既視感を覚える展開を前に、少しも笑うことができなかった。
「え、恵美ちゃん! 私どうしたらいいと思う?」
「ただの偶然かもしれないけど、それで片付けられる感じじゃないよね?」
私は学校からの帰り道、恵美ちゃんに今日見た夢のことを話していた。
サル夢の話通りなら、今度は夢の中で私の所に小人たちがやってくることになる。
そうなったら、私はどうなってしまうんだろう?
もしかしたらあるかもしれない未来を想像して、私は体を震わせていた。
そして、それよりも先に起こりえる可能性を前に私は恐怖を隠せないでいた。
「もしかしたら、由紀ちゃんも死んじゃうのかな……」
「それは考え過ぎだよ、奈々ちゃん」
「で、でも、教えてあげた方がいいんじゃないかな?」
「伝えたい気持ちはわかるけど、信じてもらうのは難しいんじゃないかな?」
私は恵美ちゃんの言葉に何も言い返せなかった。
サル夢で由紀ちゃんが殺されちゃうところを見たから気を付けて。
そんなふうに言われてもただ困惑するだけだと思う。
「……でも、もしも、次にサル夢を見ることがあったらさ、どうにかして逃げてね」
「どうにかしてって、どうやって?」
「分からない。でも、『これは夢だ!』って強く思えば夢から目覚めることができるって聞いたことあるよ」
私はいつになく真剣な目をしている恵美ちゃんの言葉に頷く。
それから大した会話をすることもなく、私たちは分かれて帰路につくことになったのだった。
翌日、由紀ちゃんの家は火事になった。
そして、由紀ちゃんは焼死体となって発見されたのだった。
「あ、あれ? ここって……うそ、」
気がつくと、私はまたあのローラーコースターに乗せられていた。
ローラーコースターが走っている中、無理やりシートベルトを外そうとするが、いつもと同じくシートベルトは外れる様子がない。
「まって、三回目ってことか……ひっ!」
私がびくびくしながら振り向くと、私のすぐ後ろに目がぎょろっとした小人たちがやってきていた。
小人たちは不気味な笑い声を上げながら、すぐに私の乗っている席まで来るとクツクツと笑い声を上げて私を見ていた。
「や、やめてっ! やめてよっ!!」
私は頭を抱えるようにしながら、笑い声を上げる小人たちが視界に入らないように努めた。
その変な笑い方をやめて! 私を見ないで!
「そ、そうだ! 夢! これは夢! 夢だからぁ!!」
私は恵美ちゃんに言われたことを思い出して、必死に夢から覚めるように、今が夢であることを自分に訴えかける。
「夢! これは夢! いたっ! やめて、蹴らないで!」
私が頭を抱えていると、小人たちは笑いながら私の頭を蹴ってきた。
脳に響くような蹴りを受けながら、私はぼうっとする頭の中で必死に夢から覚めることを願う。
『次は集団――、集団――』
いつものアナウンスが聞こえる中、私の意識は少しずつ薄れていった。
今、アナウンスは何て言ったんだろ?
そんな事を考えながら。
「本田。本田、しっかりしろ」
「え? あ、あれ?」
次の瞬間、私は教室で立っていた。
辺りを見渡すと、そこにいるのはいつものクラスメイトたちがいた。
……ということは、サル夢から逃れることができた?
私がバッと勢いよく恵美ちゃんを見ると、恵美ちゃんはきょとんとした様子で首を傾げていた。
あれ? なんか前と反応が違う。
そう思いながら教室を見渡して、私は言葉を失った。
なぜなら、そこにはいないはずの英治君と由紀ちゃんがいたからだ。
「え、な、なんで……」
私が固まってしまっていると、恵美ちゃんがくいくいっと私の服の裾を引っ張る。
「奈々ちゃん大丈夫? さっきまで寝てたのに、急に立ち上がるから驚いたよ」
「ね、寝てた?」
私はそんなサル夢の話を知らないような恵美ちゃんの反応を見て、力なくすとんと腰を下ろした。
「もしかして、今まで見てたの全部夢?」
そう思った瞬間、全身の力が抜けてしまい、私は椅子から転げ落ちてしまった。
「ちょ、ちょっと、奈々ちゃん大丈夫!?」
「う、うん、大丈夫! ちょっと気が動転して、転んじゃっただけだから」
よかった。本当に全部夢だったんだ。
そうだよね! サル夢なんてふざけた夢があるわけがない。
私は悪夢から解放された喜びで、ほどく興奮しているみたいだった。
だって、あんなに激しく転んだはずなのに痛さがまったくないのだから。
……あれ?