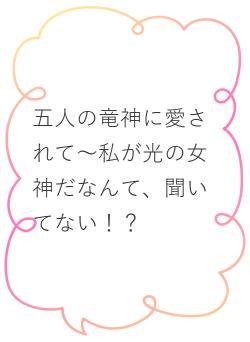私は調べ物をしているうちに、偶然学校の怪談というものを知った。
調べた記事によると、夜中になると学校の階段が増えるという怪談話があるらしい。
本来、12段のはずの階段が深夜になると13段になる。
そして、その階段の13段目の天井からは、首を吊るためのロープが垂らされているらしい。
その13段目を上ったが最後、冥界に連れていかれるとのこと。
……ふぅん、奇数階がいいんだ。
私はそんなことを考えながら、その記事をじっくりと読むのだった。
うん、そうだよね。
私がしっかりしないと。
「裕也、一緒に帰ろ!」
「紗季。ああ、一緒に帰ろうか」
私は帰りのホームルームが終わるなり、裕也の席に向かう。
裕也は私が席に来るのを待ってくれていたようで、優しく笑ってから私の隣を歩き出した。
裕也は私の彼氏だ。
転校してきた裕也に積極的にアプローチをして、数回お出かけをしてから告白をして、オーケーをもらった。
他のクラスにも裕也のことを好きな女の子がいるらしいけど、恋愛は早い者勝ちだ。
噂では、あと数歩遅かったら他の女の子が告白をしていたっぽい。
その告白をする予定だった子も可愛い子だったので、私よりも先に告白をされていたら遅かったかもしれない。
そして、今でも裕也のことを狙っている子たちがいる。
そんな子たちに、裕也を渡すわけにはいかない。他の子たちに取られない様に気を付けなくては。
私は他の子たちが裕也に話しかけるよりも早く裕也を教室から連れ出して、いつものように仲良く一緒に下校する。
すると、私たちを見た他のクラスの女の子があっと声を漏らす。
「裕也君。また紗季ちゃんと一緒にいるんだ」
「付き合ってるらしいよ、あの二人」
「え? そうなの? 裕也君、もっと可愛い子と付き合えばいいのに」
その言葉は陰口の気はなくmただ本気でそう考えているような言葉だと思った。
そんな言葉で弱いになっていてはきりがない。
私は聞き慣れたような悪口を聞き流して、聞こえないふりをして裕也の隣を歩く。
しかし、聞こえないふりをしていても、そんな声が多く聞こえてくれば不安にもなる。
「ねぇ、裕也は私とずっと一緒にいてくれるよね?」
「当たり前だろ。死ぬまで一緒だ」
私が確認するように言うと、裕也は照れくさそうな笑みと共に、私を安心させるように手を繋いでくれる。
死ぬまで、か。
私はその言葉に少しの不満を持ちながら、静かに頷くのだった。
……私がしっかりしないと、だめだよね。
「夜中に増える階段?」
私たちが付き合って数ヶ月が経ったある日。
私はいつも通り裕也と下校しながら、私は何気なくそんなことを聞いてみた。
「そう、学校の怪談話って知ってる?」
「あれ? 紗季って怖い話とか好きだったっけ?」
「うーん、最近少し興味があってね」
私が首を傾げて裕也にそう言うと、裕也はふーんと短く言葉を返した。
別に、私はとりわけ怖い話が好きなわけではない。
ただちょっと別のことを調べているときに、たまたま怪談話を見つけてしまっただけだ。
「怪談によると、夜中になると学校の階段の段数が増えるんだって。気にならない?」
「まぁ、気にならないことはないけど」
「じゃあさ、今日一緒に見に行かない? 学校に忍び込もうよ」
私が悪巧みをするように言うと、裕也は目をぱちくりとさせる。
「今日? いやいや、夜中に学校なんて入れないだろ?」
裕也はそう言いながも、少しだけ前のめりになっているよう見えた。
うん、いついになく気になってるみたい。
私はそんな裕也の反応を見てクスリと笑う。
「ううん、入れるよ。今日のために一階の教室の窓を一個だけ開けておいたの。だから、そこから入れる」
「おお、すでに準備はできてるのか」
「うん。それで、どうかな? 裕也ってこういう話好きでしょ?」
「あれ? 紗季に話したことあったっけ? 俺が幽霊とか好きなのって」
「うん、知ってるよ。だって、私は裕也の彼女だもの」
裕也は不思議そうな顔をしたあと、少しだけ考えこむ。
「今日の夜かぁ。楽しそうではあるんだけどなぁ」
「絶対に楽しいよ。それに……裕也と別の学校に通うよりも前に、あの学校で思いで作りたいなぁ」
私がしんみりと言うと、裕也は気まずそうに頭を掻く。
もうすぐ私たちは学校を卒業してしまう。
その進学のタイミングで、裕也は私とは違う学校に通うことになっていた。
「いや、別の学校っていってもそんなに遠くないぞ? これからだって今まで通り会えるって」
「うん、ありがとう。でもさ、せっかくなら卒業するんだし、少しくらい悪いことしてもいいんじゃない?」
夜の学校に忍び込むなんて褒められたことではない。
バレれば怒られるだろうけど、もうすぐ私たちは卒業をする身だ。
それなら、それはそれで思い出になるのではないだろうか?
私がそう言うと、裕也はやれやれ顔をしながら笑みを浮かべる。
「そうかもな。せっかく、紗季が準備もしてくれるんだし、行ってみてもいいか」
私は裕也のそんな言葉に喜んで笑みを浮かべる。
やった。
気が早すぎるかもしれないが、私は裕也の返事を聞いてから鼓動の音を少しだけ速めて、夜を待ち遠しく思うのだった。
それから、私たちは深夜に学校に集まる約束をして、一度各々の家に帰宅した。
「ねえ、裕也君かっこよくない?」
「ねぇー。紗季ちゃんにはもったいないよねー」
「もう卒業しちゃうんだし、最後に告白くらいしてもいいよね?」
「どうしよう! もしかしたら、乗り換えてくれるかもしれないよ!」
私がいつも一緒にいるグループの女の子たちが、私がトイレに行っているうちにそんなことを話しているのを聞いてしまった。
友達の彼氏に告白をするなんておかしい。
そう言ってやりたかったが、私は冷静に彼女たちの会話に耳を傾けることにした。
どうやら、彼女たちは各々で情報を仕入れて、それを共有しているらしかった。
彼女たちが独自で手に入れた情報を聞きながら、私は彼女たちに気づかれないように冷めた目を彼女たちに向ける。
……へぇ、裕也って心霊とか怪談とか好きなんだ。
そんな情報だけを手に入れて、私はその場をそっと離れた。
多分、裕也が違う学校に行くようになったら、彼女たちみたいに裕也に手を出す女の子も多くなるのだろう。
私がそんなことを考えて暗い顔をすると、裕也は私の様子がいつもと違うことに気づいてくれた。
私はそんな裕也の気遣いに喜びながら、何度目かになるし確認をする。
「ねぇ、裕也は私とずっと一緒にいてくれるよね?」
「当たり前だろ。死ぬまで一緒だ」
裕也はそう言うと、優しい笑みを向けながらそっと私の手を握ってくれた。
……死ぬまで、か。
私はきゅっと口を閉じて、不満な気持ちを呑み込んだ。
私がしっかりしないとダメだよね。
そんなことを考えながら。
「案外簡単に入れたな」
「ね、私もびっくりだよ」
深夜に家を抜け出して校門前に集まった私たちは、柵に空いている穴を通って学校の敷地に入った。
そして、鍵を開けておいた教室の窓から校舎に侵入して、私たちは一階の階段までやってきた。
廊下は薄暗くて少しの怖さがあったが、隣にいる裕也が手を握ってくれたので怖さは和らいだ。
私は昼間に手を繋ぐよりも体を寄せて、裕也の腕に抱きつく。
「これが、深夜になると階数が増える階段?」
「うーん、どうだろ? 何階の階段が増えるのかまでは分からないんだ。順番に一階から数えていこうよ」
「そうだな。時間はあるわけだし」
裕也は懐中電灯で目の前にある階段を照らすと、小声で階段の数を数え始めた。
私は慌てるように数を数えている裕也の指をそっと下ろさせる。
「ちょっと、裕也。それだとつまらないでしょ」
「え? つまらない?」
「せっかくなんだから、数えながら階段を上っていこうよ。そうだなぁ……うん、片方は目を閉じて、もう片方の手を引いて階段を上っていくっていうのはどうかな?」
一階は私が裕也の手を引いて、目をつむった裕也の手を引いて階段を上る。
二階は逆に裕也に手を引いてもらって、私は目を閉じて階段を上る。そして、三階はまた私が目を閉じた裕也の手を引く。
目をつぶっている方が階段が増えているかもとドキドキできるし、きっとそっちの方が楽しい。
私がそう説明をすると、裕也は確かにそうだなと言って笑って私の提案を受け入れてくれた。
そして、私は目を閉じた裕也の手を引いて、階段を歩き出す。
「「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11……12!」」
一緒に怪談の数を数えながら12段の階段を上り終えてから、裕也はパチッと目を開けてにこりと笑う。
「うん、確かに見えない方がスリルがあるな」
「でしょ? 本当に増えてると思った?」
「ああ、少しだけね。これは結構怖いかもしれないぞ?」
「本当? じゃあ、今度は私の番ね」
私はそう言うと、目をつむって裕也に手を引いて階段を上り始めた。そして、さっきと同じように階段を上りながら一緒に数を数え始める。
「「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11……12!」」
私がふぅっと息を吐いてから裕也を見ると、裕也はからかうような笑みを浮かべている。
「紗季、実は結構怖がり?」
「そうかもしれない。今すごいドキドキしてるし」
私は自分の胸に手を置いて心臓の音を聞きながら、口元を緩める。
……ただ怖いだけじゃないかもしれないけどね。
そんな事を考えながら、私は裕也を見つめる。
「じゃあ、今度は裕也の番ね」
私は焦る気持ちを抑えながら、目をつむった裕也を三階へと続く階段に連れていった。
「わぁ……」
「ん? どうかしたのか、紗季」
三階の階段を懐中電灯で照らした私は、思わずそんな声を漏らしてしまった。
「ううん、何でもない!」
私は漏れてしまった感動する声を慌て誤魔化して、裕也の手を引いて階段を上っていく。
「「1、2、3、4、5、6、7、8、9……」」
「あ、待って裕也」
私は9まで数えたところでピタッと足を止めた。
私が足を止めると、裕也が驚いてびくんっと体を跳ねさせる。
「え、な、なんだよ、紗季。なんで急に止まったんだ?」
「ふふっ、裕也驚きすぎだよ」
私は目をつむっている裕也を見ながら、抑えることのできなかった笑い声を漏らす。
「そりゃ、驚くだろ。そ、それで、なんでこんな所で止まったんだ?」
「うん。あのね、この階段を調べ終えたら、今度は旧校舎の方の階段も増えてるか確かめに行きたいんだけど、いいかな?」
「別にいいけど、なんでこのタイミングで? あ、もしかして、紗季はもう答えを知ってるからつまらなくなったんだろ?」
「ふふっ。うん、そうだね。一足先に答えは知っちゃったからね。だから、この後は旧校舎の方も見てみようよ」
私がそう言うと、裕也は胸をなでおろしてこわばった表情を緩めて頷く。
私はそんな裕也を横目に見ながら、また裕也の手を引いて階段を上りだす。
「じゃあ、続きね。9、10、」
私が急に続きから数を数え始めると、裕也も少し慌てた様子で私と一緒に数を数え始める。
「「11、12!!」」
そして、私は階段を上り終えて安心している裕也を見て、ひと際深い笑みを浮かべる。
「裕也」
「ん? どうした、紗季」
「これで、ずっと一緒だね」
私はそう言って、そっと裕也の腕に自らの腕を絡めるのだった。
……死ぬまで一緒じゃ、やだよ。
そんなことを考えながら。