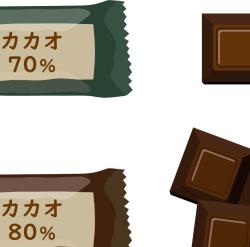「奈央・・・私の子・・・奈央・・・ごめんね・・・淋しい想いをさせて・・・ごめんなさい・・・」
その頬は涙で濡れ、そして美里は泣き崩れた。
「奈央は・・・どこにいるの?」
「奈央君は連城家の屋敷で、美里さんを待っていますよ。」
「奈央・・・会いたい・・・ずっと会いたかった・・・」
「美里・・・お前は・・・美里なんだな?」
湊が美里の身体を支えると、美里は湊に縋った。
「湊・・・私、奈央に会ってもいいの?私みたいな母親でも・・・。子供より小説を書くことに夢中になってしまった私をあの子は許してくれるの?」
渚は美里の肩に手を置き、優しく微笑んだ。
「美里さん・・・奈央君は小説家のあなたを誇らしいと言ったんです。あなたはそのままで、奈央君のママになっていいんです。」
「奈央・・・・・・。」
美里はしばらくその名を呼びつづけ、時間の経過とともに、ゆっくりと落ち着きを取り戻していった。
そして今気づいたというように顔を上げ、渚を見た。
「あなたが・・・渚さんね?」
「はい。」
美里に自分が認識されていることに、渚は驚いた。
「渚さん、・・・湊・・・ありがとう・・・」
そうふたりに礼を言って微笑む美里は、ひとりの母親の顔に戻っていた。
その頬は涙で濡れ、そして美里は泣き崩れた。
「奈央は・・・どこにいるの?」
「奈央君は連城家の屋敷で、美里さんを待っていますよ。」
「奈央・・・会いたい・・・ずっと会いたかった・・・」
「美里・・・お前は・・・美里なんだな?」
湊が美里の身体を支えると、美里は湊に縋った。
「湊・・・私、奈央に会ってもいいの?私みたいな母親でも・・・。子供より小説を書くことに夢中になってしまった私をあの子は許してくれるの?」
渚は美里の肩に手を置き、優しく微笑んだ。
「美里さん・・・奈央君は小説家のあなたを誇らしいと言ったんです。あなたはそのままで、奈央君のママになっていいんです。」
「奈央・・・・・・。」
美里はしばらくその名を呼びつづけ、時間の経過とともに、ゆっくりと落ち着きを取り戻していった。
そして今気づいたというように顔を上げ、渚を見た。
「あなたが・・・渚さんね?」
「はい。」
美里に自分が認識されていることに、渚は驚いた。
「渚さん、・・・湊・・・ありがとう・・・」
そうふたりに礼を言って微笑む美里は、ひとりの母親の顔に戻っていた。