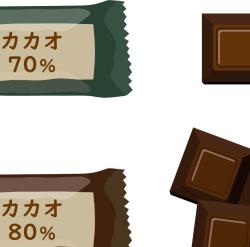「この『紫陽花と少年』を書いた木之内惣という作家さんはね・・・奈央君のお母さん・・・連城美里さんなの。」
奈央は思いがけない渚の言葉に目を丸くした。
「・・・お母さんが・・・これを書いたの?」
「そう。奈央君のお母さんはすごい人。素敵なお話を沢山書いてるの。」
「でも湊や絹さんは、お母さんは病気で遠いところにいるって言ってたよ?」
「うん・・・。今は遠くにいる。でもきっと奈央君に会いたいって強く願ってる。だから・・・お母さんにお手紙を書いてみない?『紫陽花と少年』を読んだ感想でもいい。奈央君の嬉しかったことでもいい。なんでもいいからお母さんに今の奈央君を伝えてみたらどうかな?」
「いまどき手紙?メールとかじゃなくて?」
「メールもいいけど・・・もっといい方法があるの。奈央君、声の手紙を届けようよ。ボイスレコーダーに奈央君の声を入れるの。お母さん、奈央君の声が聴けたら、きっと喜ぶと思うんだ。ね、どうかな?」
「そんなの恥ずかしいよ。」
そう口を尖らす奈央の手に、渚は無理矢理ボイスレコーダーを握らせた。
「誰かに聴かれると恥ずかしいよね。だからこれ貸してあげる。奈央君のタイミングでお母さんへメッセージを入れて欲しいんだ。短くても、ほんの一言でもいいから。ね、お願い!」
奈央はそのボイスレコーダーをじっとみつめ、それから渚を見て困ったような笑みを浮かべた。
「まったく・・・渚は強引だなあ。まあ、気が向いたら入れとくよ。」
「ほんと?奈央君、ありがとう!」
そう喜ぶ渚の声を部屋の外で、ドアにもたれかかり腕を組みながら耳を傾けていた湊も、「よし!」と小さくつぶやいた。