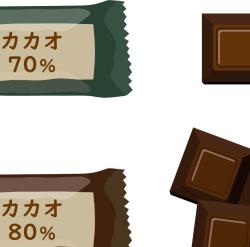奈央と渚、そして絹はそれぞれテーブル席に付き、手を合わせ「頂きます!」と唱和した。
絹の作った料理はどれも、店に出してもおかしくないくらい美味しかった。
「さあさ。沢山食べてくださいな。お代わりもたっぷりありますからね。」
「はい!」
渚は黙々とビーフシチューを口に入れる、目の前に座る奈央を見た。
「奈央君。口元にビーフシチューの汁が付いているわよ?」
「え?どこどこ?」
「ここよ。」
渚は自分の右の口元を指さした。
「奈央坊ちゃま。手ではなく、ちゃんとナプキンで汚れをお拭きなさいませ。」
「はあい。」
奈央は絹から手渡されたナプキンで口元を拭った。
「それにしても食卓に渚様のような若くて可愛らしい女の子がいると、ぱあっと花が咲いたように明るくなりますわね。」
「絹さん。私、もうアラサーよ?女の子って歳じゃないわ。」
「あら渚様。これからは人生100年時代ですわよ?アラサーなんてまだひよっこですわ。もちろんワタクシだってまだまだ現役で頑張りますわよ?」
そう言って豪快に笑う絹こそひまわりのような女性だと渚は思った。
絹・・・吉川絹はこの家に仕えてもう半世紀近く経つという。
奈央の祖父の代からだというから、絹にとって湊は息子、奈央は孫のような存在なのだろう。
若い頃に一度は結婚したそうだがすぐに離縁し、再びこの家のハウスキーパーとして戻って来たのだそうだ。
庭に咲いている四季折々の花や美しい白い薔薇も、絹の手入れによるものだ。
食事が終わり、絹が冷蔵庫から湊特製のスイーツを運んできた。
今日はバナナパウンドケーキだ。
「わあ。美味しそう!」
「この生クリームをかけるよう、湊坊ちゃまから仰せつかっておりますの。」
絹はこんがり焼けたパウンドケーキの上にクリームを乗せていった。
絹の作った料理はどれも、店に出してもおかしくないくらい美味しかった。
「さあさ。沢山食べてくださいな。お代わりもたっぷりありますからね。」
「はい!」
渚は黙々とビーフシチューを口に入れる、目の前に座る奈央を見た。
「奈央君。口元にビーフシチューの汁が付いているわよ?」
「え?どこどこ?」
「ここよ。」
渚は自分の右の口元を指さした。
「奈央坊ちゃま。手ではなく、ちゃんとナプキンで汚れをお拭きなさいませ。」
「はあい。」
奈央は絹から手渡されたナプキンで口元を拭った。
「それにしても食卓に渚様のような若くて可愛らしい女の子がいると、ぱあっと花が咲いたように明るくなりますわね。」
「絹さん。私、もうアラサーよ?女の子って歳じゃないわ。」
「あら渚様。これからは人生100年時代ですわよ?アラサーなんてまだひよっこですわ。もちろんワタクシだってまだまだ現役で頑張りますわよ?」
そう言って豪快に笑う絹こそひまわりのような女性だと渚は思った。
絹・・・吉川絹はこの家に仕えてもう半世紀近く経つという。
奈央の祖父の代からだというから、絹にとって湊は息子、奈央は孫のような存在なのだろう。
若い頃に一度は結婚したそうだがすぐに離縁し、再びこの家のハウスキーパーとして戻って来たのだそうだ。
庭に咲いている四季折々の花や美しい白い薔薇も、絹の手入れによるものだ。
食事が終わり、絹が冷蔵庫から湊特製のスイーツを運んできた。
今日はバナナパウンドケーキだ。
「わあ。美味しそう!」
「この生クリームをかけるよう、湊坊ちゃまから仰せつかっておりますの。」
絹はこんがり焼けたパウンドケーキの上にクリームを乗せていった。