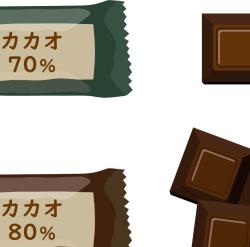「うん。前回勉強したところ、しっかり覚えているね。偉い偉い。」
渚に頭を撫でられた奈央は、誇らしげに微笑んだ。
「じゃ、今日はここまでにしようか?」
「うん。ねえ渚、今日も夕食食べていくでしょ?」
家庭教師の勉強時間が夕食前だということもあり、前回渚はスイーツはもちろん、夕食までご馳走になってしまっていた。
「んーでも、毎回は申し訳ないかな。」
「いいんだよ。僕と絹さんだけじゃ淋しいもん。どうせ湊は遅く帰ってくるしさ。この前だって絹さんも喜んでたんだよ?渚が一緒に夕食を食べてくれてさ。」
奈央は教科書やノートをランドセルに仕舞うと、部屋のドアを開けて渚をリビングへ誘った。
その言葉に釣られ、渚も奈央の後ろをそろりと付いていく。
キッチンで大きなお尻を振りながら、鼻歌を歌う絹の後ろ姿に奈央は声をかけた。
「ねえ絹さん。今日も渚と一緒にご飯食べてもいい?」
シチュー鍋の中身をお玉でかき回していた絹はくるりと振り向き、ニカッと笑顔を作った。
「もちろんですとも!そうかと思って多めに作りましたのよ?今日は奈央坊ちゃまの大好物のビーフシチューですの。渚様にも是非ご賞味頂きとうございます。」
「絹さん。渚様はよして。私はただの雇われ家庭教師なんだから。」
「いいえ!渚様は奈央坊ちゃまと湊坊ちゃまの大切な客人です。だから渚様と呼ばせてくださいませね。」
絹は奈央のことを「奈央坊ちゃま」湊のことを「湊坊ちゃま」と呼んでいた。
あの偉そうな男が「湊坊ちゃま」と呼ばれているところをこの目で見てみたいものだ、と渚は可笑しくなった。
「・・・そうお?じゃ、せめてなにか手伝わせて?」
「滅相もない!・・・と言いたいところでございますけど、ちょうどガーリックトーストが焼き上がったところですの。それをカウンターの上にあるお皿に取り分けて頂いてもよろしいかしら?」
「はい!」
渚がオーブンレンジの扉を開けると、ガーリックと香ばしいパンの香りがキッチンに広がった。
渚はトングでガーリックトーストをチューリップの模様があしらわれたパン皿に取り分け、テーブルに並べた。
絹はビーフシチューや茹でたアスパラガスのサラダやらを手早くテーブルにセッティングし、あっという間に夕食の用意が整った。
渚に頭を撫でられた奈央は、誇らしげに微笑んだ。
「じゃ、今日はここまでにしようか?」
「うん。ねえ渚、今日も夕食食べていくでしょ?」
家庭教師の勉強時間が夕食前だということもあり、前回渚はスイーツはもちろん、夕食までご馳走になってしまっていた。
「んーでも、毎回は申し訳ないかな。」
「いいんだよ。僕と絹さんだけじゃ淋しいもん。どうせ湊は遅く帰ってくるしさ。この前だって絹さんも喜んでたんだよ?渚が一緒に夕食を食べてくれてさ。」
奈央は教科書やノートをランドセルに仕舞うと、部屋のドアを開けて渚をリビングへ誘った。
その言葉に釣られ、渚も奈央の後ろをそろりと付いていく。
キッチンで大きなお尻を振りながら、鼻歌を歌う絹の後ろ姿に奈央は声をかけた。
「ねえ絹さん。今日も渚と一緒にご飯食べてもいい?」
シチュー鍋の中身をお玉でかき回していた絹はくるりと振り向き、ニカッと笑顔を作った。
「もちろんですとも!そうかと思って多めに作りましたのよ?今日は奈央坊ちゃまの大好物のビーフシチューですの。渚様にも是非ご賞味頂きとうございます。」
「絹さん。渚様はよして。私はただの雇われ家庭教師なんだから。」
「いいえ!渚様は奈央坊ちゃまと湊坊ちゃまの大切な客人です。だから渚様と呼ばせてくださいませね。」
絹は奈央のことを「奈央坊ちゃま」湊のことを「湊坊ちゃま」と呼んでいた。
あの偉そうな男が「湊坊ちゃま」と呼ばれているところをこの目で見てみたいものだ、と渚は可笑しくなった。
「・・・そうお?じゃ、せめてなにか手伝わせて?」
「滅相もない!・・・と言いたいところでございますけど、ちょうどガーリックトーストが焼き上がったところですの。それをカウンターの上にあるお皿に取り分けて頂いてもよろしいかしら?」
「はい!」
渚がオーブンレンジの扉を開けると、ガーリックと香ばしいパンの香りがキッチンに広がった。
渚はトングでガーリックトーストをチューリップの模様があしらわれたパン皿に取り分け、テーブルに並べた。
絹はビーフシチューや茹でたアスパラガスのサラダやらを手早くテーブルにセッティングし、あっという間に夕食の用意が整った。