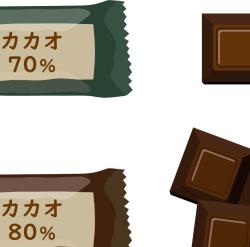すると湊は伏せた目を上げて意味ありげに渚をじっとみつめ、渚はその眼光の強さにたじろいだ。
「な、なに?」
「そこで・・・だ。本題はここからなんだが。」
まだ本題に入ってなかったの?!
「お前に奈央の家庭教師を頼みたい。」
「・・・は?!」
「奈央はお前のことをあれからずっと気にしている。渚ともう一度会いたい、遊びたいと俺に訴えてくる。」
「・・・・・・。」
「俺も奈央のそばにお前のような人間がいてくれたら何かと安心だし・・・正直な話、お前を家に連れていけば奈央は俺のことを少しは見直すかもしれない。」
「あきれた!自分の好感度を上げるために私を利用するってわけ?」
「金なら弾む。ちょっとした小遣い稼ぎにもなるだろうし、お前にとっても悪くない話だと思うが。」
「見損なわないでよ。お金の為だけに動くほど、私暇じゃないの。」
「・・・・・・。」
「ひとつ条件がある。」
「なんだ。言ってみろ。」
「私が家庭教師に行く日の冷蔵庫の中に、必ずあなたの手作りスイーツを入れておいて。私、あなたの作ったチーズケーキの味が忘れられないの。」
渚の言葉に湊はまんざらでもない顔で笑った。
「そんなことか。わかった。必ずお前の為にスイーツを入れておく。」
「言っておきますけど、この話を受けるのは決してあなたの為ではないですからね。奈央君が心配なだけだから。そこを勘違いしないでよね。」
湊の目の前に人差し指を突き差しながらそういい放つ渚に、湊は苦笑した。
「わかってるよ。ほんとお前、素直じゃないな。」
「じゃ、交渉成立ってことで。」
「ああ。よろしく頼む。」
渚が右手を出し、湊もその手をしっかりと握りしめた。
「な、なに?」
「そこで・・・だ。本題はここからなんだが。」
まだ本題に入ってなかったの?!
「お前に奈央の家庭教師を頼みたい。」
「・・・は?!」
「奈央はお前のことをあれからずっと気にしている。渚ともう一度会いたい、遊びたいと俺に訴えてくる。」
「・・・・・・。」
「俺も奈央のそばにお前のような人間がいてくれたら何かと安心だし・・・正直な話、お前を家に連れていけば奈央は俺のことを少しは見直すかもしれない。」
「あきれた!自分の好感度を上げるために私を利用するってわけ?」
「金なら弾む。ちょっとした小遣い稼ぎにもなるだろうし、お前にとっても悪くない話だと思うが。」
「見損なわないでよ。お金の為だけに動くほど、私暇じゃないの。」
「・・・・・・。」
「ひとつ条件がある。」
「なんだ。言ってみろ。」
「私が家庭教師に行く日の冷蔵庫の中に、必ずあなたの手作りスイーツを入れておいて。私、あなたの作ったチーズケーキの味が忘れられないの。」
渚の言葉に湊はまんざらでもない顔で笑った。
「そんなことか。わかった。必ずお前の為にスイーツを入れておく。」
「言っておきますけど、この話を受けるのは決してあなたの為ではないですからね。奈央君が心配なだけだから。そこを勘違いしないでよね。」
湊の目の前に人差し指を突き差しながらそういい放つ渚に、湊は苦笑した。
「わかってるよ。ほんとお前、素直じゃないな。」
「じゃ、交渉成立ってことで。」
「ああ。よろしく頼む。」
渚が右手を出し、湊もその手をしっかりと握りしめた。