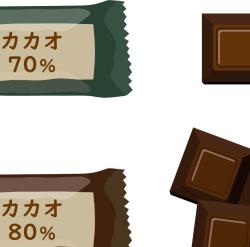「奈央は俺の義姉、美里のひとり息子だ。俺の父親と美里の母親は連れ子同士の再婚だから、俺と奈央の血は繋がってはいない。けどな、奈央は俺にとって大事な甥だ」
湊のその真剣な表情に嘘は無いようだった。
「その美里さんや奈央君のお父さんは、あの家にはいないの?」
「美里は未婚の母だ。だから奈央の父親はいない。美里は・・・。」
そう言い淀み、湊は次の言葉を慎重に選んでいた。
「美里はある理由で家を離れている。今はそれしか言えない。」
「そう・・・。」
よっぽど複雑な事情があるのだろうと察し、渚はそれ以上追求しなかった。
「あの家には奈央の他に、奈央の身の回りの世話をする絹さんというハウスキーパーがいるだけだ。だからよっぽど仕事が立て込んでいるとき以外は、俺もあの家に戻ることにしている。俺には奈央をしっかり躾ける責任がある。奈央には一人前の男になり幸せになってもらいたい。そのためにはちゃんとした大人に育てなければならない。そう思っているんだが、俺も体育会系の男だからな・・・どうやら厳しく教育しすぎてしまったらしい。今や必要最低限のことしか俺と会話してくれない。ほとほと困っているのが現状だ。」
「なるほどね。大体想像がつくわ。」
渚は小さくため息をつき、肩を竦めた。
「テストで良い点を取ってきた時や、お手伝いをしてくれたとき、ちゃんと褒めてあげてる?」
「・・・心では良くやってると思ってはいるが口には・・・だってそんなことは当然だろ?それに俺は父親に褒められたことなんかない。」
「あなたが厳しい環境の中で自分を鼓舞して育ってきたことは賞賛に値するけれど、それを奈央君にも求めるのは可哀想よ。子供は褒められるとうんと嬉しいものなの。また頑張ろうって思うものなのよ。褒めて伸ばすことを意識しながら接していけば、奈央君は連城さんに少しづつでも心を開いていくと思う。そんな情けない顔しないで頑張って!叔父さん。」
湊のその真剣な表情に嘘は無いようだった。
「その美里さんや奈央君のお父さんは、あの家にはいないの?」
「美里は未婚の母だ。だから奈央の父親はいない。美里は・・・。」
そう言い淀み、湊は次の言葉を慎重に選んでいた。
「美里はある理由で家を離れている。今はそれしか言えない。」
「そう・・・。」
よっぽど複雑な事情があるのだろうと察し、渚はそれ以上追求しなかった。
「あの家には奈央の他に、奈央の身の回りの世話をする絹さんというハウスキーパーがいるだけだ。だからよっぽど仕事が立て込んでいるとき以外は、俺もあの家に戻ることにしている。俺には奈央をしっかり躾ける責任がある。奈央には一人前の男になり幸せになってもらいたい。そのためにはちゃんとした大人に育てなければならない。そう思っているんだが、俺も体育会系の男だからな・・・どうやら厳しく教育しすぎてしまったらしい。今や必要最低限のことしか俺と会話してくれない。ほとほと困っているのが現状だ。」
「なるほどね。大体想像がつくわ。」
渚は小さくため息をつき、肩を竦めた。
「テストで良い点を取ってきた時や、お手伝いをしてくれたとき、ちゃんと褒めてあげてる?」
「・・・心では良くやってると思ってはいるが口には・・・だってそんなことは当然だろ?それに俺は父親に褒められたことなんかない。」
「あなたが厳しい環境の中で自分を鼓舞して育ってきたことは賞賛に値するけれど、それを奈央君にも求めるのは可哀想よ。子供は褒められるとうんと嬉しいものなの。また頑張ろうって思うものなのよ。褒めて伸ばすことを意識しながら接していけば、奈央君は連城さんに少しづつでも心を開いていくと思う。そんな情けない顔しないで頑張って!叔父さん。」