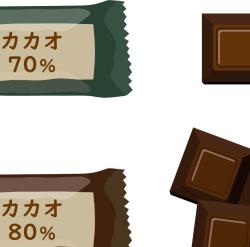「ここがお前のいきつけの店か。」
湊と居酒屋「はな」ののれんをくぐった渚は、カウンターの中にいる華に「いらっしゃいませ~」と声をかけられ、「華、久しぶり~」と答えた。
席に着いた湊は熱いおしぼりタオルで両手を拭きながら、店内を見回した。
麻で作られた桃色の座布団が座敷に敷かれ、華が旅先で購入した猫の小物がそこかしこに飾られている。
「私の親友が店のオーナーなの。可愛いお店でしょ?」
「まあ・・・素朴で個性的な店ではある。」
「あなたみたいな人はお高い店にしか行かないでしょうから、新鮮なんじゃない?」
「先入観で人を見るな。俺だって居酒屋やチェーンのコーヒーショップにだって入る。」
湊はそう言って憮然とした。
「どうせスタバのテラス席でブラックコーヒーでも飲みながらパソコン広げてるんでしょ?忙しく仕事している俺って格好いいだろ?みたいな?」
「それの何が悪い?あそこは仕事に集中出来るんだよ。」
「うわあ。否定しないんだ。」
「お前こそ小洒落たカフェでスイーツの写真を撮ってSNSにせっせと上げてんだろ?プライベートも充実してる私を見て?ってな。」
「はあ?それの何が悪いの?そういう話題ってお客様との会話を円滑にするものなのよ!」
店の一番奥のテーブルで向かい合ってやいのやいのと言い合う渚と湊の元に、華がお通しを持って顔を出した。
華はにやにやとしながら渚の顔をちらりと見て、お通しをテーブルに置いた。
「華、ビールひとつ。連城さんはなにをお飲みになります?」
湊は少し間を置いたあと、「俺もビールでお願いします。」と華に告げた。
華は渚にこっそり耳打ちした。
「彼氏がいないなんていつも言ってるくせに、渚もやるじゃない。こんないい男と差しで飲みにくるなんて。このこの~。」
「勘違いしないでくれる?この人は彼氏どころか友達でも客でもなんでもないの。ただの知り合い。」
渚の声が聞こえているのかいないのか、湊は平然とした顔で箸を取りお通しの切り干し大根を口にした。