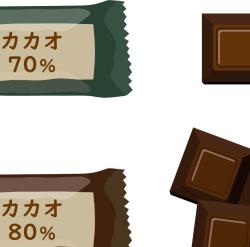そんなことを思いながら綿菓子のような雲が浮かぶ初夏の空を見上げていると、自分が情けなくて、女としての価値がまったく無いことを突きつけられたようで、いつのまにか涙が目尻に溜まり、その雫が頬を伝った。
結局私は誰にも選ばれない女なのよ。
誰でもいい・・・誰か私を慰めてくれないかな・・・
鼻ををすすりながら涙を拭い、ふと気づくと隣に気配を感じた。
見るといつのまに座ったのか、10歳くらいの少年が、膝に置いた雑誌をみつめ右手に鉛筆を持ち、渚の隣でぶつぶつと何かをつぶやいていた。
色が白く線の細い身体、黒目がちのまん丸なお目々は猫のように可愛らしい。
私立の小学校へ通っているのか、白いブラウスに紺のズボン、そして深緑のベストの胸元にはエンブレムが刺繍されている。
そこはかとない気品が漂っていて、この子は良家のお坊ちゃまなのではなかろうかと渚は思った。
それにしてもこんなところでお勉強?
渚がちらりと少年を見ると、少年もじっと渚をみつめていた。
そしておもむろに口を開いた。
「お姉さん、泣いてるの?」
「な、泣いてなんかないよ?ちょっと目にゴミが入っただけ。」
「そうですか。初めまして。こんにちは。」
「あっはい!・・・こんにちは。」
「僕、奈央といいます。」
礼儀正しい口調で自己紹介をした少年を前に、渚はぽかんと口を開けた。
もしかして私も自己紹介したほうがいいの??
渚を心配そうにじっとみつめる少年に励まされたような気持ちになった渚は、さっきまでの憂鬱を吹き飛ばし元気よく答えた。
「私は渚っていうの。よろしくね!」
そう言って微笑む渚に少年は真面目な顔をして腕を組んだ。
「これでお姉さんと僕はもう友達ですね。」
「え?まあ・・・そういうことになるのかな。」
「保護者に知らない人とは話してはいけないと言われているので。」
「そ、そうなのね。」
挨拶しただけで友達って言えるのか?と疑問に思う渚に、奈央は持っていた雑誌を広げてみせた。
見るとそれはクロスワードパズルの雑誌だった。
奈央の開いたページのパズルはほとんど文字が埋まっていて、あともう少しで全問クリアというところだ。
結局私は誰にも選ばれない女なのよ。
誰でもいい・・・誰か私を慰めてくれないかな・・・
鼻ををすすりながら涙を拭い、ふと気づくと隣に気配を感じた。
見るといつのまに座ったのか、10歳くらいの少年が、膝に置いた雑誌をみつめ右手に鉛筆を持ち、渚の隣でぶつぶつと何かをつぶやいていた。
色が白く線の細い身体、黒目がちのまん丸なお目々は猫のように可愛らしい。
私立の小学校へ通っているのか、白いブラウスに紺のズボン、そして深緑のベストの胸元にはエンブレムが刺繍されている。
そこはかとない気品が漂っていて、この子は良家のお坊ちゃまなのではなかろうかと渚は思った。
それにしてもこんなところでお勉強?
渚がちらりと少年を見ると、少年もじっと渚をみつめていた。
そしておもむろに口を開いた。
「お姉さん、泣いてるの?」
「な、泣いてなんかないよ?ちょっと目にゴミが入っただけ。」
「そうですか。初めまして。こんにちは。」
「あっはい!・・・こんにちは。」
「僕、奈央といいます。」
礼儀正しい口調で自己紹介をした少年を前に、渚はぽかんと口を開けた。
もしかして私も自己紹介したほうがいいの??
渚を心配そうにじっとみつめる少年に励まされたような気持ちになった渚は、さっきまでの憂鬱を吹き飛ばし元気よく答えた。
「私は渚っていうの。よろしくね!」
そう言って微笑む渚に少年は真面目な顔をして腕を組んだ。
「これでお姉さんと僕はもう友達ですね。」
「え?まあ・・・そういうことになるのかな。」
「保護者に知らない人とは話してはいけないと言われているので。」
「そ、そうなのね。」
挨拶しただけで友達って言えるのか?と疑問に思う渚に、奈央は持っていた雑誌を広げてみせた。
見るとそれはクロスワードパズルの雑誌だった。
奈央の開いたページのパズルはほとんど文字が埋まっていて、あともう少しで全問クリアというところだ。