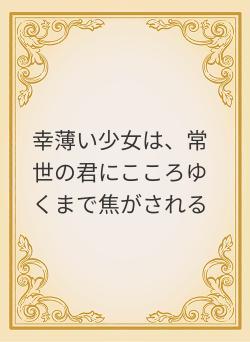数日後、朝のニュースで天気予報が流れた。
この前梅雨があけたと言っていたが、今日の午後からは雨がふるかもしれないみたいだ。
私は今日は少し気合いを入れて、身支度を整えた。
「じゃ行ってきまーす」
リビングに声をかけると、母が顔を出した。
「今日は雨ふるよ、傘持っていきなさい。いっつも忘れるんだから」
「……」
聞こえてないフリをして靴を履いていると、母が玄関までやってきた。
「聞いてるの? 傘、持ってきなさい」
私はしかたなく傘を握りしめ、家を出た。
昼間は晴れていたが、午後からは上空にうろこ雲が見え始めた。
空全体が雲におおわれていく。
放課後になるにつれ、私の期待もふくらんでいった。
そして五時間目の休み時間。
「あ、降ってきた」
隣の席の溝口がつぶやいた。私も思わず窓を見る。
「こりゃ今日も部活は中止だな、大会が近いってのに残念だよな」
「そうだねー」
私は一人、こぶしを握りしめた。
放課後、少し時間をつぶしてから教室を後にした。
昇降口まで来た時、私の胸は音を立てた。
出口のところに碓氷先輩が一人で立っていたからだ。
ザーザー降りの外を物憂げに眺めている。
「先輩? まだいたんですか」
私は平静をよそおって話しかけた。
「お、一ノ瀬。まあ、いろいろあって」
「そうですか」
「あれ、お前傘は?」
「忘れました」
私の堂々とした言葉に、眉をひそめる先輩。
「またかよ、どうすんだよ」
「大丈夫です。なんとかなりました」
「なんとか?」
私は答える代わりに、先輩の持っている傘を指差して、にやりと頬を緩める。
先輩は吹き出した。柄にもない笑顔がやっぱりステキだ。
「しゃーねー。また入ってくか?」
「はい、よろこんで!」
☂
その後、駅までの道を、他愛もない話をしながら二人で歩いた。
「あれ、雨やんだ?」
「あ、やんでますね」
とっくに気づいていたけど黙っていた。
先輩が傘をたたんでしまったため、二人の距離が少し離れてしまう。
その時、先輩が空を指差した。
「見て!」
「わあ! 虹だ」
空には大きな虹がアーチを描いている。
私たちは同時に足を止めて、立ち止まった。
今しかない──。
「先輩。この前、ありがとうございました」
改まって喋りだした私の顔を、先輩はまじまじと見つめてきた。
なんのことか思い出したようで、「や、別に」とだけつぶやく先輩。
「先輩、聞いてください」
私は溢れだす思いをおしとどめ、一度呼吸を整える。
先輩は表情を崩さずにじっと私を見つめている。
「先輩は、無口で、愛想はよくないし、何考えてるかわかんないし、女の子を、たくさん泣かせるけど……」
先輩の口角がわずかに上がる。
「私は、そんな先輩が大好きです」
言っちゃった。でも──よかった。
ずっと抑えていたモヤモヤが、口からすっと出て広がっていくような、そんなすがすがしさに包まれた。
目を見開いて、私を見つめる先輩。
その顔には肯定も否定もない。ただ受け止めてくれている安心感は感じ取れた。
この間に、耐えられず、叫びそうになる。
先輩の唇がわずかに動く。
「……ありがとう、ただ」
ダメだ。ふられた!
急に不安が襲い掛かってきて、私はうつむいた。怖くて先輩の顔が見れない。
この前告白してた子の気持ちが今ならわかる。とても顔を上げることなんてできない。
「一ノ瀬の気持ちには、答えられない」
聞いた瞬間、耳をふさぎたくなった。崖から落ちるような絶望感が襲ってきて──。
「今はね」
「……え」
「今は大会に集中したいから、だから、だから終わった後に」
先輩は、口を閉じてごくりと唾を飲み込んだ。
「あらためて俺の方から、言わせてほしい」
え、え……?
「な、なにを?」
私は目をぱちくりさせて尋ねる。
「お、同じことを」
先輩は唇をすぼめながら、たどたどしく声を出す。
「な、なん、ですか、それ……」
涙が次から次にあふれてくる。
「だから、一ノ瀬と同じ。俺の気持ちも」
「ちゃん、と……言って、くれないと……わかんないです」
「俺、一ノ瀬のこと──」
「ふふ、うそです! 困らせてみました!」
私は泣き笑いを浮かべながら、先輩の困ってる顔を見上げた。
「大会が終わった後にまた、教えてください!」
「あ、ああ。わかった……わかった。かならず、伝える」
私は嬉しいやら、なにやらで涙が止まらなかった。
先輩も同じだったことが、私と同じ気持ちだったことがとてもとてもうれしくて。
私は胸を張って、顔を上げた。
「先輩。夏の大会、頑張りましょうね」
先輩は優しく頬えむ。その顔を見るだけで胸がいっぱいになる。
「ああ。そばで支えてくれるか?」
「もちろんです!」
「足、よくなったらさ。いっしょに打とうな」
「はいっ!」
二人の夏が、始まった。
🌈
そうそう、折りたたみ傘がカバンにあったのは先輩には内緒だ。
Fin.