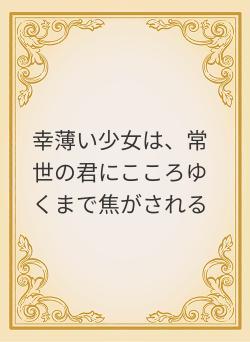【一ノ瀬、朝早くに悪いけど、今日空いてる?】
日曜日の朝、碓氷先輩からの電話で私は飛び起きた。
「あ、は、はい! どうしたんですか?」
心臓をバクバクさせながら話をうかがう。
【や、今日晴れてるからさ、せっかくだし練習しようかと思って、何人か声かけるから。一ノ瀬もこれないかな】
デートの誘いかと思った……! って、そんなわけないか……。
「──っ! 大丈夫です。準備してすぐ向かいます!」
私は早とちりした自分の感情を落ち着かせながら、身支度を始めた。
日曜日だけど、部活に行くのは全然イヤじゃない。だってテニスが好きだから。
先輩たちのプレイを見てるのは楽しいし、みんなが私を頼ってくれるならこんなに嬉しいことはない。
🎾
コートに着くと、部員は先輩を含めて四人来ていた。全員三年生のレギュラーメンバーだ。
男子テニス部のコートは二面あるので、人数的にはちょうどいい数だ。もしかしたら二年生以下には気をつかって声をかけなかったのかもしれない。
「いやー、晴れてよかったな」
「ひさびさだよなー」
ストレッチしている先輩たちの表情は明るい。
私もみんなの気持ちは痛いほどわかる。ずっと雨だったもん。
早く打ちたくてしょうがなかったに違いない。
小一時間、私はベンチに座り、練習を眺めていた。
さすが、レギュラーの先輩たちの動きはしなやかでかっこいい。中でも碓氷先輩のフォームはひときわキレイだった。
真剣な顔つきでラケットをふる碓氷先輩の姿に私は見惚れていた。
「一息入れようか」
汗を拭きながら小休止する先輩たち。
碓氷先輩がひとりで私の方へやってきた。
「なあ一ノ瀬、なんか飲み物って──」
私は、ハッとした。
「ごめんなさい。忘れてました……!」
申し訳なさそうにうなずく碓氷先輩。
「いいよいいよ。急だったから仕方ない。自販機でなんか買うから」
「あ、私が買ってきます。先輩たちは休んでてください」
じゃあ、と財布から千円札を取り出す先輩。
「これで足りるかな。一ノ瀬も買っていいから」
「あ、ありがとうございます」
「おーい、みんなリクエストはー?」
碓氷先輩の呼びかけに口々に答える他の三人。
「俺はアクアリアス」
「俺は爽建美茶」
「俺は黄色の炭酸のやつ」
私はみんなの返事にうなずきながら最後に碓氷先輩に尋ねる。
「先輩は何にしますか」
「同じやつ」
「え、えっと……同じ? 誰と」
「一ノ瀬」
「え? 私? 何を飲むか言ってませんよ」
「いつも飲んでるやつあるじゃん、ほら、あれ、あの」
「「さわやかオレンジ!!」」
同時に口にした私たちは、思わず笑いあった。
「そうそう、それ」
先輩、私が飲んでるもの見てたんだ……。なんかはずかしっ!
離れたところにある自販機まで行き飲み物を買っていると、後ろから女子たちの声がした。
振り返ると女子テニス部の同級生たちだった。日曜日だけど、彼女たちも自主練しにきたんだろうか。
「あ、一ノ瀬じゃん。何してんだろ」
「男たちに愛想ふりまいて楽しそうだよねいつも」
ひそひそと話す彼女たちの声は、しっかりと聞こえている。いや、聞こえるようにわざと言ってるのだ。
私は無視しながら一本ずつ飲み物を買っていく。
彼女たちとの軋轢は今に始まったことじゃない。いまさら何か言い返す気もない。
────────────────────────
一年生の頃、私は女子テニス部だった。
テニス部といえば、中学までは軟式が一般的だが、高校だと硬式しかない学校も多い。うちの高校もそうだった。
だけど私は中学の時から硬式テニスをやっていた。そのため、軟式テニスしか経験のない同級生たちと比べて、実力はかなり高かった。
夏の大会では、一年生なのに先輩たちを差し置いてレギュラーを獲得するくらいに。
おかげで同級生をはじめ、先輩たちからも嫉妬された。
負けず嫌いな私は、肩身の狭い思いをしながらも練習に励んだ。
そして、張り切りすぎた結果、夏の大会前に靭帯損傷という取り返しのつかないケガをしてしまった。
もちろんテニスどころじゃなく即入院。
夏休みはずっと病院でリハビリ生活だったけど、二学期が始まる頃にはなんとか歩けるくらいには回復した。
入院中、お見舞いに来る人は顧問の先生以外誰もいなかった。
夏休み明けに、久しぶりにコートに戻ると、私の居場所はどこにもなかった。
走ることもできない私は練習に参加することなどできない。部長にはマネージャーとしていさせてほしいと申し出たが、一部の部員たちから疎まれていたため渋い顔をされた。
そんな時、男子テニス部の部長になったばかりの碓氷先輩から声をかけてもらえたのだ。
────────────────────────
「一ノ瀬!」
そう、確かこんな感じで……。えっ……?
我に返って振り返ると、後ろに碓氷先輩が立っていた。
先輩、いつのまに、どうして……?
碓氷先輩は、少し険しい表情で私と後ろの女子たちを見比べている。
「あ、碓氷先輩、こんにちはー」
「おつかれさまでーす」
女子テニス部の子たちは、碓氷先輩に小声であいさつをする。先輩は何かいいたげに彼女たちに目を向けている。
そして、彼女たちはバツがわるくなったのか、足早に駆けていった。
「……どうしたんですか、先輩」
私は顔を見られたくなくて、すぐに顔を自販機の方に戻した。
「や、なんか、遅かったし、五本も持ってくるの、大変だろうなって思ってさ」
先輩の歯切れの悪い返事を聞きながら、私はあることに気が付いた。
そっか。テニスコートからはこの自販機が見えてるんだ……。
私がさっきの子たちに何か言われてるんじゃないかって心配して駆けつけてくれたんだろうな。
優しいな、先輩は……。
「──ちょうど、この自販機の前だったよな」
「え……」
「たしかあの時も、ここで声かけたろ、俺」
──あの時、私を男子テニス部のマネージャーに誘ってくれた時。
そうだ。忘れもしない。だって、今も思い出していたところだったから。
「どうして……私を誘ってくれたんですか?」
ハッキリ訊いたことはなかった。
「んー、なんかあの頃、元気なかったしさ。一ノ瀬のプレイは見てたから。ほっとけなかったし」
見てた……? 私のプレイを……。そうだったんだ。
初めて聞いた。胸がきゅっとしめつけられる。
「一ノ瀬のフォーム、変な癖がなくて、キレイでよかった」
顔が熱くなる。耳元まで赤くなってる気がする。
「見習いたいくらいだった」
「そんな、褒めすぎですよ……」
私はか細い声で反論する。
「先輩の方が、断然うまいじゃないですか」
「そんな……断然うまいってほどじゃない。こう見えてレギュラー維持するためにずっと必死にやってるよ」
知ってる。それは。誰よりも先輩を見てるから。
いつまでも後ろを向いてるのは失礼だと思い、涙をぬぐって振り返る。
碓氷先輩と視線がぶつかった。いつもの涼しげな瞳がまっすぐにこちらを向いている。
私の目はまだ腫れてるだろうか。
「先輩は、落ち込んじゃうことってありますか?」
なぜかふいに、口からこぼれた。
先輩は「あー」と一呼吸おいてから。
「あるよ。部長になってからは落ち込んでばかりだった。部員のこと、練習のこと、試合のことで頭がいっぱいで。正直自分の実力がどうとか二の次だったし。俺みたいな気の弱いやつが部長になるもんじゃないって思ったよ」
堰を切ったようにしゃべり出す先輩。なんだか珍しい……。
「そうだったんですね、意外でした……。今は大丈夫なんですか?」
「今は大丈夫。みんなの練習メニューを考えてくれたり、顧問との連絡係をまめにしてくれたり、部員たちとのコミュニケーションをよくとってくれたり──」
え……待って、なんだかそれって……。
「一ノ瀬のような優秀なマネージャーがいるおかげで助かってる」
私──。ちゃんと役に立ってたんだ……。
私は選手時代は自分の実力を伸ばすことしか考えてなかった。マネージャーになってからはとにかく選手たちのサポートに徹した。
部員たちひとりひとりに合った自主練メニューを立案してバックアップにつとめた。
時には口うるさく、暑苦しいくらいに。
それはつらい過去を忘れるためでもあった。けれど、マネージャーになったことでいろんなことへの視野が広がった。
なによりこうして、碓氷先輩がしっかりと私のことを見てくれていたことが、とても嬉しかった。
「一ノ瀬が元気になってくれてホントによかった」
碓氷先輩の、優しい笑顔が、やわらかに微笑んでくれてる顔が、にじんで見えない。
見たいのに──。
泣くな私。
どうしてだろう。涙が止まらない。
あの頃、さんざん泣いたはずなのに。涙が枯れるくらいに泣いたはずなのに。
その後、涙が落ち着くまで先輩とベンチに座って会話をした。
「ぷはー、うまいなこれ」
「でしょ?」
私と先輩の手には、さわやかオレンジの缶が握られている。
「先輩、ありがとうございます。おかげで気持ちが穏やかになりました」
「ん、よかった」
なんだか先輩の顔を見ると、いっそうドキドキするようになってしまった。
マネージャーと部長。互いに役割があるんだからしっかり線引きしなきゃいけないのに。
「大会も近いし、練習戻りましょうか」
私が立ち上がると。
「いつかいっしょに、打ちたいな」
え……。
先輩は小さな声でつぶやいた。座ったまま、目線は地面を見ている。
「私と、ですか?」
「うん、もし足がよくなったら」
「ホントに言ってます?」
先輩がすっと立ち上がる。
そして、私の目をまっすぐに見つめてくる。その視線はいつになく男らしい。
「俺は一ノ瀬といっしょにテニスがしたい」
息をのんだ。
頭が混乱する。言葉が出ない……。なにこれ……。
とにかくうなずいた。黙ったまま、こくこくっと首を何度もふる。
先輩の顔がみるみる赤くなっていく。
私の顔も今、たぶんこれくらい赤い、よね。
「とりあえず夏の大会に向けて、頑張るか──」
先輩は最後にそうしめくくって会話は終わった。
その後、数時間練習した後、みんなでいっしょに駅まで帰った。
先輩たちの会話は盛り上がっていた。もうじき梅雨が終わるから、夏の大会に向けて本格的に練習が出来ると意気込んでいる。
私は先日の先輩との相合傘を思い出して、梅雨が終わるのを少しさみしく思っていた。
帰ったあとも、先輩のことばかりが気になって気になって、何も手につかなかった。
先輩との今日の会話を思い出す。
私といっしょにテニスがしたいなんて、あれは勘違いじゃなければ……やっぱりそういう意味なんだろうか。
本当は今日も、この前みたいに先輩と二人で帰りたかったけど、あんな偶然はめったにない。
いつになるかわからないけど、もし次にチャンスがあったら、その時はちゃんと想いを伝えようと心に誓った。