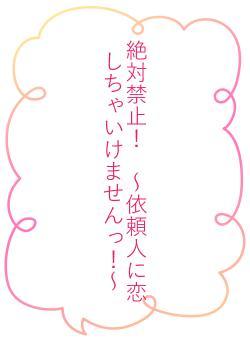蒼井先輩の声に、ピタリと足を止める。
「なに無言で逃げようとしてんだよ」
「いえ、別にそういうわけでは……」
わたしが蒼井先輩の方に向き直ると、蒼井先輩はもう一度視線をグラウンドへと向ける。
「俺ってさ、太陽の申し子みたいなとこあるだろ? だから、太陽が出てないと、なんとなく元気が出ないんだよね。顔の濡れたパンのヒーローみたいにさ」
渡り廊下の手すりに頬杖をついて、独り言のように蒼井先輩がつぶやく。
ふざけているのか、真面目なのか、よくわからない。
「そんで、三崎は? なんでそんな顔してんの?」
蒼井先輩がわたしの方を向き、じっと見つめてくる。
なんだか心の中まで覗かれてしまいそうで、わたしはすっと目をそらした。
「わたしは、いつも通りですよ」
そんなわたしのすぐそばまですたすたと歩いてくると、蒼井先輩がわたしの顔を覗き込んでくる。
「そう? はじめて駅で会ったときみたいに、泣きそうな顔してる」
ドキッと心臓が跳ねる。
まさか蒼井先輩が、あのときのことを覚えていてくれたなんて。
「そ、そんなことありません」
必死に平静を装って言い返す。
「ふぅん」
「なに無言で逃げようとしてんだよ」
「いえ、別にそういうわけでは……」
わたしが蒼井先輩の方に向き直ると、蒼井先輩はもう一度視線をグラウンドへと向ける。
「俺ってさ、太陽の申し子みたいなとこあるだろ? だから、太陽が出てないと、なんとなく元気が出ないんだよね。顔の濡れたパンのヒーローみたいにさ」
渡り廊下の手すりに頬杖をついて、独り言のように蒼井先輩がつぶやく。
ふざけているのか、真面目なのか、よくわからない。
「そんで、三崎は? なんでそんな顔してんの?」
蒼井先輩がわたしの方を向き、じっと見つめてくる。
なんだか心の中まで覗かれてしまいそうで、わたしはすっと目をそらした。
「わたしは、いつも通りですよ」
そんなわたしのすぐそばまですたすたと歩いてくると、蒼井先輩がわたしの顔を覗き込んでくる。
「そう? はじめて駅で会ったときみたいに、泣きそうな顔してる」
ドキッと心臓が跳ねる。
まさか蒼井先輩が、あのときのことを覚えていてくれたなんて。
「そ、そんなことありません」
必死に平静を装って言い返す。
「ふぅん」