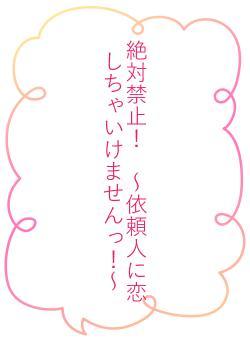先輩たちの目が怖い。
ぺこっと頭を下げると、わたしは足早にその場を立ち去った。
そのまましばらく歩いてから立ち止まると、空き教室の扉に背中を預ける。
また余計なことを言っちゃったかな。
でも、もう辞めるって決めてるし。このくらい、今さらどうってことない。
はーっ、と深く息を吐いてから、もう一度歩き出そうとしたとき——。
「三崎」
冷たい声で名前を呼ばれ、声の方を振り返る。
案の定、二年のマネの先輩たちが怖い顔で立っていた。
「さっきのどういうつもり? 予定もちゃんと覚えてないあたしらのこと、バカにしてんの?」
「別に予定覚えてたからって、偉いわけじゃないし。蒼井先輩に取り入ろうってのバレバレ」
「いちいち出しゃばんじゃねーよ」
わざわざそれを言うためだけに追いかけてきたの?
どれだけ暇なんだろ、この人たちは。
この人たちの言葉に傷つくのが、だんだんバカらしくなってきた。
「……そうですね。選手が競技に集中できるようにお手伝いするのが、マネージャーの仕事ですから、特別なことをしたとは思っていません」
ぐっと先輩たちを見据えて言い返す。
ぺこっと頭を下げると、わたしは足早にその場を立ち去った。
そのまましばらく歩いてから立ち止まると、空き教室の扉に背中を預ける。
また余計なことを言っちゃったかな。
でも、もう辞めるって決めてるし。このくらい、今さらどうってことない。
はーっ、と深く息を吐いてから、もう一度歩き出そうとしたとき——。
「三崎」
冷たい声で名前を呼ばれ、声の方を振り返る。
案の定、二年のマネの先輩たちが怖い顔で立っていた。
「さっきのどういうつもり? 予定もちゃんと覚えてないあたしらのこと、バカにしてんの?」
「別に予定覚えてたからって、偉いわけじゃないし。蒼井先輩に取り入ろうってのバレバレ」
「いちいち出しゃばんじゃねーよ」
わざわざそれを言うためだけに追いかけてきたの?
どれだけ暇なんだろ、この人たちは。
この人たちの言葉に傷つくのが、だんだんバカらしくなってきた。
「……そうですね。選手が競技に集中できるようにお手伝いするのが、マネージャーの仕事ですから、特別なことをしたとは思っていません」
ぐっと先輩たちを見据えて言い返す。