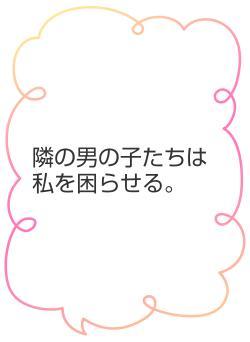「もういいよ、穂月も大変じゃん?だってさ、陸上部の大会なんてどこも太陽の光浴び放題なんだよ?無理じゃん!」
さっきは少し冷たくなっちゃったかもって思って、顔を上げて明るい普段通りのあたしで言ってみた。大きく口を開けて笑って見せて。
「そんなとこわざわざ来なくていいよ!たぶん穂月つまんないし!」
「何なんだよそれ…、緋呂が来いって言ったんだろ」
「だからもういいって言ってるの、見に来なくていいよ!」
笑って見せたの、なるべく。そしたら仕方ないかって穂月も言ってくれるんじゃないかと思って。
「…俺にはもう来てほしくないってこと?」
でもそんな顔で見られるなんて思わなかった。
そんな憂いだ瞳で見ないでよ。
「そうじゃないよ!来てほしいよ!」
「じゃあ行くよ」
「いいよ、来ないでよ!」
「どっちなんだよ!」
「だって来てほしいけど…っ」
最後の言葉は言っちゃいけなかったと思う。
1番言ったらダメだったと思う。
でも咄嗟に口からこぼれ出ちゃった。
「無理じゃん穂月には!」
つい立ち上がっちゃって、穂月はベッドに座って顔を見上げてあたしを見てた。
お互いに目が合ったまま息を止めた。
今のは傷付けた。
傷付けちゃった。
「…そうだな、俺には無理だよ」
「違う、そうじゃなくてあたしはっ」
「何が違うんだよ、迷惑なんだろ!?俺みたいなのが行ったらっ」
「そんなこと言ってない!あたしは来てほしいよ!」
あわててベッドの前に膝まずいた。
ふとんをきゅっと握って逸らされた視線をもう一度…
「穂月に見てほしいって思ってるもん、あたしの…っ」
「見るしか出来ないからな」
「…え」
合わせたいと思っていたのはあたしだけだった。
「見るぐらいしか俺には出来ない、しかも日陰から」
「穂月っ」
「だからいてもいなくても変わらないよな、実際」
「そんなことない!穂月がいてくれたらあたし…っ」
穂月がいてくれたらあたしはもっとがんばれる。
穂月が応援してくれたらもっと…
でもそれはあたしから見た穂月で。
「緋呂にはわからないよ」
それが穂月のためにあたしができることだと思ってた。
「当たり前に太陽の下を歩ける緋呂にはわからない」
穂月のために走るなんて、図々しかった。
「俺だって走りたいと思ってるよ…!」
キリッと眉を上げて睨みつけるみたいに、でも瞳の奥は悲しそうで。
だって穂月は太陽の光がダメだから、当たっちゃいけないから…外には出られなくて、真っ暗になった夜しか外を歩けないのが穂月だと思ってた。
それが普通であたり前で、そうゆうものだって思ってた。
だから少しでも連れ出せたら、そんなふうに思ってたの。
でも気付いちゃった。
運動部が多い部活も、グラウンドでやる体育祭も、何気ない登下校だって穂月にはできない。
それがあたしにはできるから…
今、気付いちゃった。
あたし、心のどこかで可哀想って思ってた。
さっきは少し冷たくなっちゃったかもって思って、顔を上げて明るい普段通りのあたしで言ってみた。大きく口を開けて笑って見せて。
「そんなとこわざわざ来なくていいよ!たぶん穂月つまんないし!」
「何なんだよそれ…、緋呂が来いって言ったんだろ」
「だからもういいって言ってるの、見に来なくていいよ!」
笑って見せたの、なるべく。そしたら仕方ないかって穂月も言ってくれるんじゃないかと思って。
「…俺にはもう来てほしくないってこと?」
でもそんな顔で見られるなんて思わなかった。
そんな憂いだ瞳で見ないでよ。
「そうじゃないよ!来てほしいよ!」
「じゃあ行くよ」
「いいよ、来ないでよ!」
「どっちなんだよ!」
「だって来てほしいけど…っ」
最後の言葉は言っちゃいけなかったと思う。
1番言ったらダメだったと思う。
でも咄嗟に口からこぼれ出ちゃった。
「無理じゃん穂月には!」
つい立ち上がっちゃって、穂月はベッドに座って顔を見上げてあたしを見てた。
お互いに目が合ったまま息を止めた。
今のは傷付けた。
傷付けちゃった。
「…そうだな、俺には無理だよ」
「違う、そうじゃなくてあたしはっ」
「何が違うんだよ、迷惑なんだろ!?俺みたいなのが行ったらっ」
「そんなこと言ってない!あたしは来てほしいよ!」
あわててベッドの前に膝まずいた。
ふとんをきゅっと握って逸らされた視線をもう一度…
「穂月に見てほしいって思ってるもん、あたしの…っ」
「見るしか出来ないからな」
「…え」
合わせたいと思っていたのはあたしだけだった。
「見るぐらいしか俺には出来ない、しかも日陰から」
「穂月っ」
「だからいてもいなくても変わらないよな、実際」
「そんなことない!穂月がいてくれたらあたし…っ」
穂月がいてくれたらあたしはもっとがんばれる。
穂月が応援してくれたらもっと…
でもそれはあたしから見た穂月で。
「緋呂にはわからないよ」
それが穂月のためにあたしができることだと思ってた。
「当たり前に太陽の下を歩ける緋呂にはわからない」
穂月のために走るなんて、図々しかった。
「俺だって走りたいと思ってるよ…!」
キリッと眉を上げて睨みつけるみたいに、でも瞳の奥は悲しそうで。
だって穂月は太陽の光がダメだから、当たっちゃいけないから…外には出られなくて、真っ暗になった夜しか外を歩けないのが穂月だと思ってた。
それが普通であたり前で、そうゆうものだって思ってた。
だから少しでも連れ出せたら、そんなふうに思ってたの。
でも気付いちゃった。
運動部が多い部活も、グラウンドでやる体育祭も、何気ない登下校だって穂月にはできない。
それがあたしにはできるから…
今、気付いちゃった。
あたし、心のどこかで可哀想って思ってた。