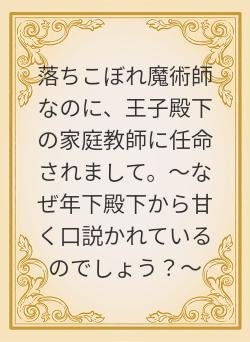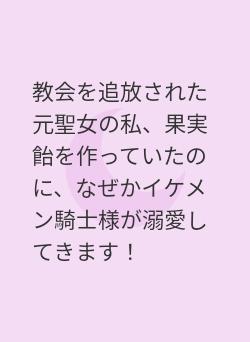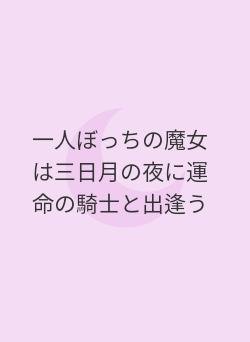「アリア嬢、君に悪役令嬢役を引き受けて欲しい」
「えっ!? えっ……??」
ライアン・シュミット公爵。28歳と若くして宰相を務める彼は、王家血筋の金色の髪に夜空を溶かしたような濃い青い瞳で、顔が良い。奥様とは仲睦まじく、皆が羨むほどの噂の夫婦である。
「君は王女に男遊びの汚名を着せられた。申し訳ないと思う。だが、そのまま悪役令嬢としての役を負ってくれないだろうか?」
彼の執務室に通されたアリアはポカン、とライアンを見つめた。
「あ、あの……王女殿下の汚名を着るのは良いのですが、私なんてとてもそんなことをしでかす器では無く……」
気の弱いアリアはボソボソとライアンに話す。
「君は寛大だね……自分で言っといて何だが、王女の汚名は酷いものだよ? 君は結婚も出来なくなるかもしれない」
アリアの言葉に目を大きく瞠り、ライアンが言った。
「あの……私は結婚なんて望んでおりません……。こんなですし、クラヴェル伯爵家は父の代で終わりでしょうし、私は働いて生計を立てて行きたかったのですが……こうなった以上、修道院にでも……ああ、でもこんな汚名では修道院も受け入れてくれないでしょうか……」
目を伏せてまくし立てるように話すアリアに、ライアンはふむ、と顎に手をやる。
「ではアリア嬢、こうしようじゃないか。この任務を完遂した後には、君を我がシュミット公爵領の領民として迎えると。生活には困らないように家も用意するし、どうだい?」
「シュミット……公爵領……」
ライアンの提案にアリアは震えた。
(シュミット公爵領といえば、自然が豊かで良い土地だと聞きます……! そこでのんびり暮らせたら……!)
「はは、返事はオーケーみたいだね?」
瞳を輝かせたアリアを見てライアンが目を細めた。
「あの、でも、私は何をすれば良いんでしょう……?」
不安そうに見上げるアリアに、ライアンは告げる。
「ああ。王女に近付いた子息の中できな臭い奴が何人かいてね。君にはそいつらに本当に近づいてもらって、探ってもらいたいんだ」
「……無理です」
「だろうね」
アリアの即答に、ライアンは眉尻を下げて笑った。
「君の王女付メイドとしての仕事は見てきた。これでも人を見る目はあるんだ私は」
「はあ……」
それでも自信ありげに語るライアンに、アリアは不安そうに返事をする。
「君に魔法をかけてあげるよ」
「ま……ほう?」
その言葉にアリアの瞳が輝いた。
「えっ!? えっ……??」
ライアン・シュミット公爵。28歳と若くして宰相を務める彼は、王家血筋の金色の髪に夜空を溶かしたような濃い青い瞳で、顔が良い。奥様とは仲睦まじく、皆が羨むほどの噂の夫婦である。
「君は王女に男遊びの汚名を着せられた。申し訳ないと思う。だが、そのまま悪役令嬢としての役を負ってくれないだろうか?」
彼の執務室に通されたアリアはポカン、とライアンを見つめた。
「あ、あの……王女殿下の汚名を着るのは良いのですが、私なんてとてもそんなことをしでかす器では無く……」
気の弱いアリアはボソボソとライアンに話す。
「君は寛大だね……自分で言っといて何だが、王女の汚名は酷いものだよ? 君は結婚も出来なくなるかもしれない」
アリアの言葉に目を大きく瞠り、ライアンが言った。
「あの……私は結婚なんて望んでおりません……。こんなですし、クラヴェル伯爵家は父の代で終わりでしょうし、私は働いて生計を立てて行きたかったのですが……こうなった以上、修道院にでも……ああ、でもこんな汚名では修道院も受け入れてくれないでしょうか……」
目を伏せてまくし立てるように話すアリアに、ライアンはふむ、と顎に手をやる。
「ではアリア嬢、こうしようじゃないか。この任務を完遂した後には、君を我がシュミット公爵領の領民として迎えると。生活には困らないように家も用意するし、どうだい?」
「シュミット……公爵領……」
ライアンの提案にアリアは震えた。
(シュミット公爵領といえば、自然が豊かで良い土地だと聞きます……! そこでのんびり暮らせたら……!)
「はは、返事はオーケーみたいだね?」
瞳を輝かせたアリアを見てライアンが目を細めた。
「あの、でも、私は何をすれば良いんでしょう……?」
不安そうに見上げるアリアに、ライアンは告げる。
「ああ。王女に近付いた子息の中できな臭い奴が何人かいてね。君にはそいつらに本当に近づいてもらって、探ってもらいたいんだ」
「……無理です」
「だろうね」
アリアの即答に、ライアンは眉尻を下げて笑った。
「君の王女付メイドとしての仕事は見てきた。これでも人を見る目はあるんだ私は」
「はあ……」
それでも自信ありげに語るライアンに、アリアは不安そうに返事をする。
「君に魔法をかけてあげるよ」
「ま……ほう?」
その言葉にアリアの瞳が輝いた。