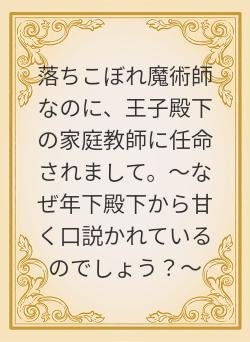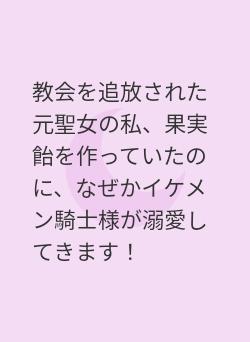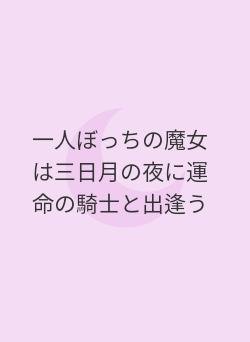「アリア、あんな事があった以上、君も標的にされかねない。今日は一緒に帰ろう。それまでここで過ごすと良い」
「えっ、で、でもお屋敷でのお仕事は……」
抱き合っていた二人は、フレディの言葉で床から立ち上がる。
昼食を届けて屋敷に帰ると、メイドとしての雑事をする。アリアはそれがあまり悪役令嬢として活躍出来ない自分の仕事であると思いつつあった。
「アリア? 君の一番の仕事は?」
「……フレディ様の妻です……」
フレディが意地悪な表情で聞けば、アリアはうっ、となりながらも答えた。
「で、ではせめて何かお手伝いさせてください!」
「アリアはいてくれるだけで良いんだけどなあ……」
困った顔で訴えかけるアリアに、フレディはうーん、と考えながら呟く。
「まあ、アリアはそれじゃ納得しないよね。わかった、それじゃあ、この机の上の本をそこの本棚に片してくれる?」
「かしこまりました!!」
アリアは顔を輝かせると、いそいそと本を片付け始める。
そんなアリアを愛おしい顔で見つめるフレディに、スティングはニヤニヤしながら言った。
「奥さんが働く姿に何がそんなに嬉しいのか謎ですけど、局長が幸せそうなら良かったです」
「そうか、お前がいたな」
「あー、ひっど! 局長、一応仕事中ですからね? イチャつくのは無しですよ!!」
ニヤニヤと誂うように叫ぶスティングに、フレディは「はいはい」と返事をして執務机に戻る。
フレディは優秀な魔法使いだが、昔魔力を暴走させてしまった苦い思い出から、極力魔法を使わないようにしている。
フレディほどの魔法使いがもったいない、と昔はよく言われていた。しかし、フレディが研究して出来た魔法具がこの国に広く浸透するようになると、フレディに余計なことを言う者はいなくなった。
誰もが魔法を使える訳では無い。フレディのように才能ある者が魔法省に入り、国のためにその力を使う。
フレディの魔法具は魔法を使えない国民たちにとって無くてはならない物だった。
「えっ、で、でもお屋敷でのお仕事は……」
抱き合っていた二人は、フレディの言葉で床から立ち上がる。
昼食を届けて屋敷に帰ると、メイドとしての雑事をする。アリアはそれがあまり悪役令嬢として活躍出来ない自分の仕事であると思いつつあった。
「アリア? 君の一番の仕事は?」
「……フレディ様の妻です……」
フレディが意地悪な表情で聞けば、アリアはうっ、となりながらも答えた。
「で、ではせめて何かお手伝いさせてください!」
「アリアはいてくれるだけで良いんだけどなあ……」
困った顔で訴えかけるアリアに、フレディはうーん、と考えながら呟く。
「まあ、アリアはそれじゃ納得しないよね。わかった、それじゃあ、この机の上の本をそこの本棚に片してくれる?」
「かしこまりました!!」
アリアは顔を輝かせると、いそいそと本を片付け始める。
そんなアリアを愛おしい顔で見つめるフレディに、スティングはニヤニヤしながら言った。
「奥さんが働く姿に何がそんなに嬉しいのか謎ですけど、局長が幸せそうなら良かったです」
「そうか、お前がいたな」
「あー、ひっど! 局長、一応仕事中ですからね? イチャつくのは無しですよ!!」
ニヤニヤと誂うように叫ぶスティングに、フレディは「はいはい」と返事をして執務机に戻る。
フレディは優秀な魔法使いだが、昔魔力を暴走させてしまった苦い思い出から、極力魔法を使わないようにしている。
フレディほどの魔法使いがもったいない、と昔はよく言われていた。しかし、フレディが研究して出来た魔法具がこの国に広く浸透するようになると、フレディに余計なことを言う者はいなくなった。
誰もが魔法を使える訳では無い。フレディのように才能ある者が魔法省に入り、国のためにその力を使う。
フレディの魔法具は魔法を使えない国民たちにとって無くてはならない物だった。