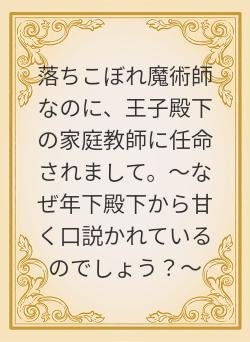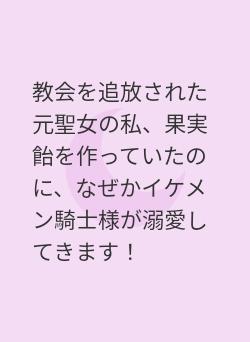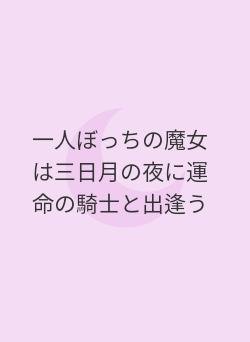令嬢たちの間を通り、持ってきたバスケットを床に置く。
「……酷い顔……スティングさん、お水をお願いします!」
「は、はいっ」
スティングはアリアの姿に戸惑いながらも急いで水差しのある棚に走る。
アリアはいつものお仕着せ姿ではなく、ラピスラズリを溶かし込んだような深みのある青のドレスで着飾っていた。
「アリア……その格好……」
「フレディ様、無理して喋らないでください」
朦朧としながらもアリアを見たフレディに、アリアはそっと肩を抱いた。
アリアに触れられた手にホッとしたフレディは、次第に息も整っていく。
「あなた、なんですの?!」
「そうですわ、割り込みなんてはしたないですわ!」
静観していた令嬢たちがアリアの存在にようやくハッとすると、口々に叫び始めた。
「フレディ様は体調が優れません! お、お引取りください!」
フレディの前にたちはだかるようにして両手を広げるアリア。
いつも自信が無さ気なアリアが、ぷるぷる震えながらも、令嬢たちに立ち向かっていた。その姿にフレディは目を瞠る。
「あ、貴方に何の権利があって……」
「あ、私、噂で聞きましたわ。フレディ様の寝室のシーツを洗濯していたメイドが、ラベンダー色の髪の毛を見つけたって!」
「じゃあ、貴方がフレディ様の愛人のメイド?!」
「ふえっ?!」
令嬢たちにやんやと責め立てられアリアは怯む。
「お、お引き取り、くださいっ!」
両手を広げたまま、アリアが力いっぱい叫ぶ。
しかし令嬢たちは不満そうな顔を見せて、アリアに詰め寄る。
「メイドなんかが私たちに命令するの?!」
「どうやってフレディ様に取り入ったのよ!」
令嬢の一人に肩を押されて、アリアは転びそうになった。
転ぶ――――と思ったその時、後ろでフレディがアリアを受け止めてくれた。
「フ、フレディ様!」
受け止めてくれたフレディの顔はまだ青く、アリアは心配になった。
そんなアリアの表情を見たフレディは、アリアににこっと微笑むと、怖い顔で令嬢たちを睨んだ。
「彼女は俺の唯一の大切な人だ! 愛人なんかじゃない! 俺の妻にこんなことをして、どうなるかわかっているのか?」
フレディの睨みに令嬢たちは青ざめながらも、「え?」「え?」と困惑している。
「去れ! 二度とここに来るな!!」
フレディが叫ぶと、令嬢たちは一目散に局長室を逃げ出して行った。
「……酷い顔……スティングさん、お水をお願いします!」
「は、はいっ」
スティングはアリアの姿に戸惑いながらも急いで水差しのある棚に走る。
アリアはいつものお仕着せ姿ではなく、ラピスラズリを溶かし込んだような深みのある青のドレスで着飾っていた。
「アリア……その格好……」
「フレディ様、無理して喋らないでください」
朦朧としながらもアリアを見たフレディに、アリアはそっと肩を抱いた。
アリアに触れられた手にホッとしたフレディは、次第に息も整っていく。
「あなた、なんですの?!」
「そうですわ、割り込みなんてはしたないですわ!」
静観していた令嬢たちがアリアの存在にようやくハッとすると、口々に叫び始めた。
「フレディ様は体調が優れません! お、お引取りください!」
フレディの前にたちはだかるようにして両手を広げるアリア。
いつも自信が無さ気なアリアが、ぷるぷる震えながらも、令嬢たちに立ち向かっていた。その姿にフレディは目を瞠る。
「あ、貴方に何の権利があって……」
「あ、私、噂で聞きましたわ。フレディ様の寝室のシーツを洗濯していたメイドが、ラベンダー色の髪の毛を見つけたって!」
「じゃあ、貴方がフレディ様の愛人のメイド?!」
「ふえっ?!」
令嬢たちにやんやと責め立てられアリアは怯む。
「お、お引き取り、くださいっ!」
両手を広げたまま、アリアが力いっぱい叫ぶ。
しかし令嬢たちは不満そうな顔を見せて、アリアに詰め寄る。
「メイドなんかが私たちに命令するの?!」
「どうやってフレディ様に取り入ったのよ!」
令嬢の一人に肩を押されて、アリアは転びそうになった。
転ぶ――――と思ったその時、後ろでフレディがアリアを受け止めてくれた。
「フ、フレディ様!」
受け止めてくれたフレディの顔はまだ青く、アリアは心配になった。
そんなアリアの表情を見たフレディは、アリアににこっと微笑むと、怖い顔で令嬢たちを睨んだ。
「彼女は俺の唯一の大切な人だ! 愛人なんかじゃない! 俺の妻にこんなことをして、どうなるかわかっているのか?」
フレディの睨みに令嬢たちは青ざめながらも、「え?」「え?」と困惑している。
「去れ! 二度とここに来るな!!」
フレディが叫ぶと、令嬢たちは一目散に局長室を逃げ出して行った。