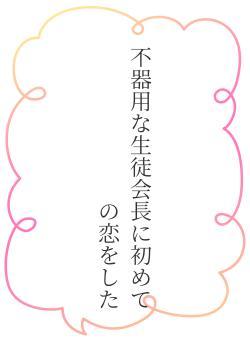背中まである髪を一つに束ねて、口に咥えていたヘアゴムで結ぶ。
緊張のあまり手が震えているのが自分でも分かる。それくらい、今日は重要なことをしに行くんだ。
「星奈ちゃん、準備できたー?」
「うん、待たせてごめん。行こう」
また、傷つくかもしれない。あのときのように。でもきっとスグルが傍にいてくれるなら大丈夫だ。そう思いながら呼吸を整える。
――今日はお母さんの妹、私にとっての叔母さんに会いに行く。私のことを “可哀想” だと思っている、本人に。
どうしてこういうことになったのかというと、スグルの一言が理由だった。
「星奈ちゃんはさ、その可哀想だって言った叔母さんに会いに行かないの?」
「……行って、どうなるの」
できるだけそのは話題は避けたかったものの、どうしても嫌だと言えなかった。
叔母さんに会ったら、きっとまた裏切られるのが怖くなってしまう。最近少しだけ人間不信を克服してきたのに。
「行きたくないよ。ていうか、行けないの。勇気が出ないの、怖いんだよ……」
「えぇ、だってひどくない? 話聞いてるだけの僕ですら怒りが湧くんだから、星奈ちゃんは相当ムカついてるよね。ガツンと言ってやろうよ」
スグルがそんなに怒っているなんて珍しい……とは思ったものの、私のために一生懸命なところが本当に優しい。
確かに二人のことがすごく嫌いだし、怒りはとっくに湧いている。
拳を握りしめて、口を開いた。
「――分かった。私、叔母さんに会いに行ってみる」
そして今日、叔母さんに急遽会いに行くことになったのだ。
叔母さんが留守にしていたら話せないから、それはそれで嬉しい気がするけれど……。
確かにスグルが言っていた通り、私は怒りでいっぱいだと思う。
「じゃあ行こっか、星奈ちゃん!」
「本当にいいの? スグルも一緒に来てもらって」
「もちろんだよ。俺は星奈ちゃんを助けるのが責務なんだからね」
何度も別に一人で行くからいい、と言ってはみたものの、私のことは一切聞いてくれなかった。
本当はスグルがいてくれたほうが心強い。いてほしいと思っている。けれど私のせいで迷惑をかけたら……なんて考えるだけで不安になってしまう。
「あ、星奈ちゃん、いま俺に申し訳ないなぁ〜なんて思ったでしょ?」
「……そんな可愛くは思ってないけど」
「あははっ、星奈ちゃんは冷たいもんねぇ」
「ちょ、どういう意味!?」
私っていつもそんなに冷たいかなぁ、なんて思う。スグルには素を出しているつもりだから、私は優しくしていないのかもしれない。
今度からは優しく接しよう。真面目にそう考えていたら、スグルはぷっと吹き出した。
「星奈ちゃん、いまの嘘だよ。わざと言ったんだ」
「えっ、わざと? ……どういうこと?」
「星奈ちゃんはそれでこそ星奈ちゃんだからね! いつも俺に対してちょっと冷たいのが本当の星奈ちゃんでしょ?」
……そっか。私は遥花ちゃんや東間さんの前ではまた裏切られるのが怖いから、優しく接するように心がけている。
でもスグルの前だと “優しくしなきゃ” なんて考えることがない。これが本当の素の私なんだ――。
「ありがと、スグル。今日頑張る」
「うん! 頑張ろう!」
あれほど拒否してきた人に会うのだから、それなりには緊張している。というか、不安でいっぱいだ。
でも大丈夫。隣には大好きな人が、お星さまが傍にいてくれるから……!
電車に乗って二時間程で、叔母さんの家に到着した。ここ数年来ていなかったけれど、確かにこんな家だったなぁなんて懐かしくなる。
今日はありのままの気持ちをぶつけに来たのだから、ちゃんと本音を伝えないと……。
深呼吸をして、家のインターホンを鳴らした。
「はーい」
ちっとも変わっていない、明るくてトーンが高い叔母さんの声が聞こえた。
家からドタドタと走る足音も聞こえてくる。それと同時に頭の中まで響くぐらい、私の心臓の鼓動も早い。
「変わってないなぁ」
誰にも聞こえないような声量で、スグルはボソッと呟いた。
スグルは叔母さんのことを知っているのだろうか。でも、どうして――?
「星奈ちゃん、大丈夫だから。星奈ちゃんがあのとき抱えていた感情を伝えてね。俺はここで待ってるから」
コソッ、とスグルが耳打ちしてきた。疑問を忘れるくらい、また胸がぎゅーっと締め付けられる。
あぁもう、こんなときにドキドキしてどうするの……!
今日は逃げてしまったあのときの感情を、ありのまま言わなきゃ。そのために来たのだから。
「こんにちはー……って、うそ、星奈ちゃん?」
叔母さんは私を見て、薄暗い険悪な顔をしていた。やっぱり私のこと、まだ嫌っているのだろうか。可哀想だと思っているのだろうか。
怖い。怖くて、怖くて、怖くて……不安で押し潰されてしまいそうなくらい。
でも逃げてばかりじゃだめだ。私自身が変わらないと……!
「お久しぶりです、星奈です。今日は急に押しかけてしまってすみません。叔母さん、お時間ありますか?」
「……ええ。もちろん。どうぞ上がって」
あれから二年ほど経った今でも、声だけでなく叔母さんの雰囲気は変わっていなかった。ほわほわとした陽だまりのような優しい存在……。
小さい頃から、叔母さんが大好きだった。お母さんの妹だからというのもあるけれど、私にとても良くしてくれていたから。
だからこそ、叔母さんと旦那さんの会話を聞いたとき、とても辛かったのだ。
「星奈ちゃん、本当にお久しぶり。もう何年会っていなかったかしら」
「だいたい二年くらいです」
「あら、もうそんなに時が経っているのね。早いわ……」
そっか……叔母さんは、私がいなくなってからの二年間は、早いと感じていたんだ。
その時が経つのが早いと思っている二年間、私はずっと苦しめられてきたんだよ。ずっと人を信じることができなかったんだよ。
心のなかの気持ちをつい出してしまいそうだったけれど、何とか抑えることができた。
「星奈ちゃん、急にいなくなったじゃない? 心配したのよ」
突然なその話題に体をビクッ、と震わせる。
軽々と『心配した』だなんてどうして言えるのだろう。そんなに心がこもっていない言葉は初めて聞いた。
「だから、また元気な顔を見れて安心したわ」
「元気じゃ、ない、です」
「えっ? でも……」
「全然、元気なんかじゃありません。元気だと言われるように、振る舞っているだけです」
人に機嫌を伺われないように。もう二度と “両親がいなくなって可哀想” なんて言われないように。
私はずっと自分の心を押し殺して頑張ってきたんだ。
「星奈ちゃんは、あの頃からずっと変わってしまったのね」
「あの頃、って……?」
「星奈ちゃんがまだ、幼かった頃。無邪気で、明るくて、ほんと元気の塊って感じの子だったのよ。それがもう高校生にまでなっちゃって、すっかり変わっちゃったのね」
違う。違う、変わったのは私じゃない。変わったのは私の運命だ。私は昔のまま、ずっと変わっていない。
両親がいない世界を生きなければならなくなった、運命が変わってしまったんだ――。
「あのさ、星奈ちゃん。一つ聞きたいんだけどいい?」
「……はい。何ですか」
「星奈ちゃんはあの日、どうして急にいなくなってしまったの?」
不安で不安でたまらない。正直、上手く本音を話せる自信がない。
でもきっと、スグルが私のことを応援してくれている。だから大丈夫だ。
呼吸を整えてから、私は口を開いた。
「聞いちゃったんです。叔母さんと旦那さんが、私のことを “可哀想” だと言っていたのを」
そう言うと、叔母さんは目を丸くして驚いていた。
それでも私の話を真剣に聞いてくれている。
「転校する前も、叔母さんたちにも、戻ったあとも可哀想だと言われ続けました。両親がいない私は、普通じゃない、変わっているんだって。そう思い始めるようになりました」
みんなは両親がいて、私は両親がいなくなった。
みんな違ってみんないい、という言葉はあるけれど、これには絶対に通用しない。だから私は変わり者なんだと思い始めたんだ。
「すごく辛くて、悲しくて、寂しくて。私だって普通の人間なのに……っ。どうしてお母さんもお父さんもいなくなっちゃったんだって。今思うと、中学生で一人暮らししてたなんて異常ですよね。ほんと、当時はそんなの考えないくらい “可哀想” が辛くて」
話し始めたら、ずっと止まらなかった。
本音を伝えているうちに、自分はこんなことを思っていたのか、なんて新たな発見もあった。
「私はそれ以来、人間不信になって。また裏切られるのが怖くて――」
「落ち着いて、星奈ちゃん」
はぁ、はぁ、と息が荒くなっていく私の背中を、叔母さんが擦ってくれた。
――あぁ。温もりのある、叔母さんの手だ。小さい頃、危ないからといって手を繋いでくれたこともあったっけ。
……私、どうしていままで、叔母さんのことを考えずにいたのだろう。
「叔母さんは、私のこと可哀想だって思ってるんですよね? みんなとは違う、変わっている私のことを……っ」
「思ってないよ、星奈ちゃん」
涙が零れ落ちながら、私は叔母さんの表情を見た。
確かに嘘は吐いていなそうな、真っ直ぐな瞳だ。私のことを真剣に考えてくれているのが分かる。
「で、でも、可哀想って……」
「星奈ちゃんのこともあるけど、星奈ちゃんのお母さん――仁美の気持ちも考えたの。二人のことを考えると、やっぱりすごく辛いだろうなって。私が星奈ちゃんだったら、ほんとに立ち直れないから」
叔母さんは――私のことを変わり者だと思って、侮辱した意味で “可哀想” と言ったのかと思った。
でも本当は、私がどれだけ辛い思いをしているか考えてくれていた。そういうこと……?
「ごめんなさい、星奈ちゃん。私のせいでこんなに辛い思いを抱えさせてしまって」
「……ううん。私のほうこそ、勝手に出ていっちゃってごめんなさい。叔母さんは私が小さい頃から優しくて、すごく――大好きだから。私のことを考えてくれていたなんて知らなかった……っ!」
叔母さんの “可哀想” という言葉は、私への愛情で溢れていた。それを私は、ただ勘違いしていただけなんだ。
こんなに泣いたのは両親が亡くなってから初めてだろう。私は何粒もの涙を零しながら、叔母さんの腕の中で抱きしめられていた。
緊張のあまり手が震えているのが自分でも分かる。それくらい、今日は重要なことをしに行くんだ。
「星奈ちゃん、準備できたー?」
「うん、待たせてごめん。行こう」
また、傷つくかもしれない。あのときのように。でもきっとスグルが傍にいてくれるなら大丈夫だ。そう思いながら呼吸を整える。
――今日はお母さんの妹、私にとっての叔母さんに会いに行く。私のことを “可哀想” だと思っている、本人に。
どうしてこういうことになったのかというと、スグルの一言が理由だった。
「星奈ちゃんはさ、その可哀想だって言った叔母さんに会いに行かないの?」
「……行って、どうなるの」
できるだけそのは話題は避けたかったものの、どうしても嫌だと言えなかった。
叔母さんに会ったら、きっとまた裏切られるのが怖くなってしまう。最近少しだけ人間不信を克服してきたのに。
「行きたくないよ。ていうか、行けないの。勇気が出ないの、怖いんだよ……」
「えぇ、だってひどくない? 話聞いてるだけの僕ですら怒りが湧くんだから、星奈ちゃんは相当ムカついてるよね。ガツンと言ってやろうよ」
スグルがそんなに怒っているなんて珍しい……とは思ったものの、私のために一生懸命なところが本当に優しい。
確かに二人のことがすごく嫌いだし、怒りはとっくに湧いている。
拳を握りしめて、口を開いた。
「――分かった。私、叔母さんに会いに行ってみる」
そして今日、叔母さんに急遽会いに行くことになったのだ。
叔母さんが留守にしていたら話せないから、それはそれで嬉しい気がするけれど……。
確かにスグルが言っていた通り、私は怒りでいっぱいだと思う。
「じゃあ行こっか、星奈ちゃん!」
「本当にいいの? スグルも一緒に来てもらって」
「もちろんだよ。俺は星奈ちゃんを助けるのが責務なんだからね」
何度も別に一人で行くからいい、と言ってはみたものの、私のことは一切聞いてくれなかった。
本当はスグルがいてくれたほうが心強い。いてほしいと思っている。けれど私のせいで迷惑をかけたら……なんて考えるだけで不安になってしまう。
「あ、星奈ちゃん、いま俺に申し訳ないなぁ〜なんて思ったでしょ?」
「……そんな可愛くは思ってないけど」
「あははっ、星奈ちゃんは冷たいもんねぇ」
「ちょ、どういう意味!?」
私っていつもそんなに冷たいかなぁ、なんて思う。スグルには素を出しているつもりだから、私は優しくしていないのかもしれない。
今度からは優しく接しよう。真面目にそう考えていたら、スグルはぷっと吹き出した。
「星奈ちゃん、いまの嘘だよ。わざと言ったんだ」
「えっ、わざと? ……どういうこと?」
「星奈ちゃんはそれでこそ星奈ちゃんだからね! いつも俺に対してちょっと冷たいのが本当の星奈ちゃんでしょ?」
……そっか。私は遥花ちゃんや東間さんの前ではまた裏切られるのが怖いから、優しく接するように心がけている。
でもスグルの前だと “優しくしなきゃ” なんて考えることがない。これが本当の素の私なんだ――。
「ありがと、スグル。今日頑張る」
「うん! 頑張ろう!」
あれほど拒否してきた人に会うのだから、それなりには緊張している。というか、不安でいっぱいだ。
でも大丈夫。隣には大好きな人が、お星さまが傍にいてくれるから……!
電車に乗って二時間程で、叔母さんの家に到着した。ここ数年来ていなかったけれど、確かにこんな家だったなぁなんて懐かしくなる。
今日はありのままの気持ちをぶつけに来たのだから、ちゃんと本音を伝えないと……。
深呼吸をして、家のインターホンを鳴らした。
「はーい」
ちっとも変わっていない、明るくてトーンが高い叔母さんの声が聞こえた。
家からドタドタと走る足音も聞こえてくる。それと同時に頭の中まで響くぐらい、私の心臓の鼓動も早い。
「変わってないなぁ」
誰にも聞こえないような声量で、スグルはボソッと呟いた。
スグルは叔母さんのことを知っているのだろうか。でも、どうして――?
「星奈ちゃん、大丈夫だから。星奈ちゃんがあのとき抱えていた感情を伝えてね。俺はここで待ってるから」
コソッ、とスグルが耳打ちしてきた。疑問を忘れるくらい、また胸がぎゅーっと締め付けられる。
あぁもう、こんなときにドキドキしてどうするの……!
今日は逃げてしまったあのときの感情を、ありのまま言わなきゃ。そのために来たのだから。
「こんにちはー……って、うそ、星奈ちゃん?」
叔母さんは私を見て、薄暗い険悪な顔をしていた。やっぱり私のこと、まだ嫌っているのだろうか。可哀想だと思っているのだろうか。
怖い。怖くて、怖くて、怖くて……不安で押し潰されてしまいそうなくらい。
でも逃げてばかりじゃだめだ。私自身が変わらないと……!
「お久しぶりです、星奈です。今日は急に押しかけてしまってすみません。叔母さん、お時間ありますか?」
「……ええ。もちろん。どうぞ上がって」
あれから二年ほど経った今でも、声だけでなく叔母さんの雰囲気は変わっていなかった。ほわほわとした陽だまりのような優しい存在……。
小さい頃から、叔母さんが大好きだった。お母さんの妹だからというのもあるけれど、私にとても良くしてくれていたから。
だからこそ、叔母さんと旦那さんの会話を聞いたとき、とても辛かったのだ。
「星奈ちゃん、本当にお久しぶり。もう何年会っていなかったかしら」
「だいたい二年くらいです」
「あら、もうそんなに時が経っているのね。早いわ……」
そっか……叔母さんは、私がいなくなってからの二年間は、早いと感じていたんだ。
その時が経つのが早いと思っている二年間、私はずっと苦しめられてきたんだよ。ずっと人を信じることができなかったんだよ。
心のなかの気持ちをつい出してしまいそうだったけれど、何とか抑えることができた。
「星奈ちゃん、急にいなくなったじゃない? 心配したのよ」
突然なその話題に体をビクッ、と震わせる。
軽々と『心配した』だなんてどうして言えるのだろう。そんなに心がこもっていない言葉は初めて聞いた。
「だから、また元気な顔を見れて安心したわ」
「元気じゃ、ない、です」
「えっ? でも……」
「全然、元気なんかじゃありません。元気だと言われるように、振る舞っているだけです」
人に機嫌を伺われないように。もう二度と “両親がいなくなって可哀想” なんて言われないように。
私はずっと自分の心を押し殺して頑張ってきたんだ。
「星奈ちゃんは、あの頃からずっと変わってしまったのね」
「あの頃、って……?」
「星奈ちゃんがまだ、幼かった頃。無邪気で、明るくて、ほんと元気の塊って感じの子だったのよ。それがもう高校生にまでなっちゃって、すっかり変わっちゃったのね」
違う。違う、変わったのは私じゃない。変わったのは私の運命だ。私は昔のまま、ずっと変わっていない。
両親がいない世界を生きなければならなくなった、運命が変わってしまったんだ――。
「あのさ、星奈ちゃん。一つ聞きたいんだけどいい?」
「……はい。何ですか」
「星奈ちゃんはあの日、どうして急にいなくなってしまったの?」
不安で不安でたまらない。正直、上手く本音を話せる自信がない。
でもきっと、スグルが私のことを応援してくれている。だから大丈夫だ。
呼吸を整えてから、私は口を開いた。
「聞いちゃったんです。叔母さんと旦那さんが、私のことを “可哀想” だと言っていたのを」
そう言うと、叔母さんは目を丸くして驚いていた。
それでも私の話を真剣に聞いてくれている。
「転校する前も、叔母さんたちにも、戻ったあとも可哀想だと言われ続けました。両親がいない私は、普通じゃない、変わっているんだって。そう思い始めるようになりました」
みんなは両親がいて、私は両親がいなくなった。
みんな違ってみんないい、という言葉はあるけれど、これには絶対に通用しない。だから私は変わり者なんだと思い始めたんだ。
「すごく辛くて、悲しくて、寂しくて。私だって普通の人間なのに……っ。どうしてお母さんもお父さんもいなくなっちゃったんだって。今思うと、中学生で一人暮らししてたなんて異常ですよね。ほんと、当時はそんなの考えないくらい “可哀想” が辛くて」
話し始めたら、ずっと止まらなかった。
本音を伝えているうちに、自分はこんなことを思っていたのか、なんて新たな発見もあった。
「私はそれ以来、人間不信になって。また裏切られるのが怖くて――」
「落ち着いて、星奈ちゃん」
はぁ、はぁ、と息が荒くなっていく私の背中を、叔母さんが擦ってくれた。
――あぁ。温もりのある、叔母さんの手だ。小さい頃、危ないからといって手を繋いでくれたこともあったっけ。
……私、どうしていままで、叔母さんのことを考えずにいたのだろう。
「叔母さんは、私のこと可哀想だって思ってるんですよね? みんなとは違う、変わっている私のことを……っ」
「思ってないよ、星奈ちゃん」
涙が零れ落ちながら、私は叔母さんの表情を見た。
確かに嘘は吐いていなそうな、真っ直ぐな瞳だ。私のことを真剣に考えてくれているのが分かる。
「で、でも、可哀想って……」
「星奈ちゃんのこともあるけど、星奈ちゃんのお母さん――仁美の気持ちも考えたの。二人のことを考えると、やっぱりすごく辛いだろうなって。私が星奈ちゃんだったら、ほんとに立ち直れないから」
叔母さんは――私のことを変わり者だと思って、侮辱した意味で “可哀想” と言ったのかと思った。
でも本当は、私がどれだけ辛い思いをしているか考えてくれていた。そういうこと……?
「ごめんなさい、星奈ちゃん。私のせいでこんなに辛い思いを抱えさせてしまって」
「……ううん。私のほうこそ、勝手に出ていっちゃってごめんなさい。叔母さんは私が小さい頃から優しくて、すごく――大好きだから。私のことを考えてくれていたなんて知らなかった……っ!」
叔母さんの “可哀想” という言葉は、私への愛情で溢れていた。それを私は、ただ勘違いしていただけなんだ。
こんなに泣いたのは両親が亡くなってから初めてだろう。私は何粒もの涙を零しながら、叔母さんの腕の中で抱きしめられていた。