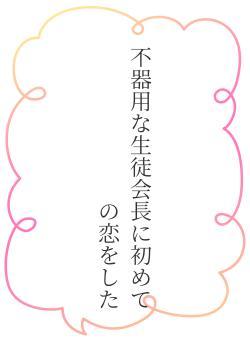「ね、お願いだよ星奈ちゃん!」
「だから、無理って言ってるでしょ。一軒家だけど狭いし……男女が一つ屋根の下ってまずいと思うし」
あれから数時間、スグルから私の家に泊めてほしいと頼まれている。まぁ断り続けているものの、しつこいのはとても苦手だ。
生活費も二人分になってしまうし、男の子と一緒に住むなんて絶対に無理だから。
「じゃあこうする! 俺、家事一生懸命手伝うよ。食事も一日一食でいい。ね、だからお願いだよ星奈ちゃん……!」
両手を組んで目を光らせて、私のことを見つめてきた。うっ、この雰囲気、断っちゃいけない気がする……。
はぁ、とわざとらしいため息を吐いて、私は口を開いた。
「……絶対、だからね。私の言うことはちゃんと聞いてね。何かしたら承知しないから」
「えっ、てことは住んでもいいの?」
「だから、そう言ってるでしょ」
この人本当に星なんだろうか……と疑ってしまうんだけど。
けれど少しだけ、私もホッとする。中学校では一人ぼっちだったし、家に帰っても一人。そんな生活をずっとしてきたから、正直寂しい思いをしていた。
スグルといれば、嫌なことは忘れることができる……。
「早速、何すればいい!?」
「いいよ今日は、適当に座ってて」
リビングにある椅子に腰を下ろして、スグルは家中をキョロキョロと見渡している。
私は食パンとハムやトマトなどを皿に取り分けて、持っていく。
やはり二人分だと用意するのが大変だ。
「はい、こんなのしかないけど」
「これ、なに?」
「それはハム、こっちがトマト。パンに挟んで食べると美味しいから」
星なのに、人間が食べるものは知らないのだろうか。私の星のイメージだと、何でも知ってる神様みたいなものかと思ってたんだけど。
「いただきまーす」と言いながらスグルはパンを口に運んでいる。それが見ていて可愛らしかった。
「美味しいね、食べ物って!」
「食べたことないの?」
「うん、お星さまは食べなくても生きていけるからね」
ふーん、と思いながら頬杖をついてスグルの食べっぷりを見た。やっぱり家に一人じゃないというのは、心強く感じる。
スグルが一緒に住んでくれることになって良かったかも、なんて思った。
「あれ、何で星奈ちゃん、微笑んでるの?」
「えっ、私笑ってた?」
「うん、笑ってるというか……安心して笑みがこぼれる、みたいな感じ」
たぶん、スグルは正しい答えを言った。私、本当は一人で心細かったんだ。けれどスグルが来てくれて安心した……んだと思う。
星も嫌いではない、むしろ好きな方だから、スグルという星に出会えて嬉しい、なんて思ってしまう。
「ねぇ、スグル」
「どうしたの、星奈ちゃん?」
「……私のこと助けてくれるんだよね?」
スグルは真っ直ぐな瞳で、真剣に「もちろん」と答えた。
じゃあ言うしかない――私は深く呼吸をし、口を開いた。
本当は思い出すのが怖いけど、きっとスグルなら私のことを信じてくれるから。
私は中学一年生になってすぐ、両親を事故で亡くした。
一人っ子で大切に育てられてきた私は、現実を受け入れられなくて、しばらくは不登校だった。
半年経って学校に行ったとき、その事件は起きた。
私の机の中は荒らされていて、ノートや教科書には落書きがされていた。
なかでも一番傷ついたのは、『親がいなくなったなんて可哀想』という言葉だ。
親がいない私は普通じゃないんだ。可哀想な人なんだ。そう思い始めるようになった。
また不登校になって半年後、中学二年生になって転校した。お母さんの妹が私を引き取ってくれたから。
「星奈ちゃんを助けるからね」。その言葉を信じて、私は叔母さんと暮らすことにした。
だけど数日後、叔母さんとその旦那さんが話していることをこっそり聞いてしまった。
「星奈ちゃん、子供なのに両親を亡くして……可哀想だわ」という言葉を。
悪気がなかったのは分かっている。でも可哀想という言葉は、他人とは違うことを意味しているのだから、それが苦しかった。
翌日、転校先の学校で友達にも言われた。「綾川さんって親いないんだ……可哀想だね」ということを。
やっぱり私は普通じゃないんだ、とまた心を苦しめられた。
私は勝手に叔母さんの家を出て行き、また両親と住んでいた家に戻ってきた。両親はもともとお金持ちなほうだから、金銭問題は困らなかった。
でも家に帰ると、両親がいないという現実を突きつけられて一人孤独な気持ちになっていた。
それ以来、『助ける』『可哀想』という言葉に恐怖を抱くようになったと共に、人を信じることができなくなった――。
話し終えると、何やらスグルは下を向いて目の辺りを手で擦っている。
嫌な予感がしてスグルの顔を覗き込むと、やはり涙を流していた。
「ちょっと泣かないでよね。私が困るんだから」
「そ、そうだよね……ごめん、俺何も知らないのに助けるとか言っちゃって」
……やっぱり、何か憎めないのが物凄く悔しい。
スグルが私のことを懸命に考えてくれているのだと分かるから。そのことが何よりも嬉しい。
そう思うのはどうしてだろうか。
「星奈ちゃん辛かったよね。一人で頑張れたのすごいよ」
「……頑張ってなんか……っ」
スグルは優しくあたたかい手で、私の頭をポンポンと撫でてくれた。
途端に目頭が熱くなって、服に涙がこぼれ落ちる。
――私、泣いてる?
「頑張ったよ、ううん頑張ってるよ。星奈ちゃん、これからは俺が助けるから。星奈ちゃんはもっと自分に自信を持って!」
……あぁ私、頑張ってるんだろうなって思う。スグルの一言で何粒もの涙を流してしまうなんて、相当頑張っているという証拠だもん。
スグルならきっと、私のことを助けてくれる。出会って一日目なのに、そう確信できる。
「……ありがと、お星さま」
「わぁ、初めて星奈ちゃんにそんなふうに呼んでもらえた!」
出会ったときはただ失礼で変わってる人だと思っていたけれど、いまはそう思わない。
本当は優しくて、あたたかくて、眩しい笑顔を持っている人なんだ。
「じゃあ俺は、星奈ちゃんの人間嫌いを克服できるように手伝えばいいかな?」
「……うん」
「分かった! じゃあ改めて約束するよ。絶対に星奈ちゃんを助けてみせるから」
スグルは私に手を差し伸べて、そう言ってくれた。……こういうときだけ男の子になるの、やめてほしいんだけど。
胸の鼓動が早くなっているのは、どうしてだろうか。
「じゃあスグルはソファで寝てね」
「うん、分かった! 別に俺は星奈ちゃんの隣で寝てもいいからねー?」
「……次言ったら追い出すよ」
「ごめんなさい」
全くもう、と思いながらソファに横になったスグルに、布団を掛けてあげる。
こういうやり取りを異性としたことがなかったから、何だか楽しくなる。
「星奈ちゃん、俺、料理とか家事やったことないけど頑張るから。迷惑かけるかもしれないけど」
「……うん。私も、教えるから」
「えっ? いいの!?」
「だって私の家だし。散らかったら困るでしょ」
「やったぁ! やっぱり星奈ちゃんって優しいよね」
優しい――そんなこと、両親に言われて以来、一度も言われたことがなかった。
『星奈は優しい子に育って良かった』とお母さんに言われたときはとてつもなく嬉しかった。
……今も、スグルにそう言われて嬉しいと思ってしまった。
「はいはい、ありがとう、褒めるのがお上手ね。じゃあおやすみ、スグル」
「えぇー本当なのになぁ。おやすみなさい星奈ちゃん」
スグルは頬を膨らましている。私は電気を消し、自分のベッドに戻った。
やっぱり異性と一緒の家に住むなんて緊張してしまうけれど、スグルなら大丈夫だろう。……何かしてきたら、すぐ追い出すし。
明日は良い一日が待っていますように。そう心のなかで言って、眠りについた。
「だから、無理って言ってるでしょ。一軒家だけど狭いし……男女が一つ屋根の下ってまずいと思うし」
あれから数時間、スグルから私の家に泊めてほしいと頼まれている。まぁ断り続けているものの、しつこいのはとても苦手だ。
生活費も二人分になってしまうし、男の子と一緒に住むなんて絶対に無理だから。
「じゃあこうする! 俺、家事一生懸命手伝うよ。食事も一日一食でいい。ね、だからお願いだよ星奈ちゃん……!」
両手を組んで目を光らせて、私のことを見つめてきた。うっ、この雰囲気、断っちゃいけない気がする……。
はぁ、とわざとらしいため息を吐いて、私は口を開いた。
「……絶対、だからね。私の言うことはちゃんと聞いてね。何かしたら承知しないから」
「えっ、てことは住んでもいいの?」
「だから、そう言ってるでしょ」
この人本当に星なんだろうか……と疑ってしまうんだけど。
けれど少しだけ、私もホッとする。中学校では一人ぼっちだったし、家に帰っても一人。そんな生活をずっとしてきたから、正直寂しい思いをしていた。
スグルといれば、嫌なことは忘れることができる……。
「早速、何すればいい!?」
「いいよ今日は、適当に座ってて」
リビングにある椅子に腰を下ろして、スグルは家中をキョロキョロと見渡している。
私は食パンとハムやトマトなどを皿に取り分けて、持っていく。
やはり二人分だと用意するのが大変だ。
「はい、こんなのしかないけど」
「これ、なに?」
「それはハム、こっちがトマト。パンに挟んで食べると美味しいから」
星なのに、人間が食べるものは知らないのだろうか。私の星のイメージだと、何でも知ってる神様みたいなものかと思ってたんだけど。
「いただきまーす」と言いながらスグルはパンを口に運んでいる。それが見ていて可愛らしかった。
「美味しいね、食べ物って!」
「食べたことないの?」
「うん、お星さまは食べなくても生きていけるからね」
ふーん、と思いながら頬杖をついてスグルの食べっぷりを見た。やっぱり家に一人じゃないというのは、心強く感じる。
スグルが一緒に住んでくれることになって良かったかも、なんて思った。
「あれ、何で星奈ちゃん、微笑んでるの?」
「えっ、私笑ってた?」
「うん、笑ってるというか……安心して笑みがこぼれる、みたいな感じ」
たぶん、スグルは正しい答えを言った。私、本当は一人で心細かったんだ。けれどスグルが来てくれて安心した……んだと思う。
星も嫌いではない、むしろ好きな方だから、スグルという星に出会えて嬉しい、なんて思ってしまう。
「ねぇ、スグル」
「どうしたの、星奈ちゃん?」
「……私のこと助けてくれるんだよね?」
スグルは真っ直ぐな瞳で、真剣に「もちろん」と答えた。
じゃあ言うしかない――私は深く呼吸をし、口を開いた。
本当は思い出すのが怖いけど、きっとスグルなら私のことを信じてくれるから。
私は中学一年生になってすぐ、両親を事故で亡くした。
一人っ子で大切に育てられてきた私は、現実を受け入れられなくて、しばらくは不登校だった。
半年経って学校に行ったとき、その事件は起きた。
私の机の中は荒らされていて、ノートや教科書には落書きがされていた。
なかでも一番傷ついたのは、『親がいなくなったなんて可哀想』という言葉だ。
親がいない私は普通じゃないんだ。可哀想な人なんだ。そう思い始めるようになった。
また不登校になって半年後、中学二年生になって転校した。お母さんの妹が私を引き取ってくれたから。
「星奈ちゃんを助けるからね」。その言葉を信じて、私は叔母さんと暮らすことにした。
だけど数日後、叔母さんとその旦那さんが話していることをこっそり聞いてしまった。
「星奈ちゃん、子供なのに両親を亡くして……可哀想だわ」という言葉を。
悪気がなかったのは分かっている。でも可哀想という言葉は、他人とは違うことを意味しているのだから、それが苦しかった。
翌日、転校先の学校で友達にも言われた。「綾川さんって親いないんだ……可哀想だね」ということを。
やっぱり私は普通じゃないんだ、とまた心を苦しめられた。
私は勝手に叔母さんの家を出て行き、また両親と住んでいた家に戻ってきた。両親はもともとお金持ちなほうだから、金銭問題は困らなかった。
でも家に帰ると、両親がいないという現実を突きつけられて一人孤独な気持ちになっていた。
それ以来、『助ける』『可哀想』という言葉に恐怖を抱くようになったと共に、人を信じることができなくなった――。
話し終えると、何やらスグルは下を向いて目の辺りを手で擦っている。
嫌な予感がしてスグルの顔を覗き込むと、やはり涙を流していた。
「ちょっと泣かないでよね。私が困るんだから」
「そ、そうだよね……ごめん、俺何も知らないのに助けるとか言っちゃって」
……やっぱり、何か憎めないのが物凄く悔しい。
スグルが私のことを懸命に考えてくれているのだと分かるから。そのことが何よりも嬉しい。
そう思うのはどうしてだろうか。
「星奈ちゃん辛かったよね。一人で頑張れたのすごいよ」
「……頑張ってなんか……っ」
スグルは優しくあたたかい手で、私の頭をポンポンと撫でてくれた。
途端に目頭が熱くなって、服に涙がこぼれ落ちる。
――私、泣いてる?
「頑張ったよ、ううん頑張ってるよ。星奈ちゃん、これからは俺が助けるから。星奈ちゃんはもっと自分に自信を持って!」
……あぁ私、頑張ってるんだろうなって思う。スグルの一言で何粒もの涙を流してしまうなんて、相当頑張っているという証拠だもん。
スグルならきっと、私のことを助けてくれる。出会って一日目なのに、そう確信できる。
「……ありがと、お星さま」
「わぁ、初めて星奈ちゃんにそんなふうに呼んでもらえた!」
出会ったときはただ失礼で変わってる人だと思っていたけれど、いまはそう思わない。
本当は優しくて、あたたかくて、眩しい笑顔を持っている人なんだ。
「じゃあ俺は、星奈ちゃんの人間嫌いを克服できるように手伝えばいいかな?」
「……うん」
「分かった! じゃあ改めて約束するよ。絶対に星奈ちゃんを助けてみせるから」
スグルは私に手を差し伸べて、そう言ってくれた。……こういうときだけ男の子になるの、やめてほしいんだけど。
胸の鼓動が早くなっているのは、どうしてだろうか。
「じゃあスグルはソファで寝てね」
「うん、分かった! 別に俺は星奈ちゃんの隣で寝てもいいからねー?」
「……次言ったら追い出すよ」
「ごめんなさい」
全くもう、と思いながらソファに横になったスグルに、布団を掛けてあげる。
こういうやり取りを異性としたことがなかったから、何だか楽しくなる。
「星奈ちゃん、俺、料理とか家事やったことないけど頑張るから。迷惑かけるかもしれないけど」
「……うん。私も、教えるから」
「えっ? いいの!?」
「だって私の家だし。散らかったら困るでしょ」
「やったぁ! やっぱり星奈ちゃんって優しいよね」
優しい――そんなこと、両親に言われて以来、一度も言われたことがなかった。
『星奈は優しい子に育って良かった』とお母さんに言われたときはとてつもなく嬉しかった。
……今も、スグルにそう言われて嬉しいと思ってしまった。
「はいはい、ありがとう、褒めるのがお上手ね。じゃあおやすみ、スグル」
「えぇー本当なのになぁ。おやすみなさい星奈ちゃん」
スグルは頬を膨らましている。私は電気を消し、自分のベッドに戻った。
やっぱり異性と一緒の家に住むなんて緊張してしまうけれど、スグルなら大丈夫だろう。……何かしてきたら、すぐ追い出すし。
明日は良い一日が待っていますように。そう心のなかで言って、眠りについた。