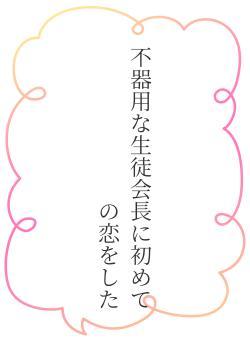「私……スグルに、甘えてたの」
スグルが来てからまだ数ヶ月しか経っていないけれど、思い出は数え切れないほどある。
私は叔母さんや遥花ちゃん、優衣ちゃんに本音を伝えるとき……スグルが傍にいてくれたから勇気が出た。
思い返すと、自分一人の力じゃなかった。スグルのおかげで伝えることができたんだ。
「スグルがいなくなってから気がついた。私は一人じゃ何もできないんだなって。スグルがいなかったらきっと……前の私のままだった。一歩踏み出せない、人間不信の私」
「うん。でも俺は、星奈ちゃんの人間不信を直すこと、助けることが責務だったから。それを克服てきただけですごいと思うけどな!」
「……それだけじゃ、だめなんだよ。一人で頑張れるようにしないと。でも、スグルがいないと私は一人じゃ何もできないの」
そう言っても、スグルは笑顔を浮かべたままだった。
――なんで笑顔でいられるの? そんな笑顔を向けられたら何も言えなくなっちゃうよ。
「教えて。スグルは、十年前の事件の、関沢優流さんなの?」
「それは……」
「私、考えてみたの。どうしてスグルは星だったんだろうって。どうして私のことを助けに来てくれたんだろうって。――もしかしたら、スグルは星になる前は人間で、私と同じような辛い経験をしたからなんじゃない?」
スグルは私の話を黙って聞いていたけれど、少しだけ動揺しているのが分かる。
たぶん、私の推理は的中した。後はスグルが、本当のことを話してくれるのを待つだけ。
「星奈ちゃんは、ほんとにすごいね。そうだよ、俺は関沢優流。十年前、高校一年生だったときに自殺したんだ」
分かってはいたものの、いざ本人を目の前にすると少しだけ怖いと思ってしまう。スグルの事実を知ることが。
でもスグルは私の気持ちをたくさん聞いてくれた。だから今度は、私がスグルの気持ちを聞く番なんだ。
「どうして、自殺なんかしたの?」
「……星奈ちゃんと一緒だよ。両親が事故で亡くなって、母さんの叔母さんに引き取られて。でもそこでは暴力を振られたり、暴言を吐かれたりした。叔母さんは昔から俺のことが気に入らなかったらしいからね。理由は分からないけど」
それを想像しただけで、とてつもなく胸が苦しくなった。
私はただ『可哀想』だと思われていただけ。でもスグルは実際に危害を加えられて……私よりもきっと辛い思いをしていた。
「でも誰にも言えなかった。言ったら、それがどんどんエスカレートしそうで怖かった。限界を迎えた俺は台所にあるナイフを使って――自殺した。小さい頃から両親には料理を教わってたからナイフの使い方とかは知ってたんだ」
そっか。だから私と暮らしていたとき、勝手に料理を作っていたんだ。ナイフには慣れているから――。
そのことを知って、すごく悔しくなった。もっと早く気づいてあげられたかもしれないから。
「俺……辛かったんだ。両親が亡くなったのは小一の頃だった。もっと甘えたかった。もっと話したかった。その幸せが全部、全部……叔母さんたちのせいで消え失せた。俺は――気がついたら、星になっていた」
私は両親が亡くなってすごく辛かったけれど、一人で生きてこられた。死にたい、と思うことは確かになかった。
でもスグルはそう思って、実践した。私よりも遥かに辛かったのだろう。
「星になって何年経ったか分からないある日、神様に告げられた。“あの子のことを助けてやりなさい” って。それが星奈ちゃんだった」
『星奈ちゃんを助けるために人間の世界に来たんだ』。最初に出会ったとき、言っていたこと。神様に告げられて私を助けるためここに来たんだ――。
「星奈ちゃんは初めて会ったとき、すごく冷たかったよね。構わないでーとか強がってたし」
「だ、だって、私はあのとき誰とも関わりたくないって思ってたし。怖かったんだよ、スグルでも」
「……そうだよね。俺、一目見たときから分かってたんだ。星奈ちゃんは俺と同じだって。だから絶対に助けたいって心から思ったんだ」
そのおかげで、私はスグルに助けられた。人を信じることがまたできるようになった。
……なのに。どうしてスグルは消えてしまったのだろうか。何も言わずに消えちゃうなんて、こんなに悲しいことはない。
「それなのにどうして、あの日突然、スグルは消えちゃったの?」
「……俺も分からない。もともと、俺が星から人間になって来た理由は、星奈ちゃんを助けるためだ。でも星奈ちゃんは、叔母さんたちに本音を伝えられて、もう人間不信を克服できたでしょ? じゃあもう助けたってことなんだよ」
そう言われて、私は花火が散ったように顔が熱くなる。
私、スグルから鈍感だって言われて悔しかった。鈍感なんかじゃない、とも思っていた。
スグルは分かってない。私はまだ気持ちを伝えるべき相手が一人いる。
――鈍感なのはスグルの方だよ。
「私はまだ、気持ちを伝えられてない人がいるよ」
「えっ、でも、叔母さんと遥花ちゃんたちに伝えられたんでしょ? じゃあ他には――」
「スグルのバカ! なんで分からないの!? だって私はまだスグルに……っ」
「……俺?」
この気持ちを伝えてしまえば、スグルはきっと星へ帰ってしまう。そんなの絶対に嫌だ。
だったらまだ『好き』だと伝えないほうがいい。この恋は報われなくても構わない。どうでもいい。
だけどスグルともう会えなくなってしまうのは嫌だ。だから……言えない。
「星奈ちゃん、教えて。俺に伝えたいことってなに?」
「嫌だよ、言ったらきっとスグルは消えちゃう。もうあの苦しみは味わいたくない。消えてほしくない。だから絶対に言わない……!」
泣きじゃくる子供のようにそう言うと、スグルは頭をぽんぽんと優しく撫でたあとに、私を腕に抱き寄せた。
――えっ? 私いま、スグルの腕の中にいる……?
「俺はもうこの世にはいないんだよ。消える運命だったんだ。でも神様の気まぐれで、俺は星になることができた。……ここにはきっといてはいけない。だから帰る前に、星奈ちゃんの気持ちを聞かせて。お願い」
――ずるい。スグルは本当に、ずるい人だ。
私は止まらない涙を流し続けたまま、もう一度口を開いた。
「――好き。バカで、無邪気で、小さい子供みたいにいつもはしゃいでて。でもたまに男らしくて、たくましくて、すごく優しくて。私は……スグルのことが、大好き、なの」
息をするのも忘れて、私はスグルに本音を伝えた。
するとスグルは、私のことを先程よりも強く抱きしめてくれた。スグルの手が震えているのが分かる。
――なんでだろう。
「……星奈ちゃんは、やっぱり正直だね」
「私も、言ったんだから……スグルも、思ってること、言ってよ」
スグルの返事が聞きたい。返事を聞くのは怖くて胸がいっぱいになるけれど、いま聞かないともう聞くことはできないと思うから。
私の頬に、光る雫が零れ落ちた。それは私の涙じゃなくて、スグルが流していた涙だった。
「俺も――星奈ちゃんが好きだよ。星奈ちゃんのことをいつの間にか好きになってた」
「……スグル……っ!」
スグルも、私に好意を寄せてくれていた。好きだと想ってくれていた。
ねぇ神様、お星さま。なんで私たちがこんな運命にならなきゃいけないの? なんで私たちは二人一緒に幸せになれないの?
星なんて無数にある。人間なんて数え切れないほど生きている。それなのにどうして――私たちが選ばれちゃったの?
「せっかく、スグルの気持ちを知ることができたのに。やっと両思いになれたのに。どうして私たちは結ばれないの……? ねぇスグル、辛いよ……っ」
「……うん、俺も。でも神様は気まぐれなんだ。だから俺たちが選ばれちゃったのは仕方ないことなんだよ。これが運命なんだ」
――どうして。どうしてスグルは仕方ないなんて思えるの?
私はそんなこと思えない。ただただ目の前にある現実しか見れなくて、すごく悲しくて、辛い。
スグルと会えなくなるなんて、そんなの想像もしたくない。
「そろそろ、時間みたいだ」
はっ、としてスグルを見ると、全身が光のオーラに囲まれていた。前にもここで光っていたけれど、それよりも遥かに光っている。
……本当に、もうお別れなんだ。スグルと話せなくなるし、もう絶対に会うことはできない。
私はスグルのことを抱きしめながら、服をぎゅっと掴んだ。
「いかないで……スグルお願い、いかないで。スグルと話せなくなるなんてそんなの無理だよ」
「あはは、星奈ちゃんもそういう可愛いこと言えるんだね。初めてじゃない?」
「スグルにもっと、甘えたいもん……」
手を繋いだり、手を振ったり、デートしたり、抱きしめあったり。そんな普通のカップルのようなことを、してみたかった。
スグルと――もっともっと一緒にやりたいことはたくさんある。それが絶対に叶わないなんて、あまりにも虚しい。
「ねぇ星奈ちゃん、上を見てみて」
「……上?」
言われるがまま上を向くと、流星群が見えた。夜空に浮かぶ星の大群は、やはりとても美しい。
初めてスグルとここの海に来て同じように流星群を見た、あの日をとても懐かしく思う。
「……とても、綺麗だね」
「でも星奈ちゃんはあの星たちよりも輝いてるよ。すごく可愛くて、美しい」
「それは言いすぎじゃない? 誰が見たって、私よりも星のほうが美しいでしょ」
「他の人はどうでもいいよ。俺がそう思ってればいーの! 星奈ちゃんのことは世界一、いや銀河一大好きだから!」
――あぁ。私、その言葉があればきっと生きていくことができる。
それにスグルが消えても……私の心のなかで、スグルは生き続けているから。
「星奈ちゃん。俺と出会ってくれて、ありがとう」
「……私のほうこそ。私を助けてくれたのがスグルで本当に良かった。スグルという星を……必ず、見つけてみせるから」
「あはは、なら待ってるね! 見つけてもらうのを!」
もう目を閉じてしまうくらい、スグルの光のオーラが眩しくなってきた。
――そろそろ、別れが近づいてきている。
「スグル、大好きだよ。お星さまになっても私のことちゃんと見ててね!」
「俺も大好き。星奈ちゃんこそ、そこから俺のことちゃんと見ててね! 約束――」
私たちが差し出した小指は触れ合うことなく、スグルは消えていった。ううん、あの夜空に輝く場所へ帰っていったんだ。
「スグル……っ!!」
スグルと出会って過ごしていた日々が嘘のように、ポツンと無くなってしまった。
海に名前を叫ぶと、物凄く涙が込み上げてきた。とても辛くて悲しくて、現実が信じられない。
夜空を見上げると、まだたくさんの星が浮かんでいた。幻想的で、とても美しい。
――スグルは、この星空よりも私のほうが輝いてると言った。さすがに大袈裟だなぁ。
とは思ったものの、やはり嬉しかった。スグルのあの言葉は、私の心のなかにはずっと残り続けている。
「ありがとう、スグル。見ててね」
――見てくれてると、信じてるからね。
お星さまへの願いごとを心のなかで唱えて、私は孤独で寂しい帰り道を一歩ずつ歩き出した。
スグルが来てからまだ数ヶ月しか経っていないけれど、思い出は数え切れないほどある。
私は叔母さんや遥花ちゃん、優衣ちゃんに本音を伝えるとき……スグルが傍にいてくれたから勇気が出た。
思い返すと、自分一人の力じゃなかった。スグルのおかげで伝えることができたんだ。
「スグルがいなくなってから気がついた。私は一人じゃ何もできないんだなって。スグルがいなかったらきっと……前の私のままだった。一歩踏み出せない、人間不信の私」
「うん。でも俺は、星奈ちゃんの人間不信を直すこと、助けることが責務だったから。それを克服てきただけですごいと思うけどな!」
「……それだけじゃ、だめなんだよ。一人で頑張れるようにしないと。でも、スグルがいないと私は一人じゃ何もできないの」
そう言っても、スグルは笑顔を浮かべたままだった。
――なんで笑顔でいられるの? そんな笑顔を向けられたら何も言えなくなっちゃうよ。
「教えて。スグルは、十年前の事件の、関沢優流さんなの?」
「それは……」
「私、考えてみたの。どうしてスグルは星だったんだろうって。どうして私のことを助けに来てくれたんだろうって。――もしかしたら、スグルは星になる前は人間で、私と同じような辛い経験をしたからなんじゃない?」
スグルは私の話を黙って聞いていたけれど、少しだけ動揺しているのが分かる。
たぶん、私の推理は的中した。後はスグルが、本当のことを話してくれるのを待つだけ。
「星奈ちゃんは、ほんとにすごいね。そうだよ、俺は関沢優流。十年前、高校一年生だったときに自殺したんだ」
分かってはいたものの、いざ本人を目の前にすると少しだけ怖いと思ってしまう。スグルの事実を知ることが。
でもスグルは私の気持ちをたくさん聞いてくれた。だから今度は、私がスグルの気持ちを聞く番なんだ。
「どうして、自殺なんかしたの?」
「……星奈ちゃんと一緒だよ。両親が事故で亡くなって、母さんの叔母さんに引き取られて。でもそこでは暴力を振られたり、暴言を吐かれたりした。叔母さんは昔から俺のことが気に入らなかったらしいからね。理由は分からないけど」
それを想像しただけで、とてつもなく胸が苦しくなった。
私はただ『可哀想』だと思われていただけ。でもスグルは実際に危害を加えられて……私よりもきっと辛い思いをしていた。
「でも誰にも言えなかった。言ったら、それがどんどんエスカレートしそうで怖かった。限界を迎えた俺は台所にあるナイフを使って――自殺した。小さい頃から両親には料理を教わってたからナイフの使い方とかは知ってたんだ」
そっか。だから私と暮らしていたとき、勝手に料理を作っていたんだ。ナイフには慣れているから――。
そのことを知って、すごく悔しくなった。もっと早く気づいてあげられたかもしれないから。
「俺……辛かったんだ。両親が亡くなったのは小一の頃だった。もっと甘えたかった。もっと話したかった。その幸せが全部、全部……叔母さんたちのせいで消え失せた。俺は――気がついたら、星になっていた」
私は両親が亡くなってすごく辛かったけれど、一人で生きてこられた。死にたい、と思うことは確かになかった。
でもスグルはそう思って、実践した。私よりも遥かに辛かったのだろう。
「星になって何年経ったか分からないある日、神様に告げられた。“あの子のことを助けてやりなさい” って。それが星奈ちゃんだった」
『星奈ちゃんを助けるために人間の世界に来たんだ』。最初に出会ったとき、言っていたこと。神様に告げられて私を助けるためここに来たんだ――。
「星奈ちゃんは初めて会ったとき、すごく冷たかったよね。構わないでーとか強がってたし」
「だ、だって、私はあのとき誰とも関わりたくないって思ってたし。怖かったんだよ、スグルでも」
「……そうだよね。俺、一目見たときから分かってたんだ。星奈ちゃんは俺と同じだって。だから絶対に助けたいって心から思ったんだ」
そのおかげで、私はスグルに助けられた。人を信じることがまたできるようになった。
……なのに。どうしてスグルは消えてしまったのだろうか。何も言わずに消えちゃうなんて、こんなに悲しいことはない。
「それなのにどうして、あの日突然、スグルは消えちゃったの?」
「……俺も分からない。もともと、俺が星から人間になって来た理由は、星奈ちゃんを助けるためだ。でも星奈ちゃんは、叔母さんたちに本音を伝えられて、もう人間不信を克服できたでしょ? じゃあもう助けたってことなんだよ」
そう言われて、私は花火が散ったように顔が熱くなる。
私、スグルから鈍感だって言われて悔しかった。鈍感なんかじゃない、とも思っていた。
スグルは分かってない。私はまだ気持ちを伝えるべき相手が一人いる。
――鈍感なのはスグルの方だよ。
「私はまだ、気持ちを伝えられてない人がいるよ」
「えっ、でも、叔母さんと遥花ちゃんたちに伝えられたんでしょ? じゃあ他には――」
「スグルのバカ! なんで分からないの!? だって私はまだスグルに……っ」
「……俺?」
この気持ちを伝えてしまえば、スグルはきっと星へ帰ってしまう。そんなの絶対に嫌だ。
だったらまだ『好き』だと伝えないほうがいい。この恋は報われなくても構わない。どうでもいい。
だけどスグルともう会えなくなってしまうのは嫌だ。だから……言えない。
「星奈ちゃん、教えて。俺に伝えたいことってなに?」
「嫌だよ、言ったらきっとスグルは消えちゃう。もうあの苦しみは味わいたくない。消えてほしくない。だから絶対に言わない……!」
泣きじゃくる子供のようにそう言うと、スグルは頭をぽんぽんと優しく撫でたあとに、私を腕に抱き寄せた。
――えっ? 私いま、スグルの腕の中にいる……?
「俺はもうこの世にはいないんだよ。消える運命だったんだ。でも神様の気まぐれで、俺は星になることができた。……ここにはきっといてはいけない。だから帰る前に、星奈ちゃんの気持ちを聞かせて。お願い」
――ずるい。スグルは本当に、ずるい人だ。
私は止まらない涙を流し続けたまま、もう一度口を開いた。
「――好き。バカで、無邪気で、小さい子供みたいにいつもはしゃいでて。でもたまに男らしくて、たくましくて、すごく優しくて。私は……スグルのことが、大好き、なの」
息をするのも忘れて、私はスグルに本音を伝えた。
するとスグルは、私のことを先程よりも強く抱きしめてくれた。スグルの手が震えているのが分かる。
――なんでだろう。
「……星奈ちゃんは、やっぱり正直だね」
「私も、言ったんだから……スグルも、思ってること、言ってよ」
スグルの返事が聞きたい。返事を聞くのは怖くて胸がいっぱいになるけれど、いま聞かないともう聞くことはできないと思うから。
私の頬に、光る雫が零れ落ちた。それは私の涙じゃなくて、スグルが流していた涙だった。
「俺も――星奈ちゃんが好きだよ。星奈ちゃんのことをいつの間にか好きになってた」
「……スグル……っ!」
スグルも、私に好意を寄せてくれていた。好きだと想ってくれていた。
ねぇ神様、お星さま。なんで私たちがこんな運命にならなきゃいけないの? なんで私たちは二人一緒に幸せになれないの?
星なんて無数にある。人間なんて数え切れないほど生きている。それなのにどうして――私たちが選ばれちゃったの?
「せっかく、スグルの気持ちを知ることができたのに。やっと両思いになれたのに。どうして私たちは結ばれないの……? ねぇスグル、辛いよ……っ」
「……うん、俺も。でも神様は気まぐれなんだ。だから俺たちが選ばれちゃったのは仕方ないことなんだよ。これが運命なんだ」
――どうして。どうしてスグルは仕方ないなんて思えるの?
私はそんなこと思えない。ただただ目の前にある現実しか見れなくて、すごく悲しくて、辛い。
スグルと会えなくなるなんて、そんなの想像もしたくない。
「そろそろ、時間みたいだ」
はっ、としてスグルを見ると、全身が光のオーラに囲まれていた。前にもここで光っていたけれど、それよりも遥かに光っている。
……本当に、もうお別れなんだ。スグルと話せなくなるし、もう絶対に会うことはできない。
私はスグルのことを抱きしめながら、服をぎゅっと掴んだ。
「いかないで……スグルお願い、いかないで。スグルと話せなくなるなんてそんなの無理だよ」
「あはは、星奈ちゃんもそういう可愛いこと言えるんだね。初めてじゃない?」
「スグルにもっと、甘えたいもん……」
手を繋いだり、手を振ったり、デートしたり、抱きしめあったり。そんな普通のカップルのようなことを、してみたかった。
スグルと――もっともっと一緒にやりたいことはたくさんある。それが絶対に叶わないなんて、あまりにも虚しい。
「ねぇ星奈ちゃん、上を見てみて」
「……上?」
言われるがまま上を向くと、流星群が見えた。夜空に浮かぶ星の大群は、やはりとても美しい。
初めてスグルとここの海に来て同じように流星群を見た、あの日をとても懐かしく思う。
「……とても、綺麗だね」
「でも星奈ちゃんはあの星たちよりも輝いてるよ。すごく可愛くて、美しい」
「それは言いすぎじゃない? 誰が見たって、私よりも星のほうが美しいでしょ」
「他の人はどうでもいいよ。俺がそう思ってればいーの! 星奈ちゃんのことは世界一、いや銀河一大好きだから!」
――あぁ。私、その言葉があればきっと生きていくことができる。
それにスグルが消えても……私の心のなかで、スグルは生き続けているから。
「星奈ちゃん。俺と出会ってくれて、ありがとう」
「……私のほうこそ。私を助けてくれたのがスグルで本当に良かった。スグルという星を……必ず、見つけてみせるから」
「あはは、なら待ってるね! 見つけてもらうのを!」
もう目を閉じてしまうくらい、スグルの光のオーラが眩しくなってきた。
――そろそろ、別れが近づいてきている。
「スグル、大好きだよ。お星さまになっても私のことちゃんと見ててね!」
「俺も大好き。星奈ちゃんこそ、そこから俺のことちゃんと見ててね! 約束――」
私たちが差し出した小指は触れ合うことなく、スグルは消えていった。ううん、あの夜空に輝く場所へ帰っていったんだ。
「スグル……っ!!」
スグルと出会って過ごしていた日々が嘘のように、ポツンと無くなってしまった。
海に名前を叫ぶと、物凄く涙が込み上げてきた。とても辛くて悲しくて、現実が信じられない。
夜空を見上げると、まだたくさんの星が浮かんでいた。幻想的で、とても美しい。
――スグルは、この星空よりも私のほうが輝いてると言った。さすがに大袈裟だなぁ。
とは思ったものの、やはり嬉しかった。スグルのあの言葉は、私の心のなかにはずっと残り続けている。
「ありがとう、スグル。見ててね」
――見てくれてると、信じてるからね。
お星さまへの願いごとを心のなかで唱えて、私は孤独で寂しい帰り道を一歩ずつ歩き出した。