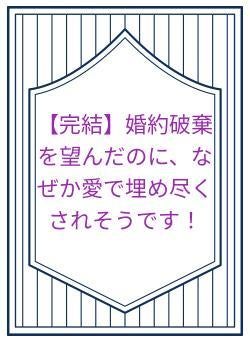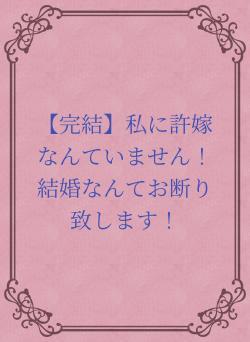「秋文さんって、無愛想だと思ってたけど、本当はちゃんと優しい人なんだよね」
私がそう言うとと、秋文さんは「は?ちゃんとって、なんだよ」と私を見る。
「だってなんか、初めて会った時無愛想で怖かったから」
「無愛想? 俺がか?」
まるでそんなことない、と言うような顔で私を見ている。
「そうだよ。無愛想だった」
「そんなことないと思うけどな」
「え?本気で言ってるの?」
自分ではあれが普通だってこと? まるで自覚がないってこと……?
恐ろしいよ、この人は。
「私のこと、お前って言ってたよ」
「そうだっけ?」
「そうだよ。覚えてないの?」
私はこんなにも覚えてるのに、ひどくない?
「少なくとも、言った記憶はないな」
「……最低」
秋文さん、本当に無愛想だよ。
「私、お前って言われて、あの時結構ショックだったんだよ」
「そうか? 全然覚えてないわ」
「ひどいっ!」
私、絶対に忘れてないのに。
「まあまあ、そんな怒るなよ。 今はちゃんと好きだから、澪奈のこと」
「……もう。都合いいんだから」
私がそう言うと、秋文さんは「澪奈、俺のこと嫌いになった?」と聞いてくる。
「なってないよ、嫌いになんて」
「そうか」
「でもちょっと傷付いた」
秋文さんはそんな私に、「悪かったよ、澪奈」と頭を撫でる。