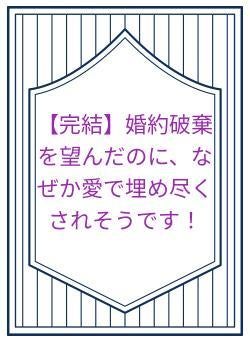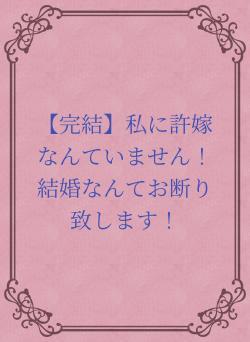「なあ、澪奈」
「ん?」
秋文さんに名前を呼ばれて、秋文さんの方に振り返る。
「いつもごめんな」
「え……?」
秋文さんに謝られた私は、秋文さんから「こうやってデートの時、いつも呼び出されちまうし。 澪奈には、寂しい思い……させてるだろ?」と言われてしまう。
「そんなことないよ。 全然気にしてないし、私」
仕事で忙しいのは、分かっているし。それは仕方のないことだって、分かっている。
「いつも本当、申し訳ないと思ってる」
「……秋文さん、そんなに謝らないで」
私は秋文さんに謝ってほしい訳じゃない。 秋文さんが警察官なのは、よく分かっている。
警察官が忙しい仕事で、そして休みが不定期なのも分かっているから、私は秋文さんに謝ってほしくはない。
「澪奈……好きだよ」
「え?……っ、んっ」
秋文さんの唇が重なると、私は思わず目を閉じていた。
「秋文さん……私も、秋文さんのことが好き」
私は秋文さんのことが、たまらなく好きだ。 愛おしいと思う感情って、人それぞれ違うと思うけど、私は秋文さんのことがたまらなく大好き。
「こんな俺だけど、これからもそばにいてくれるか」
秋文さんにそう言われて、私は「うん」と返事をした。
私は秋文さんが警察官として、働く姿が好き。 でも彼氏として、そばにいてくれる時も好き。