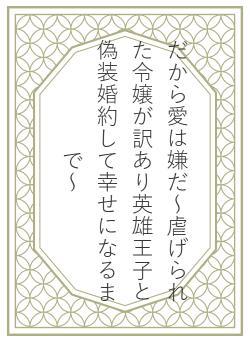あっという間に、ロザリンド様のお茶会の日になりました。
テオドール様が私のドレスやアクセサリーを用意してくださったので、準備は万端です。
お茶会まであまり日数がありませんでしたが、テオドール様のおかげで私はゆっくりと過ごすことができました。
その間に、念のためもう一度、王都でのお茶会のマナーを学び直しましたが、相変わらずいろいろと複雑です。
バルゴア領でのお茶会は、もっと気楽なものなので、王都でも気楽にお茶会を楽しんだらいいのに。
でもここは王都なので、その場所のルールに従うのが正解です。
お茶会は、バルゴア領では癒しの時間でも、王都では戦場なのです。
気を引き締めて参加しないと!
今日のお茶会に向けて改めて気合を入れた私を、ターチェ家のメイドたちが丁寧に磨いてくれます。でも、バルゴア領から一緒に来てくれた私の専属メイドジーナは、ここにはいません。
数日前に、「シンシア様。テオドール様の指示で少しお側を離れます」と言っていたので、別の場所でお仕事をしているのでしょう。ジーナの代わりに、部屋の前にいつもより多くの護衛騎士が控えています。
ターチェ家内で危ないことなんて起こらないと思うんですが……。
念には念をということなのでしょう。
メイドたちのおかげで私の髪はいつも以上にサラサラになり、お肌はツルツル。これならどこに行っても恥ずかしくありません。
メイドたちが「テオドール様からです」とドレスとアクセサリーを部屋に運び入れてくれました。
お茶会までの日にちがあまりなかったこともあり、ドレスを見るのは今が初めてです。
「よかった。間に合ったんですね」
ホッと胸を撫で下ろす私は、届いたドレスに目を奪われました。
そこには、華やかで赤いドレスがあります。赤はテオドール様の瞳の色です。
それだけではありません。胸元から腕部分は、黒いレースで飾られています。
黒はもちろんテオドール様の髪色です。
自分の色を相手に贈ることは、この国では愛情の証です。
恋愛小説でもそういうシーンがよく出てくるので、私も憧れていました。
いつか着たいと思っていた赤いドレスをテオドール様に贈ってもらえるなんて……。
大人っぽい赤いドレスなんて私には似合わないと思っていたのに、そこはさすがのテオドール様。
大人っぽすぎず、かといって子供っぽくもないドレスは、私が着ても違和感がありません。
鏡に映る自分を見て、私はポツリと呟きました。
「なんだか私、テオドール様の婚約者みたい……」
その言葉を聞いたメイドたちは、驚きながら顔を見合わせています。
いや、バルゴア領では婚約者なんですけど、王都ではまだ認められていないから、複雑な立ち位置なのです。
だからこそ、早急に国王陛下に私たちの婚約を認めていただきたいのですが……。
メイドが私にイヤリングとネックレスをつけてくれました。
テオドール様が贈ってくださったアクセサリーについている宝石は、予想外にアメジストでした。煌めく紫色は、私の瞳と同じ色です。
『どうして、紫色?』と思った私の疑問は、テオドール様の登場で解決しました。
黒い衣装を身にまとったテオドール様の首元や手首には、私と同じデザインのブローチやカフスが輝いています。
ようするに、おそろいです。
嬉しくて胸がドキドキしてしまいます。
テオドール様は、ドレスアップした私を見たとたんに、フワッと優しい笑みを浮かべました。
「シンシア様……。とても……とてもお美しいです」
そんなに貯めて言われると、さすがに照れてしまいます。
「テオドール様も素敵ですって、あれ? テオドール様もどこかに行くのですか?」
今日のお茶会に参加するのは私だけなのに、テオドール様もしっかりと正装しています。
「私も王宮に出向いて、同僚たちと会う予定です」
「そうだったんですね」
「はい。ですから、王宮までエスコートさせてください」
「嬉しいです! ありがとうございます」
一人で王宮まで行かないといけないと思っていたので、テオドール様も一緒に来てくれると分かって私はホッとしました。
二人並んで歩き出すと、テオドール様は穏やかな声で話し始めます。
「私もロザリンド様にご挨拶させていただきます」
「はい」
「もちろん、私はお茶会に参加しませんが……。事前に私の意志はしっかりと伝えておかないといけませんので」
「はい?」
なんだかテオドール様の声が急に低くなったような気がしたので見上げると、何事もなかったようにいつもの優しい笑みを返されます。
エントランスホールでは、叔母様が待ってくれていました。
ドレス姿の私を見て、「いい出来だわ」と満足そうです。そして、不敵に微笑みました。
「独占欲丸出しの衣装を着せて、俺の女に手を出すなアピールは完璧ね」
「ど、独占欲? 俺の女⁉」
叔母様の言葉に驚いたのは私だけで、テオドール様は涼しい顔をしています。
「夫人。ご協力くださり、ありがとうございます」
「いいのよ。私も最近の王家のやり方には疑問を感じているわ。それに可愛い姪のためだもの」
私に向かってパチンとウィンクする叔母様。
「叔母様……。ありがとうございます」
「シンシア、頑張ってくるのよ。失敗してもいいから、あなたは堂々としていなさい。何を言われても謝ってはダメよ」
「は、はい!」
叔母様と別れを告げて、馬車に乗り込むと、テオドール様は私の隣に座りました。その手はしっかりと私の手を握っています。
「シンシア様。王宮内で、あなたへの私の態度が無礼だと感じるかもしれませんが、全て意味があることなので、どうかお許しください」
「えっと、はい」
私に無礼なことをするテオドール様って想像がつかないんですけど?
テオドール様は、私にひどいことはしないでしょう。なので、心配はしていません。
でも、これから何が起きるのかと、私がドキドキしている間に、馬車が王宮に着きました。
私たちを出迎えた使用人は、少しも待たせることなく丁重にロザリンド様の元へと案内してくれます。
開け放たれた扉の向こうには、可憐なロザリンド様が座っていました。
以前見たときより、顔色が良くなっています。
テオドール様が「王女殿下にご挨拶を申し上げます」と言いながら頭を下げたので、私も淑女の礼を取りました。
こちらを見る王女殿下の瞳は大きく見開いています。
「テオドール、様?」
ロザリンド様の言葉にニッコリと微笑んだテオドール様は、私の腰を抱き寄せました。
「⁉」
驚く私をよそにテオドール様の顔が近づいてきます。
「愛しいシンシア様をエスコートできて光栄です」
私の耳元でものすごくいい声がしたかと思ったら、頬にチュッとキスされました。
「どうぞお茶会をお楽しみください」
カァと頬が熱くなる私とは違い、テオドール様は満面の笑みを浮かべています。
あっなるほど、これがテオドール様が言っていた無礼なことなんですね。こんな無礼なら大歓迎です!
おそらくこの行動は、ロザリンド様に私たちの仲がいいことを見せるためにやっているのでしょう。
そうすることで、テオドール様はロザリンド様の婚約者になるつもりがないという意思表示をしているのかもしれません。
ロザリンド様は何も言わずに、固まってしまっています。
そうですよね……。もし、ロザリンド様がテオドール様に好意を持っていたら、とてもショックな光景を見せられたことになってしまいます。
側を離れようとしないテオドール様に、私は囁きました。
「もう大丈夫ですよ。あとは任せてください」
テオドール様は、一瞬だけ心配そうな顔をしましたが「分かりました」と微笑んでから、固まったままのロザリンド様に「失礼します」と声をかけてから部屋を出て行きました。
残されたのは、気まずい沈黙。
どうしたものかと思っていると、ロザリンド様の瞳から涙が零れました。
「あっ」
思わず出てしまった私の声を聞いたロザリンド様は、その涙を隠すように両手で顔を覆ってしまいます。
「皆、出て行って」
ロザリンド様の震えた声の命令で、室内に控えていたメイドたちは静かに出て行きました。
それに続いて私も出て行こうとすると「シンシア様は行かないで」と。しかも、ロザリンド様とテーブルを挟んだ向かいの席に座るように勧められてしまいます。
テーブルの上には、すでにティーセットとお菓子が並んでいました。
二人きりの室内に、ロザリンド様のすすり泣く声だけが響いています。
私は居心地が悪くて仕方ありません。ここに来る前は、罵られてお茶を頭からかけられる覚悟できましたが、これではまるで私が悪者です。
でももし、ロザリンド様がテオドール様を好きだったら、そこにどういう事情があれ、私は好きな人を奪った嫌な女です。
叔母様は『何を言われても謝ってはダメよ』と言っていましたが、失恋の痛みは想像を絶します。
私が謝ってその痛みが少しでも和らぐのなら、謝ってもいいのではないでしょうか?
覚悟を決めた私が口を開こうとしたとき、ロザリンド様の呟きが聞こえてきました。
「良かった……」
そう言いながら、ロザリンド様は両手を覆っていた手を下ろします。
「テオドール様が、お幸せそうで……」
涙で濡れてしまったその顔には、なぜか満面の笑みが浮かんでいました。
テオドール様が私のドレスやアクセサリーを用意してくださったので、準備は万端です。
お茶会まであまり日数がありませんでしたが、テオドール様のおかげで私はゆっくりと過ごすことができました。
その間に、念のためもう一度、王都でのお茶会のマナーを学び直しましたが、相変わらずいろいろと複雑です。
バルゴア領でのお茶会は、もっと気楽なものなので、王都でも気楽にお茶会を楽しんだらいいのに。
でもここは王都なので、その場所のルールに従うのが正解です。
お茶会は、バルゴア領では癒しの時間でも、王都では戦場なのです。
気を引き締めて参加しないと!
今日のお茶会に向けて改めて気合を入れた私を、ターチェ家のメイドたちが丁寧に磨いてくれます。でも、バルゴア領から一緒に来てくれた私の専属メイドジーナは、ここにはいません。
数日前に、「シンシア様。テオドール様の指示で少しお側を離れます」と言っていたので、別の場所でお仕事をしているのでしょう。ジーナの代わりに、部屋の前にいつもより多くの護衛騎士が控えています。
ターチェ家内で危ないことなんて起こらないと思うんですが……。
念には念をということなのでしょう。
メイドたちのおかげで私の髪はいつも以上にサラサラになり、お肌はツルツル。これならどこに行っても恥ずかしくありません。
メイドたちが「テオドール様からです」とドレスとアクセサリーを部屋に運び入れてくれました。
お茶会までの日にちがあまりなかったこともあり、ドレスを見るのは今が初めてです。
「よかった。間に合ったんですね」
ホッと胸を撫で下ろす私は、届いたドレスに目を奪われました。
そこには、華やかで赤いドレスがあります。赤はテオドール様の瞳の色です。
それだけではありません。胸元から腕部分は、黒いレースで飾られています。
黒はもちろんテオドール様の髪色です。
自分の色を相手に贈ることは、この国では愛情の証です。
恋愛小説でもそういうシーンがよく出てくるので、私も憧れていました。
いつか着たいと思っていた赤いドレスをテオドール様に贈ってもらえるなんて……。
大人っぽい赤いドレスなんて私には似合わないと思っていたのに、そこはさすがのテオドール様。
大人っぽすぎず、かといって子供っぽくもないドレスは、私が着ても違和感がありません。
鏡に映る自分を見て、私はポツリと呟きました。
「なんだか私、テオドール様の婚約者みたい……」
その言葉を聞いたメイドたちは、驚きながら顔を見合わせています。
いや、バルゴア領では婚約者なんですけど、王都ではまだ認められていないから、複雑な立ち位置なのです。
だからこそ、早急に国王陛下に私たちの婚約を認めていただきたいのですが……。
メイドが私にイヤリングとネックレスをつけてくれました。
テオドール様が贈ってくださったアクセサリーについている宝石は、予想外にアメジストでした。煌めく紫色は、私の瞳と同じ色です。
『どうして、紫色?』と思った私の疑問は、テオドール様の登場で解決しました。
黒い衣装を身にまとったテオドール様の首元や手首には、私と同じデザインのブローチやカフスが輝いています。
ようするに、おそろいです。
嬉しくて胸がドキドキしてしまいます。
テオドール様は、ドレスアップした私を見たとたんに、フワッと優しい笑みを浮かべました。
「シンシア様……。とても……とてもお美しいです」
そんなに貯めて言われると、さすがに照れてしまいます。
「テオドール様も素敵ですって、あれ? テオドール様もどこかに行くのですか?」
今日のお茶会に参加するのは私だけなのに、テオドール様もしっかりと正装しています。
「私も王宮に出向いて、同僚たちと会う予定です」
「そうだったんですね」
「はい。ですから、王宮までエスコートさせてください」
「嬉しいです! ありがとうございます」
一人で王宮まで行かないといけないと思っていたので、テオドール様も一緒に来てくれると分かって私はホッとしました。
二人並んで歩き出すと、テオドール様は穏やかな声で話し始めます。
「私もロザリンド様にご挨拶させていただきます」
「はい」
「もちろん、私はお茶会に参加しませんが……。事前に私の意志はしっかりと伝えておかないといけませんので」
「はい?」
なんだかテオドール様の声が急に低くなったような気がしたので見上げると、何事もなかったようにいつもの優しい笑みを返されます。
エントランスホールでは、叔母様が待ってくれていました。
ドレス姿の私を見て、「いい出来だわ」と満足そうです。そして、不敵に微笑みました。
「独占欲丸出しの衣装を着せて、俺の女に手を出すなアピールは完璧ね」
「ど、独占欲? 俺の女⁉」
叔母様の言葉に驚いたのは私だけで、テオドール様は涼しい顔をしています。
「夫人。ご協力くださり、ありがとうございます」
「いいのよ。私も最近の王家のやり方には疑問を感じているわ。それに可愛い姪のためだもの」
私に向かってパチンとウィンクする叔母様。
「叔母様……。ありがとうございます」
「シンシア、頑張ってくるのよ。失敗してもいいから、あなたは堂々としていなさい。何を言われても謝ってはダメよ」
「は、はい!」
叔母様と別れを告げて、馬車に乗り込むと、テオドール様は私の隣に座りました。その手はしっかりと私の手を握っています。
「シンシア様。王宮内で、あなたへの私の態度が無礼だと感じるかもしれませんが、全て意味があることなので、どうかお許しください」
「えっと、はい」
私に無礼なことをするテオドール様って想像がつかないんですけど?
テオドール様は、私にひどいことはしないでしょう。なので、心配はしていません。
でも、これから何が起きるのかと、私がドキドキしている間に、馬車が王宮に着きました。
私たちを出迎えた使用人は、少しも待たせることなく丁重にロザリンド様の元へと案内してくれます。
開け放たれた扉の向こうには、可憐なロザリンド様が座っていました。
以前見たときより、顔色が良くなっています。
テオドール様が「王女殿下にご挨拶を申し上げます」と言いながら頭を下げたので、私も淑女の礼を取りました。
こちらを見る王女殿下の瞳は大きく見開いています。
「テオドール、様?」
ロザリンド様の言葉にニッコリと微笑んだテオドール様は、私の腰を抱き寄せました。
「⁉」
驚く私をよそにテオドール様の顔が近づいてきます。
「愛しいシンシア様をエスコートできて光栄です」
私の耳元でものすごくいい声がしたかと思ったら、頬にチュッとキスされました。
「どうぞお茶会をお楽しみください」
カァと頬が熱くなる私とは違い、テオドール様は満面の笑みを浮かべています。
あっなるほど、これがテオドール様が言っていた無礼なことなんですね。こんな無礼なら大歓迎です!
おそらくこの行動は、ロザリンド様に私たちの仲がいいことを見せるためにやっているのでしょう。
そうすることで、テオドール様はロザリンド様の婚約者になるつもりがないという意思表示をしているのかもしれません。
ロザリンド様は何も言わずに、固まってしまっています。
そうですよね……。もし、ロザリンド様がテオドール様に好意を持っていたら、とてもショックな光景を見せられたことになってしまいます。
側を離れようとしないテオドール様に、私は囁きました。
「もう大丈夫ですよ。あとは任せてください」
テオドール様は、一瞬だけ心配そうな顔をしましたが「分かりました」と微笑んでから、固まったままのロザリンド様に「失礼します」と声をかけてから部屋を出て行きました。
残されたのは、気まずい沈黙。
どうしたものかと思っていると、ロザリンド様の瞳から涙が零れました。
「あっ」
思わず出てしまった私の声を聞いたロザリンド様は、その涙を隠すように両手で顔を覆ってしまいます。
「皆、出て行って」
ロザリンド様の震えた声の命令で、室内に控えていたメイドたちは静かに出て行きました。
それに続いて私も出て行こうとすると「シンシア様は行かないで」と。しかも、ロザリンド様とテーブルを挟んだ向かいの席に座るように勧められてしまいます。
テーブルの上には、すでにティーセットとお菓子が並んでいました。
二人きりの室内に、ロザリンド様のすすり泣く声だけが響いています。
私は居心地が悪くて仕方ありません。ここに来る前は、罵られてお茶を頭からかけられる覚悟できましたが、これではまるで私が悪者です。
でももし、ロザリンド様がテオドール様を好きだったら、そこにどういう事情があれ、私は好きな人を奪った嫌な女です。
叔母様は『何を言われても謝ってはダメよ』と言っていましたが、失恋の痛みは想像を絶します。
私が謝ってその痛みが少しでも和らぐのなら、謝ってもいいのではないでしょうか?
覚悟を決めた私が口を開こうとしたとき、ロザリンド様の呟きが聞こえてきました。
「良かった……」
そう言いながら、ロザリンド様は両手を覆っていた手を下ろします。
「テオドール様が、お幸せそうで……」
涙で濡れてしまったその顔には、なぜか満面の笑みが浮かんでいました。