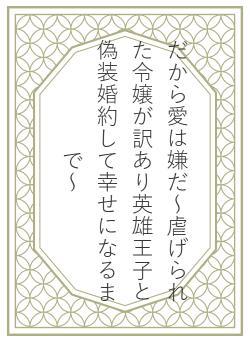ロザリンド様の誕生日パーティーから帰ると、私はすぐにお医者さんに足を見てもらうことになりました。
「あの、大丈夫ですよ。少し捻っただけですから」
ソファーに座りながら笑顔でそう言ってみたものの私の言葉は、誰にも聞いてもらえません。
足を見てもらっている私の後ろで、叔母様が心配そうな顔をしていますが、叔父様とテオドール様は気を使って後ろを向いてくださっています。
叔母様が言うには、なんでも淑女が男性に素足を見せるのは良くないとかなんとか。本当に王都はいろんなルールがありますね。
バルゴア領では、幼い頃に靴を脱ぎ捨ててお兄様と一緒に川遊びをしたことがあるんですが、そんな私の姿を見たら叔母様は倒れてしまうかもしれません。
お医者さんは私の足を丁寧に診察してくださったあとで「少し捻ったようですね。腫れてもいませんし、すぐに痛みもなくなると思います」と言ってくれました。
『だから、そう言ったのに……』と思う私の隣で、「良かったわ」と胸を撫でおろす叔母様。
「リオが社交界デビューしたときのように、骨にヒビが入っていたらどうしようかと思っていたの」
「え? お兄様、王都でケガをしていたんですか?」
あのクマみたいな兄は、骨まで丈夫そうですけど?
「違うわよ。相手の骨にヒビを入れたのよ!」
……お、お兄様は王都で、何をやらかしたんですか?
詳細を聞くのが怖すぎて、私はつい聞こえないふりをしてしまいました。
そのことが大きな問題になっていないということは、きっと叔父様と叔母様がうまく解決してくれたのでしょう。
その間にも、お医者さんは私の足に湿布を貼り、慣れた手つきで包帯を巻いてくれます。
「湿布薬を処方しておきますね」
「ありがとうございます」
お医者様の背中を見送ると、叔父様とテオドール様がくるりとこちらを向きました。
「良かった良かった」と朗らかに笑う叔父様の横で、テオドール様は深刻な顔をしています。
「テオドール様?」
私たちの妙な空気を察したのか、叔母様が叔父様と使用人たちを引きつれて部屋から出て行きました。
ああっ、行かないで!
そんな私の気持ちを知らない叔母様は、私にパチンとウィンクしてくれます。きっと気を利かせて二人きりにしてくれたつもりでしょうが、今は困ります。
なぜなら、私は昨日のテオドール様の発言を忘れることができず、気を抜くと頭の中であのときの言葉がぐるぐると回ってしまうからです。
――私はすでにシンシア様の唇のやわらかさを知っている!
――言っておくが、私はシンシア様に押し倒されて、服を脱がされたことがある。私たちはすでに、それほど深い関係だ。
あれ以来、私はテオドール様の顔をまともに見ることができません。テオドール様は普通の態度なのに、私だけ動揺してしまって恥ずかしいです。
でも、私だってちゃんと分かっているのです!
あの言葉は、テオドール様の弟であるクルト様を牽制するためのものだということを!
特に深い意味はないし、あえてああいう言い方をすることで、テオドール様が私を守ろうとしてくださったんですよね。
それなのに、こんなに意識してしまっている私がおかしいのです。
テオドール様の口から小さなため息が漏れました。私の反応が子どもすぎて呆れているのかもしれません。
熱くなってしまった顔を上げられずにいると、すぐ側でテオドール様の気配がしました。
「シンシア様」
その声は、なぜか切なさを含んでいるように聞こえます。驚いた私が顔を上げるとテオドール様は物語に出てくる騎士のようにひざまずいていました。
「あなたがお優しいことは、助けていただいた私が誰よりも知っています。でも……」
テオドール様は、私の手にそっと触れました。
「今回のようなことは二度としないでください。あなたにもし、何かあったら、私は……。お願いですから……」
私の手を両手で握りしめたテオドール様は、まるで祈っているかのようです。
「す、すみません」
素直に謝ったものの、あのときとっさに倒れたロザリンド様を支えたことを、私は後悔していません。でも、テオドール様にこんなに悲しそうな顔をさせてしまうなんて……。
「これからは気をつけます」
私が心から反省してそう伝えると、テオドール様はようやく少しだけ微笑んでくれました。
そして、私の手をしっかりと握ったまま隣に座ります。
「シンシア様。これからのことをお話させてください」
「は、はい」
至近距離にドキドキしてしまっている私とは違い、テオドール様はすっかり仕事中の顔をしています。
「国王陛下への謁見は、1ケ月後に決まりました。その場でシンシア様と私の婚約を認めてもらいます」
「1ケ月後なんて、だいぶ先ですね?」
「そうでもありませんよ。陛下への謁見は、2~3ヶ月待つなんて当たり前ですから。それと、ロザリンド様が倒れたことは、まだ公表されていません」
「そうなんですか?」
「はい。次期女王陛下となられる方の健康面が怪しいとなれば、色々面倒になります。王家としては隠したいところでしょう。私たちも内緒にしていたほうが良さそうです」
「分かりました」
「あと、クルトの件ですが」
クルトという言葉で、また昨日のことを思い出してしまった私の顔は、真っ赤になっていることでしょう。
テオドール様は、少し視線をそらしてから咳払いをしました。その頬は少し赤くなっているような気もしなくないです。
「その、昨日のことは、大変申し訳ありませんでした」
「い、いえ」
今は真面目な話をしているのですから、恥ずかしがっている場合ではありません。
「クルトの発言で分かったのですが、どうやら彼は、シンシア様を狙っているようです」
すぐに言葉の意味が理解できず、私は静かになってしまいました。
そんな私にテオドール様は、ゆっくりと言葉を紡いで再度、別の言葉を使って説明してくれます。
「クルトは、アンジェリカ様と離婚して、シンシア様と結婚することを希望していました」
「は?」
そんなこと絶対に嫌ですが?
「そして、私には仕事だけをしていればいいとも言っていたので、ベイリー公爵家の仕事を私に押しつける気のようです」
「え?」
呆然とする私にテオドール様は、さらに言葉を続けます。
「この件ですが、ベイリー公爵家の総意なのか、クルトが勝手に言っているだけなのかはまだ分かりません。しかし、クルトにはもちろん、ベイリー公爵家にも近づかないでください」
ベイリー公爵家……。
テオドール様の黒髪と赤い目が、厳しかった祖父と同じという理由だけで、テオドール様につらく当たっていた人々。
あの話を聞いたときから愚かだとは思っていましたが、まさかここまでだなんて……。
「あのテオドール様、ちょっと分からないのですが、どうして銀髪野郎、じゃなくて! クルト様と私が結婚するなんて話が出てくるのですか? 私はテオドール様との婚約を望んでいるのですが?」
テオドール様は、困ったような顔をしています。
「クルトは次期ベイリー公爵です。身分が申し分ない上に、母に似た華やかな外見が王都ではとても人気があります。彼に声をかけられて喜ばない女性はいないでしょう」
「ここにいるのですが?」
きっぱりと言い切った私にテオドール様は、ニッコリと微笑みました。
「そうですね……」
私を優しく抱きしめたテオドール様は、「そうですよね」と嬉しそうに繰り返しています。
その笑みにときめきつつも、私は心の中で『まさか同僚さんたちだけでなく、ベイリー公爵家までテオドール様を取り戻そうとしているなんて』と驚いていました。
確かに優秀なテオドール様は、なんでもできます。でもテオドール様を側で見てきた私は知っています。
テオドール様は初めからなんでもできるのではなく、できるようになるまで努力し続ける人だということを。
だから、なんでもかんでもテオドール様に頼るのは間違っています。
私は大きなため息をつきました。
「王都の方々は皆、テオドール様に頼りすぎです。それではテオドール様はどんどん苦しくなってしまいます。だから、私はそうならないように、しっかりとした大人の女性になって、テオドール様に頼らないように気をつけますね」
安心してほしくてそう伝えると、テオドール様は複雑な表情をしていました。
「頼られたくない相手には頼られ、頼って甘えてほしい方には頼られない。難しいですね。……まぁ、諦める気はありませんが」
その笑みに少しだけ黒いものを感じてしまったのは、きっと気のせいではないでしょう。でも、そんな笑顔も素敵です。
「あの、大丈夫ですよ。少し捻っただけですから」
ソファーに座りながら笑顔でそう言ってみたものの私の言葉は、誰にも聞いてもらえません。
足を見てもらっている私の後ろで、叔母様が心配そうな顔をしていますが、叔父様とテオドール様は気を使って後ろを向いてくださっています。
叔母様が言うには、なんでも淑女が男性に素足を見せるのは良くないとかなんとか。本当に王都はいろんなルールがありますね。
バルゴア領では、幼い頃に靴を脱ぎ捨ててお兄様と一緒に川遊びをしたことがあるんですが、そんな私の姿を見たら叔母様は倒れてしまうかもしれません。
お医者さんは私の足を丁寧に診察してくださったあとで「少し捻ったようですね。腫れてもいませんし、すぐに痛みもなくなると思います」と言ってくれました。
『だから、そう言ったのに……』と思う私の隣で、「良かったわ」と胸を撫でおろす叔母様。
「リオが社交界デビューしたときのように、骨にヒビが入っていたらどうしようかと思っていたの」
「え? お兄様、王都でケガをしていたんですか?」
あのクマみたいな兄は、骨まで丈夫そうですけど?
「違うわよ。相手の骨にヒビを入れたのよ!」
……お、お兄様は王都で、何をやらかしたんですか?
詳細を聞くのが怖すぎて、私はつい聞こえないふりをしてしまいました。
そのことが大きな問題になっていないということは、きっと叔父様と叔母様がうまく解決してくれたのでしょう。
その間にも、お医者さんは私の足に湿布を貼り、慣れた手つきで包帯を巻いてくれます。
「湿布薬を処方しておきますね」
「ありがとうございます」
お医者様の背中を見送ると、叔父様とテオドール様がくるりとこちらを向きました。
「良かった良かった」と朗らかに笑う叔父様の横で、テオドール様は深刻な顔をしています。
「テオドール様?」
私たちの妙な空気を察したのか、叔母様が叔父様と使用人たちを引きつれて部屋から出て行きました。
ああっ、行かないで!
そんな私の気持ちを知らない叔母様は、私にパチンとウィンクしてくれます。きっと気を利かせて二人きりにしてくれたつもりでしょうが、今は困ります。
なぜなら、私は昨日のテオドール様の発言を忘れることができず、気を抜くと頭の中であのときの言葉がぐるぐると回ってしまうからです。
――私はすでにシンシア様の唇のやわらかさを知っている!
――言っておくが、私はシンシア様に押し倒されて、服を脱がされたことがある。私たちはすでに、それほど深い関係だ。
あれ以来、私はテオドール様の顔をまともに見ることができません。テオドール様は普通の態度なのに、私だけ動揺してしまって恥ずかしいです。
でも、私だってちゃんと分かっているのです!
あの言葉は、テオドール様の弟であるクルト様を牽制するためのものだということを!
特に深い意味はないし、あえてああいう言い方をすることで、テオドール様が私を守ろうとしてくださったんですよね。
それなのに、こんなに意識してしまっている私がおかしいのです。
テオドール様の口から小さなため息が漏れました。私の反応が子どもすぎて呆れているのかもしれません。
熱くなってしまった顔を上げられずにいると、すぐ側でテオドール様の気配がしました。
「シンシア様」
その声は、なぜか切なさを含んでいるように聞こえます。驚いた私が顔を上げるとテオドール様は物語に出てくる騎士のようにひざまずいていました。
「あなたがお優しいことは、助けていただいた私が誰よりも知っています。でも……」
テオドール様は、私の手にそっと触れました。
「今回のようなことは二度としないでください。あなたにもし、何かあったら、私は……。お願いですから……」
私の手を両手で握りしめたテオドール様は、まるで祈っているかのようです。
「す、すみません」
素直に謝ったものの、あのときとっさに倒れたロザリンド様を支えたことを、私は後悔していません。でも、テオドール様にこんなに悲しそうな顔をさせてしまうなんて……。
「これからは気をつけます」
私が心から反省してそう伝えると、テオドール様はようやく少しだけ微笑んでくれました。
そして、私の手をしっかりと握ったまま隣に座ります。
「シンシア様。これからのことをお話させてください」
「は、はい」
至近距離にドキドキしてしまっている私とは違い、テオドール様はすっかり仕事中の顔をしています。
「国王陛下への謁見は、1ケ月後に決まりました。その場でシンシア様と私の婚約を認めてもらいます」
「1ケ月後なんて、だいぶ先ですね?」
「そうでもありませんよ。陛下への謁見は、2~3ヶ月待つなんて当たり前ですから。それと、ロザリンド様が倒れたことは、まだ公表されていません」
「そうなんですか?」
「はい。次期女王陛下となられる方の健康面が怪しいとなれば、色々面倒になります。王家としては隠したいところでしょう。私たちも内緒にしていたほうが良さそうです」
「分かりました」
「あと、クルトの件ですが」
クルトという言葉で、また昨日のことを思い出してしまった私の顔は、真っ赤になっていることでしょう。
テオドール様は、少し視線をそらしてから咳払いをしました。その頬は少し赤くなっているような気もしなくないです。
「その、昨日のことは、大変申し訳ありませんでした」
「い、いえ」
今は真面目な話をしているのですから、恥ずかしがっている場合ではありません。
「クルトの発言で分かったのですが、どうやら彼は、シンシア様を狙っているようです」
すぐに言葉の意味が理解できず、私は静かになってしまいました。
そんな私にテオドール様は、ゆっくりと言葉を紡いで再度、別の言葉を使って説明してくれます。
「クルトは、アンジェリカ様と離婚して、シンシア様と結婚することを希望していました」
「は?」
そんなこと絶対に嫌ですが?
「そして、私には仕事だけをしていればいいとも言っていたので、ベイリー公爵家の仕事を私に押しつける気のようです」
「え?」
呆然とする私にテオドール様は、さらに言葉を続けます。
「この件ですが、ベイリー公爵家の総意なのか、クルトが勝手に言っているだけなのかはまだ分かりません。しかし、クルトにはもちろん、ベイリー公爵家にも近づかないでください」
ベイリー公爵家……。
テオドール様の黒髪と赤い目が、厳しかった祖父と同じという理由だけで、テオドール様につらく当たっていた人々。
あの話を聞いたときから愚かだとは思っていましたが、まさかここまでだなんて……。
「あのテオドール様、ちょっと分からないのですが、どうして銀髪野郎、じゃなくて! クルト様と私が結婚するなんて話が出てくるのですか? 私はテオドール様との婚約を望んでいるのですが?」
テオドール様は、困ったような顔をしています。
「クルトは次期ベイリー公爵です。身分が申し分ない上に、母に似た華やかな外見が王都ではとても人気があります。彼に声をかけられて喜ばない女性はいないでしょう」
「ここにいるのですが?」
きっぱりと言い切った私にテオドール様は、ニッコリと微笑みました。
「そうですね……」
私を優しく抱きしめたテオドール様は、「そうですよね」と嬉しそうに繰り返しています。
その笑みにときめきつつも、私は心の中で『まさか同僚さんたちだけでなく、ベイリー公爵家までテオドール様を取り戻そうとしているなんて』と驚いていました。
確かに優秀なテオドール様は、なんでもできます。でもテオドール様を側で見てきた私は知っています。
テオドール様は初めからなんでもできるのではなく、できるようになるまで努力し続ける人だということを。
だから、なんでもかんでもテオドール様に頼るのは間違っています。
私は大きなため息をつきました。
「王都の方々は皆、テオドール様に頼りすぎです。それではテオドール様はどんどん苦しくなってしまいます。だから、私はそうならないように、しっかりとした大人の女性になって、テオドール様に頼らないように気をつけますね」
安心してほしくてそう伝えると、テオドール様は複雑な表情をしていました。
「頼られたくない相手には頼られ、頼って甘えてほしい方には頼られない。難しいですね。……まぁ、諦める気はありませんが」
その笑みに少しだけ黒いものを感じてしまったのは、きっと気のせいではないでしょう。でも、そんな笑顔も素敵です。