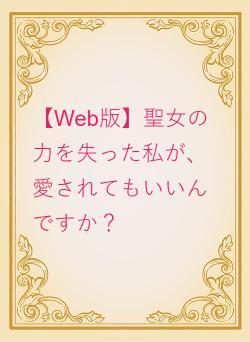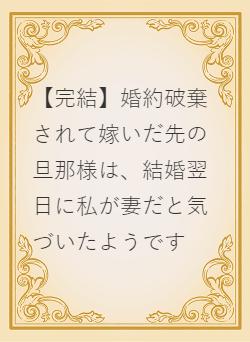「いつからあの子どもが私だと気づいていたんだ?」
「最初からだ」
「ほお?」
興味深そうに私のほうを見ている彼に、自分がどうしてそう思ったのか告げる。
「店を引き継いだといっていたが、全て子どもの背の高さでは届かない場所に道具が置かれていた」
「洞察力があるな、お前」
「どうも」
そうだ、子どもにしては違和感のある振る舞いや言葉、そして師匠が死んだのに淡々と事情を話す。
あまりにも「子どもではなかった」ことに違和感を覚えた。
「アリスを本気で傷つけようとしていたら、あの魔法での幻覚の時点でお前を殺していた」
「ふん、俺は命拾いしたわけか」
「命までは取りはしないといいながら王族のブローチを見せられたら、下手に動けるわけがない」
アリスがイルゼの魔法の幻覚で「試された」時、俺は詰め寄った。
しかしあんな身分証を見せられては自国内でもない、私には何もできなかった。
「これからどうするんだ?」
「アリスを守る、私のすることはそれのみ」
ワインを飲み干して立ち上がった私に、イルゼが声をかける。
「最初からだ」
「ほお?」
興味深そうに私のほうを見ている彼に、自分がどうしてそう思ったのか告げる。
「店を引き継いだといっていたが、全て子どもの背の高さでは届かない場所に道具が置かれていた」
「洞察力があるな、お前」
「どうも」
そうだ、子どもにしては違和感のある振る舞いや言葉、そして師匠が死んだのに淡々と事情を話す。
あまりにも「子どもではなかった」ことに違和感を覚えた。
「アリスを本気で傷つけようとしていたら、あの魔法での幻覚の時点でお前を殺していた」
「ふん、俺は命拾いしたわけか」
「命までは取りはしないといいながら王族のブローチを見せられたら、下手に動けるわけがない」
アリスがイルゼの魔法の幻覚で「試された」時、俺は詰め寄った。
しかしあんな身分証を見せられては自国内でもない、私には何もできなかった。
「これからどうするんだ?」
「アリスを守る、私のすることはそれのみ」
ワインを飲み干して立ち上がった私に、イルゼが声をかける。