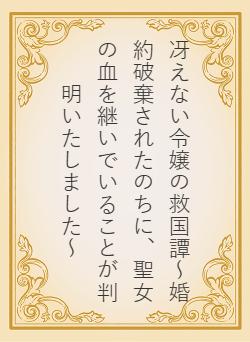「お、おおお王子様で……あらせられたとは思わず、ご無礼を……」
「気を使う必要はない。どのような非礼を取ろうとも、恩人を罰したりはせん。安心しろ」
そうは言うが、令嬢であった頃ならまだしもメルはもう一般市民だ。
雲の上の人間に下手な口を聞き、やはり気が変わったではたまらない。
遠慮するように肩を竦め、機嫌を窺う。
「お、お身体は痛みます?」
「いや、そうでもない。ただ、少し……疲れて、な」
そこで気づいた。安堵のせいかここへきて、ただでさえ白かったその顔が、青く見えるほどになっている。
思えばたびたび、馬上でも彼は意識が落ちそうになっていた。やはり、こんな状態で数日間の旅路は厳しかったのだろう。本来ならしばらくベッドで安静にしているべきなのに、気力で無理やり体を持たせていたのだ。
そこまで急いでこの屋敷に戻ろうとするなんて――。
(いったいどういった事情があるのかしら)
感心と呆れが半々のメルの肩口に、
「う……限界だ。済ま……ない。後は、たの……む」
「気を使う必要はない。どのような非礼を取ろうとも、恩人を罰したりはせん。安心しろ」
そうは言うが、令嬢であった頃ならまだしもメルはもう一般市民だ。
雲の上の人間に下手な口を聞き、やはり気が変わったではたまらない。
遠慮するように肩を竦め、機嫌を窺う。
「お、お身体は痛みます?」
「いや、そうでもない。ただ、少し……疲れて、な」
そこで気づいた。安堵のせいかここへきて、ただでさえ白かったその顔が、青く見えるほどになっている。
思えばたびたび、馬上でも彼は意識が落ちそうになっていた。やはり、こんな状態で数日間の旅路は厳しかったのだろう。本来ならしばらくベッドで安静にしているべきなのに、気力で無理やり体を持たせていたのだ。
そこまで急いでこの屋敷に戻ろうとするなんて――。
(いったいどういった事情があるのかしら)
感心と呆れが半々のメルの肩口に、
「う……限界だ。済ま……ない。後は、たの……む」