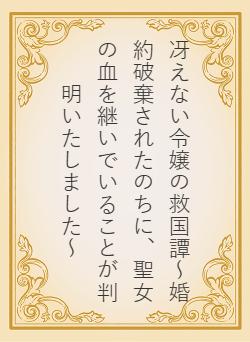絹糸の様に滑る金の髪が指の間をさらさらと流れる。一度触れてしまうと……胸の中が、今まで感じたことのない愛おしさで溢れてしまう。
「大好きですよ、ラルドリス様。あなたのその真っ直ぐなところが……。私は、本当は疑いの強い人間なんです。でも、あなたのことは不思議と信じられた。最初からこの人に力を貸してあげたいとそう、思えたんです」
「ずるいよお前は……。そういうところをおくびにも出さないくせ、いつもけなげにこっちを気遣って。お前がひとり寂しく森に帰るところなんて、見たくない。ずっと俺の傍にいろ」
「ぁ……」
気付けば、ラルドリスの唇がメルのものを塞いでいた。
それは互いに生まれて初めてなのか、上手なものではなかったけれど――温かく柔らかい感触と同時に、互いを想う感情が流れ込み、混ざり合う。
掴まれた手からも同じリズムの脈動が伝わり、まるで不可分の存在になれたかのような安らぎが、体を支配する……。
静かに唇を離した後も、ふたりは満ち足りた気持でずっと、身体を離さずにいた。
木立の陰が伸びてゆくのを眺めながら、ラルドリスはメルの耳元で呟く。
「離れて欲しくないんだよ、大事な人は。お前、一言も言ってくれなかったな。寂しいんだって……」
「大好きですよ、ラルドリス様。あなたのその真っ直ぐなところが……。私は、本当は疑いの強い人間なんです。でも、あなたのことは不思議と信じられた。最初からこの人に力を貸してあげたいとそう、思えたんです」
「ずるいよお前は……。そういうところをおくびにも出さないくせ、いつもけなげにこっちを気遣って。お前がひとり寂しく森に帰るところなんて、見たくない。ずっと俺の傍にいろ」
「ぁ……」
気付けば、ラルドリスの唇がメルのものを塞いでいた。
それは互いに生まれて初めてなのか、上手なものではなかったけれど――温かく柔らかい感触と同時に、互いを想う感情が流れ込み、混ざり合う。
掴まれた手からも同じリズムの脈動が伝わり、まるで不可分の存在になれたかのような安らぎが、体を支配する……。
静かに唇を離した後も、ふたりは満ち足りた気持でずっと、身体を離さずにいた。
木立の陰が伸びてゆくのを眺めながら、ラルドリスはメルの耳元で呟く。
「離れて欲しくないんだよ、大事な人は。お前、一言も言ってくれなかったな。寂しいんだって……」