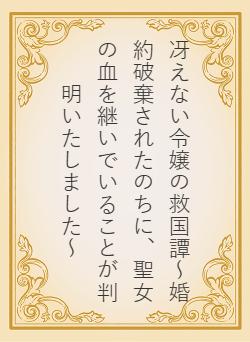すぐさま訂正を求めるが、ラルドリスはまったく引きそうにない。捧げ持つように握ったメルの手を離さず、一瞬たりとも目線を逸らさなかった。
「からかうならもうちょっとうまくやってる! 何度でも言うぞ、俺はお前に惚れたんだ。決して、お前が特別な力を持っているからとかじゃなくな。誰も見向きもしなかった俺にたくさんのことを教え、ここまで導いて守ってくれた……そんな女性を、好きになってなにがおかしい。今度は俺が傍に居てお前を守りたいんだ。お前を、ずっと笑顔でいさせてやりたい……」
情熱的な告白に、メルの顔がみるみる赤くなる。だが、彼女はその手を自分の方に引き戻すと……突き放すようにラルドリスを睨みつける。
「一度冷静になって考えてみてください……! 私はもう侯爵家の娘でもなんでもないんです。そんな人間があなたのような人とどうやって結ばれるんです!」
「そんなものどうとでもしてやるさ! 王族の権力を舐めるなよ、シーベルだってボルドフだって、母上もきっと協力してくれる! それともなにか、お前は俺のことが……嫌いなのか?」
「……そんなわけ、ないじゃないですか」
耳の垂れた犬のようにしょんぼりしたラルドリスの姿がなんとも庇護欲をそそり、メルは不敬だと思いつつもその頭を撫で、抱き締めた。
「からかうならもうちょっとうまくやってる! 何度でも言うぞ、俺はお前に惚れたんだ。決して、お前が特別な力を持っているからとかじゃなくな。誰も見向きもしなかった俺にたくさんのことを教え、ここまで導いて守ってくれた……そんな女性を、好きになってなにがおかしい。今度は俺が傍に居てお前を守りたいんだ。お前を、ずっと笑顔でいさせてやりたい……」
情熱的な告白に、メルの顔がみるみる赤くなる。だが、彼女はその手を自分の方に引き戻すと……突き放すようにラルドリスを睨みつける。
「一度冷静になって考えてみてください……! 私はもう侯爵家の娘でもなんでもないんです。そんな人間があなたのような人とどうやって結ばれるんです!」
「そんなものどうとでもしてやるさ! 王族の権力を舐めるなよ、シーベルだってボルドフだって、母上もきっと協力してくれる! それともなにか、お前は俺のことが……嫌いなのか?」
「……そんなわけ、ないじゃないですか」
耳の垂れた犬のようにしょんぼりしたラルドリスの姿がなんとも庇護欲をそそり、メルは不敬だと思いつつもその頭を撫で、抱き締めた。