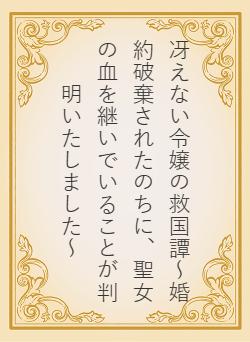私たちがいますから……言葉の外にそんな気持ちを込めて。メルは彼の瞳をじっと見つめた。
「ああ。そうだな、ひとりではないんだ。背中は任せる」
ラルドリスはメルの手を強く握り返すと、快活な笑みを装うが、やはり顔のこわばりは消えない。
そして手の震えも、城に辿り着くまで治まることはなかった。
◇
いくつもの赤屋根の尖塔が針のように連なる王城は、平時は丸い堀に囲まれ、決められた時間や緊急時のみ跳ね橋が下りて通行を許可される仕組みのようだ。
だがラルドリスはさすがに王族。ボルドフの手回しもあり、一行は比較的スムーズに橋を渡り、城の敷地内に足を踏み入れる。
「早速囚われの母に顔を見せに行きたいところだが、まずは父上に帰還を報告せねばなるまい。ボルドフ、先導を頼む」
「御意」
停車場で馬車から降りると、ラルドリスはボルドフにそう命じた。部隊は解散し、彼と少数の精鋭だけがラルドリスの護衛に付くようだ。メルもシーベルもラルドリスの後ろに付く。
「ああ。そうだな、ひとりではないんだ。背中は任せる」
ラルドリスはメルの手を強く握り返すと、快活な笑みを装うが、やはり顔のこわばりは消えない。
そして手の震えも、城に辿り着くまで治まることはなかった。
◇
いくつもの赤屋根の尖塔が針のように連なる王城は、平時は丸い堀に囲まれ、決められた時間や緊急時のみ跳ね橋が下りて通行を許可される仕組みのようだ。
だがラルドリスはさすがに王族。ボルドフの手回しもあり、一行は比較的スムーズに橋を渡り、城の敷地内に足を踏み入れる。
「早速囚われの母に顔を見せに行きたいところだが、まずは父上に帰還を報告せねばなるまい。ボルドフ、先導を頼む」
「御意」
停車場で馬車から降りると、ラルドリスはボルドフにそう命じた。部隊は解散し、彼と少数の精鋭だけがラルドリスの護衛に付くようだ。メルもシーベルもラルドリスの後ろに付く。