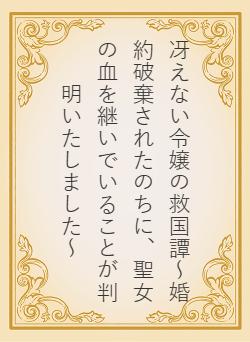その後の記憶は飛び飛びだ。
温もりの消えた彼女を背負うと、魔法の力を借り急いでサンチノの街医者を尋ねたこと。
そこで、祖母が既に亡くなっていることを聞かされ、教会へと連れて行かれたこと。
冷たくなった祖母の手を握り呆然としているところを教会の神父に諭され、遺体を焼いてもらう流れになったこと。
小さな壺に骨だけを入れて持ち帰り、ひとりで弔ったこと。
そこからは考えることを避け、生物としての本能に従い同じことを繰り返すような毎日を過ごしていたのだと思う。
そうして気が付けば、メルは日常に戻っていた。すべてが夢の中のような、非常にぼんやりとした日々からメルが現実に戻るころには、実に半年ほどの時間が経過していた――。
……彼らがなにかをしたわけではない。一生懸命祖母を運んできたメルを気遣い、できる限りのことをしてくれた。それは理解していても、記憶からなんともいえない虚しさが湧きあがってどうしようもなくなりそうで怖い。だからメルは視線を下に落とす。
「どうかしたか?」
温もりの消えた彼女を背負うと、魔法の力を借り急いでサンチノの街医者を尋ねたこと。
そこで、祖母が既に亡くなっていることを聞かされ、教会へと連れて行かれたこと。
冷たくなった祖母の手を握り呆然としているところを教会の神父に諭され、遺体を焼いてもらう流れになったこと。
小さな壺に骨だけを入れて持ち帰り、ひとりで弔ったこと。
そこからは考えることを避け、生物としての本能に従い同じことを繰り返すような毎日を過ごしていたのだと思う。
そうして気が付けば、メルは日常に戻っていた。すべてが夢の中のような、非常にぼんやりとした日々からメルが現実に戻るころには、実に半年ほどの時間が経過していた――。
……彼らがなにかをしたわけではない。一生懸命祖母を運んできたメルを気遣い、できる限りのことをしてくれた。それは理解していても、記憶からなんともいえない虚しさが湧きあがってどうしようもなくなりそうで怖い。だからメルは視線を下に落とす。
「どうかしたか?」