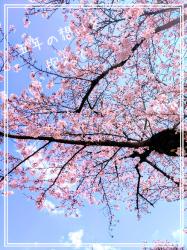チャラくてお調子者の性格が故に何も考えていないのか、彰のやさしさなのかはわからない。
でも異質なものだと自覚して、親にさえ言えてない俺にとって彰は救いだった。
「だからさ、俺はそんな啓斗が好きになった人とちゃんと幸せになってほしいんだよ」
「はいはい」
俺の照れ隠しの塩対応にも彰は気づいついるようだった。
もう一度高宮の方に目線を移す。
高宮にも彰のような存在はいたんだろうか。
自席に1人で座る彼女は小さく見えた。
先生に頼まれた用事を済ませた俺は薄暗い教室に足を踏み入れた。
そこにはただぼんやりと座る高宮がいた。
相変わらず心は読めないまま。
「高宮」
でも異質なものだと自覚して、親にさえ言えてない俺にとって彰は救いだった。
「だからさ、俺はそんな啓斗が好きになった人とちゃんと幸せになってほしいんだよ」
「はいはい」
俺の照れ隠しの塩対応にも彰は気づいついるようだった。
もう一度高宮の方に目線を移す。
高宮にも彰のような存在はいたんだろうか。
自席に1人で座る彼女は小さく見えた。
先生に頼まれた用事を済ませた俺は薄暗い教室に足を踏み入れた。
そこにはただぼんやりと座る高宮がいた。
相変わらず心は読めないまま。
「高宮」