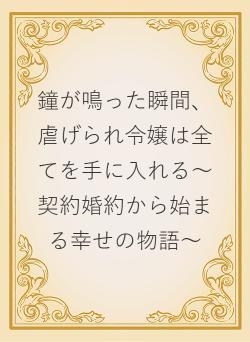「それで姉様は、兄様と一緒に玄関まで行ったの?」
ダイニングに着くと、すでに着席していた弟のクリフに、これまでの出来事を話した。
私が隣に座ると、次々に食事を運んでくれる使用人たち。そのどれもが私の好きなもの、と栄養を考えた料理だった。
さらによく見ると、クリフの前に置かれている料理とは違うラインナップ。お母様が言った通り、準備されていたことがありありと理解できた。
「えぇ。だからお兄様があぁして項垂れているんじゃない」
「相手は婚約者になったエヴァレット辺境伯だろう? しかも倒れそうになった姉様を助けただけで、抱き合ったわけじゃないのに、大袈裟なんだから」
「何を言っているんだ、クリフ。お前はアレを見ていないから!」
そう、私とお兄様はダイニングを目前にしながら、玄関に戻ったのだ。何故、目前かというと、私が一度、お兄様を説得してしまったせいだった。
***
時を遡ること、数十分前。
毎日使用人たちの手で綺麗に整えられている廊下を歩いていた。
壁には聖画を思わせる神聖な絵画が掛けてある。複雑な彫刻が施されている額縁が、さらにその神秘性を高めていた。
それを眺めながら、私はふと足を止める。
「お兄様。やはり様子だけでも見に行く、というのはどうでしょう」
前方を歩くお兄様が振り返った。訝しげな目を向けて。しかし、それは無理もなかった。
「さっきは俺が許可したのにもかかわらず止めたじゃないか。それなのに?」
「だってあれは……」
問答無用でアリスター様に剣を、いや文句を言いに行きそうな雰囲気だったから止めたのよ!
本当は私だって行きたかったのに、それを我慢して。だけどやっぱり……。
「その……何と言いますか、えっと。お兄様だって気になりませんか? アリスター様のご様子。お名前で呼ばれるほど、親しいのではありませんか?」
普通に聞き流していたが、お兄様とアリスター様が知り合いだったことに驚いた。
成人したばかりの私と違って、すでに社交界にいた二人だ。そんなに驚くべきことではないのだろうが、意外だった。
お兄様がわざわざ、偏屈と噂されているアリスター様と親しくなる理由が分からなかったのだ。
「お互い騎士団を有している家門だからね。色々とあるのさ。まぁそれもあってからかな。バードランド皇子なんかよりは十分、母上の相手は務まるって俺は思っているよ」
「それはつまり、バードランド皇子に婚約破棄されたのは、お母様が原因なんですか?」
結んだのも、恐らくお母様の意思だとは思うけれど。今はそれよりも、恐ろしい想像が脳裏を過った。
「バードランド皇子とアリスター様。変だとは思ったんです。接点のない二人が共謀なんて。もしかして今回の出来事に、お兄様も一枚噛んでいらっしゃるんですか?」
それなら辻褄が合う。
いくら婚約者でも、皇族でも、一令嬢の私室に入るなんて許されることではない。使用人たちが止めるだろう。
けれど、私専属のメイドであるサミーさえも、そのことに言及はしなかった。つまり、誰かが許可を出したのだ。私は確認するように、その相手に向かって詰め寄った。
「お答えください、お兄様」
するとお兄様は、口元を手で隠して、いかにもマズいといった顔をした。次期公爵がそれでいいのか、とジト目で見ると、さらに顔が青くなる。
「あっ……これは、その、何と言うか……」
「大丈夫です。そういうところはアリスター様と同じなんですね。何って言うんでしたっけ、こういうの。あぁ、思い出しました。類は友を呼ぶ、というんですよね。お兄様の認識を改めさせてもらいました。あと、これはお母様に報告すべき案件ですからね」
いいですよね、と尋ねずに私は、真顔で処刑にも似た通告を宣言した。さらにショックで固まっているお兄様の隙をついて、来た道を引き返す。
ダイニングからエントランスまでは一直線の廊下だったから、最初から遠慮は必要ない。幼い頃から騎士団に交じって訓練をしてきたのだ。そこら辺の令嬢とは違い、私は速かった。
「っ! メイベル!」
ようやく我に返ったのか、お兄様の声が廊下に響き渡る。けれどもう遅い! 私の足はエントランスに踏み入れていた。
すでに私とお兄様の声は、エントランスにいる使用人たちには聞こえていたらしい。
邪魔にならないように壁際に寄っていた。いや、巻き込まれないようにしていたのだろう。お陰で、玄関先に立つお母様とアリスター様の姿が見えた。
お兄様に捕まる前に、私は透かさず名前を呼ぶ。
「お母様!」
「メイベル、どうして、まだここに? いえ、違うわね。話ならあとでと言ったでしょう」
私が引き返して来たのだと、瞬時に判断するお母様。さすがだと言いたいところだが、内容が違う。
「実はお母様に聞いていただきたい話ができたので、急遽戻ってきたんです」
後ろから足音が聞こえるが、私は気にしなかった。お母様を目の前にして、無体なことはしないだろう、と高を括ったのだ。
しかしそれは、詰めが甘かった。
「今回のバードランド皇子との婚約破――……」
お兄様に口を塞がれたのだ。が、私もお母様の娘。思いっ切り足を後ろに蹴った。さらに抗議の言葉を言おうと振り返った瞬間、私はバランスを崩した。
「え?」
「「「メイベル!!」」」
その原因に気づかず、私は受け身を取ろうと体を半回転させる。このまま片足を前に出して踏ん張れば大丈夫、と思った矢先、スカートが足に絡まってできないことに気がついた。
あっ。いつも訓練ではズボンだったから……!
私は衝突に備えて目を瞑った。けれど痛みを感じない。地面ほどではないが、硬い何かに当たったような気がしたのだ。
恐る恐る目を開けると、そこには……。
「大丈夫か。怪我は?」
少しだけ息を切らせて私を覗く、赤い瞳があった。それがアリスター様だと気がつくのに数秒。
だって、私が倒れかけた時、アリスター様はお母様を挟んだ向こう側にいた。当然、間に合わない距離だった……はずなのに。
何も言わない私を余所に、アリスター様は肩や腕などに触れ、入念にチェックをする。その行為に私は勿論のこと、お母様もお兄様も何も言わない。
お陰でアリスター様に助けられたのだと気づいたのは、その逞しい腕に包まれた瞬間だった。
「はぁ~。良かった」
「!!」
頭上からかかる息に、体が反応する。羞恥なのか、それとも別の感情なのか分からなかったが、顔が一気に熱くなった。
すぐにここから離れないと、と思うのに体が動かない。もう少しこのまま、と思う気持ちの方が大きくて、アリスター様を押しのけられなかった。
けれど私の意思とは正反対に、体がアリスター様から離れていく。誰かが私の体を掴み、引っ張ったのだ。
「母上。メイベルはバランスを崩すほどお腹を空かせているようなので、すぐにダイニングへ連れて行こうと思います」
「え? あぁ、そうね。そうしなさい、エルバート」
混乱状態の私は、そうしてお兄様によってダイニングへ強制連行されたのだ。気がついた時には隣にクリフがいて、思わず一部始終を語っていた、というのが事の顛末だった。
ダイニングに着くと、すでに着席していた弟のクリフに、これまでの出来事を話した。
私が隣に座ると、次々に食事を運んでくれる使用人たち。そのどれもが私の好きなもの、と栄養を考えた料理だった。
さらによく見ると、クリフの前に置かれている料理とは違うラインナップ。お母様が言った通り、準備されていたことがありありと理解できた。
「えぇ。だからお兄様があぁして項垂れているんじゃない」
「相手は婚約者になったエヴァレット辺境伯だろう? しかも倒れそうになった姉様を助けただけで、抱き合ったわけじゃないのに、大袈裟なんだから」
「何を言っているんだ、クリフ。お前はアレを見ていないから!」
そう、私とお兄様はダイニングを目前にしながら、玄関に戻ったのだ。何故、目前かというと、私が一度、お兄様を説得してしまったせいだった。
***
時を遡ること、数十分前。
毎日使用人たちの手で綺麗に整えられている廊下を歩いていた。
壁には聖画を思わせる神聖な絵画が掛けてある。複雑な彫刻が施されている額縁が、さらにその神秘性を高めていた。
それを眺めながら、私はふと足を止める。
「お兄様。やはり様子だけでも見に行く、というのはどうでしょう」
前方を歩くお兄様が振り返った。訝しげな目を向けて。しかし、それは無理もなかった。
「さっきは俺が許可したのにもかかわらず止めたじゃないか。それなのに?」
「だってあれは……」
問答無用でアリスター様に剣を、いや文句を言いに行きそうな雰囲気だったから止めたのよ!
本当は私だって行きたかったのに、それを我慢して。だけどやっぱり……。
「その……何と言いますか、えっと。お兄様だって気になりませんか? アリスター様のご様子。お名前で呼ばれるほど、親しいのではありませんか?」
普通に聞き流していたが、お兄様とアリスター様が知り合いだったことに驚いた。
成人したばかりの私と違って、すでに社交界にいた二人だ。そんなに驚くべきことではないのだろうが、意外だった。
お兄様がわざわざ、偏屈と噂されているアリスター様と親しくなる理由が分からなかったのだ。
「お互い騎士団を有している家門だからね。色々とあるのさ。まぁそれもあってからかな。バードランド皇子なんかよりは十分、母上の相手は務まるって俺は思っているよ」
「それはつまり、バードランド皇子に婚約破棄されたのは、お母様が原因なんですか?」
結んだのも、恐らくお母様の意思だとは思うけれど。今はそれよりも、恐ろしい想像が脳裏を過った。
「バードランド皇子とアリスター様。変だとは思ったんです。接点のない二人が共謀なんて。もしかして今回の出来事に、お兄様も一枚噛んでいらっしゃるんですか?」
それなら辻褄が合う。
いくら婚約者でも、皇族でも、一令嬢の私室に入るなんて許されることではない。使用人たちが止めるだろう。
けれど、私専属のメイドであるサミーさえも、そのことに言及はしなかった。つまり、誰かが許可を出したのだ。私は確認するように、その相手に向かって詰め寄った。
「お答えください、お兄様」
するとお兄様は、口元を手で隠して、いかにもマズいといった顔をした。次期公爵がそれでいいのか、とジト目で見ると、さらに顔が青くなる。
「あっ……これは、その、何と言うか……」
「大丈夫です。そういうところはアリスター様と同じなんですね。何って言うんでしたっけ、こういうの。あぁ、思い出しました。類は友を呼ぶ、というんですよね。お兄様の認識を改めさせてもらいました。あと、これはお母様に報告すべき案件ですからね」
いいですよね、と尋ねずに私は、真顔で処刑にも似た通告を宣言した。さらにショックで固まっているお兄様の隙をついて、来た道を引き返す。
ダイニングからエントランスまでは一直線の廊下だったから、最初から遠慮は必要ない。幼い頃から騎士団に交じって訓練をしてきたのだ。そこら辺の令嬢とは違い、私は速かった。
「っ! メイベル!」
ようやく我に返ったのか、お兄様の声が廊下に響き渡る。けれどもう遅い! 私の足はエントランスに踏み入れていた。
すでに私とお兄様の声は、エントランスにいる使用人たちには聞こえていたらしい。
邪魔にならないように壁際に寄っていた。いや、巻き込まれないようにしていたのだろう。お陰で、玄関先に立つお母様とアリスター様の姿が見えた。
お兄様に捕まる前に、私は透かさず名前を呼ぶ。
「お母様!」
「メイベル、どうして、まだここに? いえ、違うわね。話ならあとでと言ったでしょう」
私が引き返して来たのだと、瞬時に判断するお母様。さすがだと言いたいところだが、内容が違う。
「実はお母様に聞いていただきたい話ができたので、急遽戻ってきたんです」
後ろから足音が聞こえるが、私は気にしなかった。お母様を目の前にして、無体なことはしないだろう、と高を括ったのだ。
しかしそれは、詰めが甘かった。
「今回のバードランド皇子との婚約破――……」
お兄様に口を塞がれたのだ。が、私もお母様の娘。思いっ切り足を後ろに蹴った。さらに抗議の言葉を言おうと振り返った瞬間、私はバランスを崩した。
「え?」
「「「メイベル!!」」」
その原因に気づかず、私は受け身を取ろうと体を半回転させる。このまま片足を前に出して踏ん張れば大丈夫、と思った矢先、スカートが足に絡まってできないことに気がついた。
あっ。いつも訓練ではズボンだったから……!
私は衝突に備えて目を瞑った。けれど痛みを感じない。地面ほどではないが、硬い何かに当たったような気がしたのだ。
恐る恐る目を開けると、そこには……。
「大丈夫か。怪我は?」
少しだけ息を切らせて私を覗く、赤い瞳があった。それがアリスター様だと気がつくのに数秒。
だって、私が倒れかけた時、アリスター様はお母様を挟んだ向こう側にいた。当然、間に合わない距離だった……はずなのに。
何も言わない私を余所に、アリスター様は肩や腕などに触れ、入念にチェックをする。その行為に私は勿論のこと、お母様もお兄様も何も言わない。
お陰でアリスター様に助けられたのだと気づいたのは、その逞しい腕に包まれた瞬間だった。
「はぁ~。良かった」
「!!」
頭上からかかる息に、体が反応する。羞恥なのか、それとも別の感情なのか分からなかったが、顔が一気に熱くなった。
すぐにここから離れないと、と思うのに体が動かない。もう少しこのまま、と思う気持ちの方が大きくて、アリスター様を押しのけられなかった。
けれど私の意思とは正反対に、体がアリスター様から離れていく。誰かが私の体を掴み、引っ張ったのだ。
「母上。メイベルはバランスを崩すほどお腹を空かせているようなので、すぐにダイニングへ連れて行こうと思います」
「え? あぁ、そうね。そうしなさい、エルバート」
混乱状態の私は、そうしてお兄様によってダイニングへ強制連行されたのだ。気がついた時には隣にクリフがいて、思わず一部始終を語っていた、というのが事の顛末だった。