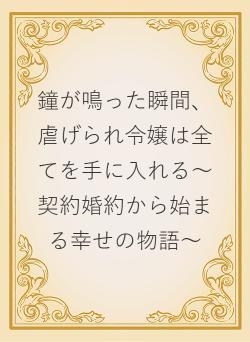十三年前。
成人まであと五年、という年齢に差し掛かった頃、突然「そろそろ首都で人脈作りに励め」という、難題を父親から突きつけられた。
その手始めに挑んだのが、ブレイズ公爵家だった。
将を射んと欲すればまず馬を射よ、という戦法があるが、そんなまどろっこしいことはせずに、俺は将を狙った。
これは辺境伯家という地位が、ベルリカーク帝国の中でも高いからこそ、できたものであって、ただの伯爵家だったら無理だろう。
ブレイズ公爵家に近づくことすらできなかったと思う。
それでもずっとエヴァレット辺境伯領にいた俺が成せたのは偏に、同じ騎士団を有する家門だったからだ。
「ちょっと参考にさせてもらいたいんだ」
「いいよ。逆にエヴァレット辺境伯家の騎士団が、どんな訓練をしているのか、教えてくれるのならね」
子ども同士の社交場も、バカにはできなかった。
後日、俺はブレイズ公爵家を訪れることになるわけだが……。そこで見たのは、騎士たちに交じって訓練をしている少女の姿だった。
「ブレイズ公爵家では、あのような幼子も訓練させるのか……」
凄いな、と感心していると、後ろからエルバートがやってきて、それを否定する。
「アレは真似事をしているだけだよ。体力作りにもなるから、誰も止めないけど」
「誰も、ってブレイズ公爵夫人もか?」
エルバートは初対面の時から、身分の低い俺が気安く話していても咎めない男だった。
「メイベルは寝起きが悪いんだ。睡眠をよく取っていないのも原因かもしれないからって、あぁして毎日熟睡できるように、体を動かしているんだとか」
「そんなに悪いのか、あんなことをさせるほど」
大人と一緒にいるからなのか、駆けている姿さえ可愛らしく見える。
「……見た目、可愛いだろう。母上に似ていても、皆、構いたがるんだ。特に昼寝をしている時は」
「確かに、ちょっかいをかけたくなるな」
「それで毎回、大騒ぎだ。ただ睨むだけならいいんだけど、俺たちを部屋から追い出すまで、物を投げ続けるんだよ」
「あの見た目でか?」
想像がつかないな、と思っていると、当のメイベル嬢が俺たちのところまでやって来た。
「メイベル。もういいのか。皆はまだ、走っているぞ」
「お客様に挨拶を、と思いまして。メイベル・ブレイズと申します」
ズボン姿であるため、少しだけ膝を折って挨拶をされた。すでにそこから醸し出す優雅さに、俺は驚いた。
こんな少女が、物を投げつける暴挙を?
「アリスター。メイベルが怖がっている」
まじまじと見過ぎたせいか、メイベル嬢はエルバートの後ろに隠れてしまった。
「すまない。その……疲れていないか」
「いつもやっていることなので、大丈夫……です」
「そうか。他には何をするんだ?」
「……腹筋とか腕立て伏せも、しています」
「は?」
確かに、騎士たちに交じって訓練しているが、何もそこまでしなくても。
この時の俺は、メイベル嬢の逆鱗に触れたとも知らずにただただ驚いていた。
「ランニングだって、腹筋だって、腕立て伏せだって、ちゃんとできます! 皆と同じにはできなくても、毎日やっているんだから!」
「あっ、待て、メイベル」
エルバートが制止する声も無視して、メイベル嬢は芝生の上に座り、仰向けになって腹筋のような仕草を始めた。
俺は近づき、手を差し伸べる。止めろと言ってもダメなのは分かっているから、和解の握手を求めたのだ。しかし、その裏の意図も読まれたのか、起き上がった瞬間に手を弾かれた。
「見くびらないでください!」
「アリスター。こういう場合、優しい行動は逆効果だよ」
「そしたらどうするんだ?」
「勿論」
俺たちの声を無視しているメイベル嬢に近づくエルバート。何をするのかと見守っていると、突然しゃがみ込み、そのままメイベル嬢の体を持ち上げた。
「無理やり止めるまでだよ」
そう口では言っているものの、優しくメイベル嬢を抱き上げる。さらに宥めるように背中を軽く叩いてまでいた。
何が「優しい行動は」だ。そっくりそのまま返してやりたかったが、今はエルバートに任せるしかない。
ご機嫌斜めなメイベル嬢に、何やら話しかけていたからだ。俺の耳には届かないほど、小さな声で。
いや、わざと聞かれないようにしているのだろう。メイベル嬢のために。
さっき言っていた「皆、構いたがる」中に、エルバートもいるのが手に取るように分かった。
「メイベル。ほら、約束しただろう。アリスターにちゃんと言うんだ」
恐らく謝罪だろう。俺は気にしていない。むしろこっちが悪いのだから、謝罪するべきなのは俺の方だ。
そう言おうとした瞬間、再度エルバートに催促されたメイベル嬢がこちらを振り向いた。
「っ!」
少しだけ泣いたのか、大きな目が濡れてキラキラと光っている。まるで海を閉じ込めたかのように。
「ごめんなさい」
俺は堪らず両手を伸ばし、エルバートからメイベル嬢を取ろうとした。その瞬間、バシッとまた手を叩かれた。
「メイベル! いや、これはアリスターの方か。まだ完全に機嫌を直したわけじゃないんだぞ」
「すまない。つい可愛らしくてな」
「……かわいい?」
俺の言葉に反応して、聞き返すメイベル嬢。まるで自分のこと? とでも言っているのか、その頭には、猫の耳がピンっと生えているように見えた。
勿論、錯覚なのだが、思わず撫でたくなるほどの可愛らしさだった。しかし、今度はその手をグッと下ろす。
折角、再び振り向いてくれたのに、台無しにはしたくなかったのだ。
「あぁ。とても」
その返事がお気に召したのか、メイベル嬢は俺に微笑みかけてくれた。欲望に負けず、手を伸ばさなくて良かった、とこの時ほど思うことはなかった。
成人まであと五年、という年齢に差し掛かった頃、突然「そろそろ首都で人脈作りに励め」という、難題を父親から突きつけられた。
その手始めに挑んだのが、ブレイズ公爵家だった。
将を射んと欲すればまず馬を射よ、という戦法があるが、そんなまどろっこしいことはせずに、俺は将を狙った。
これは辺境伯家という地位が、ベルリカーク帝国の中でも高いからこそ、できたものであって、ただの伯爵家だったら無理だろう。
ブレイズ公爵家に近づくことすらできなかったと思う。
それでもずっとエヴァレット辺境伯領にいた俺が成せたのは偏に、同じ騎士団を有する家門だったからだ。
「ちょっと参考にさせてもらいたいんだ」
「いいよ。逆にエヴァレット辺境伯家の騎士団が、どんな訓練をしているのか、教えてくれるのならね」
子ども同士の社交場も、バカにはできなかった。
後日、俺はブレイズ公爵家を訪れることになるわけだが……。そこで見たのは、騎士たちに交じって訓練をしている少女の姿だった。
「ブレイズ公爵家では、あのような幼子も訓練させるのか……」
凄いな、と感心していると、後ろからエルバートがやってきて、それを否定する。
「アレは真似事をしているだけだよ。体力作りにもなるから、誰も止めないけど」
「誰も、ってブレイズ公爵夫人もか?」
エルバートは初対面の時から、身分の低い俺が気安く話していても咎めない男だった。
「メイベルは寝起きが悪いんだ。睡眠をよく取っていないのも原因かもしれないからって、あぁして毎日熟睡できるように、体を動かしているんだとか」
「そんなに悪いのか、あんなことをさせるほど」
大人と一緒にいるからなのか、駆けている姿さえ可愛らしく見える。
「……見た目、可愛いだろう。母上に似ていても、皆、構いたがるんだ。特に昼寝をしている時は」
「確かに、ちょっかいをかけたくなるな」
「それで毎回、大騒ぎだ。ただ睨むだけならいいんだけど、俺たちを部屋から追い出すまで、物を投げ続けるんだよ」
「あの見た目でか?」
想像がつかないな、と思っていると、当のメイベル嬢が俺たちのところまでやって来た。
「メイベル。もういいのか。皆はまだ、走っているぞ」
「お客様に挨拶を、と思いまして。メイベル・ブレイズと申します」
ズボン姿であるため、少しだけ膝を折って挨拶をされた。すでにそこから醸し出す優雅さに、俺は驚いた。
こんな少女が、物を投げつける暴挙を?
「アリスター。メイベルが怖がっている」
まじまじと見過ぎたせいか、メイベル嬢はエルバートの後ろに隠れてしまった。
「すまない。その……疲れていないか」
「いつもやっていることなので、大丈夫……です」
「そうか。他には何をするんだ?」
「……腹筋とか腕立て伏せも、しています」
「は?」
確かに、騎士たちに交じって訓練しているが、何もそこまでしなくても。
この時の俺は、メイベル嬢の逆鱗に触れたとも知らずにただただ驚いていた。
「ランニングだって、腹筋だって、腕立て伏せだって、ちゃんとできます! 皆と同じにはできなくても、毎日やっているんだから!」
「あっ、待て、メイベル」
エルバートが制止する声も無視して、メイベル嬢は芝生の上に座り、仰向けになって腹筋のような仕草を始めた。
俺は近づき、手を差し伸べる。止めろと言ってもダメなのは分かっているから、和解の握手を求めたのだ。しかし、その裏の意図も読まれたのか、起き上がった瞬間に手を弾かれた。
「見くびらないでください!」
「アリスター。こういう場合、優しい行動は逆効果だよ」
「そしたらどうするんだ?」
「勿論」
俺たちの声を無視しているメイベル嬢に近づくエルバート。何をするのかと見守っていると、突然しゃがみ込み、そのままメイベル嬢の体を持ち上げた。
「無理やり止めるまでだよ」
そう口では言っているものの、優しくメイベル嬢を抱き上げる。さらに宥めるように背中を軽く叩いてまでいた。
何が「優しい行動は」だ。そっくりそのまま返してやりたかったが、今はエルバートに任せるしかない。
ご機嫌斜めなメイベル嬢に、何やら話しかけていたからだ。俺の耳には届かないほど、小さな声で。
いや、わざと聞かれないようにしているのだろう。メイベル嬢のために。
さっき言っていた「皆、構いたがる」中に、エルバートもいるのが手に取るように分かった。
「メイベル。ほら、約束しただろう。アリスターにちゃんと言うんだ」
恐らく謝罪だろう。俺は気にしていない。むしろこっちが悪いのだから、謝罪するべきなのは俺の方だ。
そう言おうとした瞬間、再度エルバートに催促されたメイベル嬢がこちらを振り向いた。
「っ!」
少しだけ泣いたのか、大きな目が濡れてキラキラと光っている。まるで海を閉じ込めたかのように。
「ごめんなさい」
俺は堪らず両手を伸ばし、エルバートからメイベル嬢を取ろうとした。その瞬間、バシッとまた手を叩かれた。
「メイベル! いや、これはアリスターの方か。まだ完全に機嫌を直したわけじゃないんだぞ」
「すまない。つい可愛らしくてな」
「……かわいい?」
俺の言葉に反応して、聞き返すメイベル嬢。まるで自分のこと? とでも言っているのか、その頭には、猫の耳がピンっと生えているように見えた。
勿論、錯覚なのだが、思わず撫でたくなるほどの可愛らしさだった。しかし、今度はその手をグッと下ろす。
折角、再び振り向いてくれたのに、台無しにはしたくなかったのだ。
「あぁ。とても」
その返事がお気に召したのか、メイベル嬢は俺に微笑みかけてくれた。欲望に負けず、手を伸ばさなくて良かった、とこの時ほど思うことはなかった。