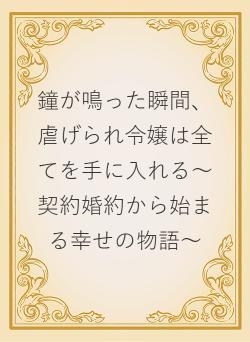「……ただいま戻りました」
一言も発しないお母様を前に、私はカーテシーをした。左手を、アリスター様の手のひらに重ねながら。
「メイベル。おかえりなさい」
返ってきたのは穏やかな声音だった。
予想外の出来事に、思わず私は顔を上げる。すると、先ほどの鋭い視線はどこへ行ったのか。口元は笑っているものの、目元には心配の色が見えた。
ここは駆け寄ってもいいのかな。甘えても――……。
その瞬間、腕を引っ張られた。あっという間に、アリスター様の手に添えていた左手が離れ、私の体は……。
「少し痩せたのではなくて?」
お母様の腕の中にいた。
「やっぱり食事のことも言わなければ分からないようね、あのクソガキは……」
「え?」
それは……バードランド皇子のこと、ですよね。アリスター様とか皇帝……いやいや、さすがにそこまでは。でも、お母様ならあり得る?
「ともかく、家に帰ってきたのだから、ちゃんとした食事を摂って、ゆっくりと体を休めなさい。いいわね」
「はい。でも、その前にお話したいことがあるのですが」
「それはあと。落ち着いてからでもできるでしょう?」
確かにそうなのだけれど、お母様の言う『あと』は私が想像する『あと』ではないような気がした。
「エルバート。メイベルをダイニングに連れて行きなさい。用意はさせてあるから」
「分かりました、母上。さぁ、メイベル」
いつの間にそこにいたのか、お兄様が立っていた。お父様譲りの青い髪が、二週間前よりも短髪になっている。
一体何があったのか、と思っていると、手を差し伸べられた。が、今はその手を取ることはできない。
私は振り返り、お母様を呼ぼうとした途端、問答無用で背中を押されてしまった。
すかさずお兄様は私を引き寄せる。そうしなければ、無様にもこの場で倒れてしまいそうだったからだ。
さすがにアリスター様の前でそのような醜態は晒せない。
「ありがとうございます」
お兄様にお礼を言うも、内心は冷や汗ものだった。それはどうやら、私だけではなかったらしい。
「相変わらず、目的のためなら手段を選ばない人だなぁ。本当にメイベルが転んだらどうするんですか?」
「あら、私は貴方をそんなやわな人間に育てたわけではないはずよ。それくらいカバーできなければ公爵は名乗れなくてよ」
何を根拠に……、と思わず言いたくなった言葉を胸に仕舞った。今は反論するところじゃない。私の本能がそう言っていた。それはお兄様もまた同じようだった。
「はいはい。そんなわけだから、メイベル。大人しく言うことを聞いてくれるよな」
「……はい」
けれど私は後ろを振り返った。案の定、お母様の瞳が再び鋭くなっていた。相手は勿論……。
「心配かい? アリスターが」
「お母様はどなたに対しても容赦がないですから。特に今回は」
「そうだね。でも、アリスターだって覚悟の上さ。わざわざ嵌めた相手の親に会うんだから」
確かに、と眺めること数秒。お母様が強い口調で何かを指摘したのか、アリスター様はタジタジになっていた。
「ふふふっ。あの姿を見ていると、到底私を嵌めた方とは思えませんね」
「その言葉、そのままメイベルに返すよ。一喜一憂して、まさかもう絆されたのか?」
「なっ! ありえませんわ!」
一気に顔が熱くなるのを感じたが、口から出たのは否定の言葉だった。何故か軽い女だと非難されたように感じたせいだろう。お兄様に他意はなくても。
「本当にお前は母上に似て素直じゃないな。まぁ、アリスターも同じだから、これはこれでいいのか」
お兄様はそういうと、私の頭を撫でた。
***
二週間振りに帰ってきた我が家。
あのような形で婚約破棄された挙げ句、牢屋に入れられた公爵令嬢だというのに、屋敷の雰囲気はとても温かかった。
今まではあまり気にならなかった使用人たちの視線を感じ、そっと盗み見る。すると、安堵の表情をしている者たちばかりが目に入った。
「お兄様。この二週間、我が家はどのような感じだったのですか?」
エントランスを抜け、廊下を歩き始めること数分。私は率直な疑問を投げかけた。何せ、今度はすすり泣く声まで聞こえ出したからだ。
本当に一体、何が……?
「聞きたいか? そうかそうか。まぁ、気になるよな。メイベルも大変だったように、我が家も大変だったからな」
「お、お兄様!? 無理にとは言いません。思い出したくないのであれば余計にっ!」
「いいから聞け」
「はい」
おちゃらけたのかと思えば次の瞬間、圧をかけてくる。お兄様こそ、お母様に似ているのでは? と思わざるを得なかった。
いや、次期ブレイズ公爵となるべく、お母様から直々に習ったのかもしれない。それだけお兄様への期待と教育を、惜しみなく注いでいたからだ。
「そもそも、メイベルが謝罪に行くことを、母上が反対していたことは知っていたか?」
「え? いいえ。ただお父様から行けと言われただけで、お母様からは……」
説教の嵐だった。
『だからあれほど、寝起きを良くしなさいと言ったでしょう! 早めに寝るなり、寝具は……色々やったわね。あとは、睡眠の質を良くしたり、時間を決めたりできたでしょうが!』
思い出しただけでも、ため息を吐きそうになった。
「お前に説教をした後、ようやく頭が冷えたんだろうな。今度はバードランドの所業に再び血が上ったんだ」
『あのクソガキ。断りもなくメイベルの部屋に、しかも朝方! あの子が起きていないことくらい分かるでしょう! これは卑怯ではなくて! 姑息よ! 一国の皇子のやることなの!? 再教育……いえ、廃嫡まで追い込まなければ気がすまないわ』
「もう皇帝の胸ぐらを掴みに行くんじゃないかとヒヤヒヤしたものさ」
やっぱりあの『クソガキ』はバードランド皇子のことだったのね。
「けれど、会いに行ったのですよね。それもバードランド皇子に」
「そうしないと我が家の雰囲気は最悪。鬱憤を晴らさないと、何をしでかすのか分からなかったんだ。一応、俺も同席するから、と頼み込んでな」
「……ということは!」
アリスター様も危ないのでは!?
私は踵を返し、駆け出そうとした。が、お兄様に腕を掴まれた。ふと、その感触に私は動きを止める。
「どうした? そんなに強く掴んでいないだろう? それでも痛かったか?」
「いえ、痛くはないです。ただ……」
「……またアリスターのことか? それなら大丈夫だって言っただろう?」
「えっと、上手く言えないんですが……同じ男の人なのに、違うなって思って」
お兄様も剣を扱うけれど、アリスター様ほどゴツゴツしていない。何が違うのかしら。
「……俺もメイベルと一緒に玄関に行こうかな」
「え? 行ってもいいんですか?」
「うん。俺もアリスターに用事ができたから」
何だろう。行っていいという許可を得たのは嬉しいものの、お兄様を行かせてはいけないような、そんな気がした。
一言も発しないお母様を前に、私はカーテシーをした。左手を、アリスター様の手のひらに重ねながら。
「メイベル。おかえりなさい」
返ってきたのは穏やかな声音だった。
予想外の出来事に、思わず私は顔を上げる。すると、先ほどの鋭い視線はどこへ行ったのか。口元は笑っているものの、目元には心配の色が見えた。
ここは駆け寄ってもいいのかな。甘えても――……。
その瞬間、腕を引っ張られた。あっという間に、アリスター様の手に添えていた左手が離れ、私の体は……。
「少し痩せたのではなくて?」
お母様の腕の中にいた。
「やっぱり食事のことも言わなければ分からないようね、あのクソガキは……」
「え?」
それは……バードランド皇子のこと、ですよね。アリスター様とか皇帝……いやいや、さすがにそこまでは。でも、お母様ならあり得る?
「ともかく、家に帰ってきたのだから、ちゃんとした食事を摂って、ゆっくりと体を休めなさい。いいわね」
「はい。でも、その前にお話したいことがあるのですが」
「それはあと。落ち着いてからでもできるでしょう?」
確かにそうなのだけれど、お母様の言う『あと』は私が想像する『あと』ではないような気がした。
「エルバート。メイベルをダイニングに連れて行きなさい。用意はさせてあるから」
「分かりました、母上。さぁ、メイベル」
いつの間にそこにいたのか、お兄様が立っていた。お父様譲りの青い髪が、二週間前よりも短髪になっている。
一体何があったのか、と思っていると、手を差し伸べられた。が、今はその手を取ることはできない。
私は振り返り、お母様を呼ぼうとした途端、問答無用で背中を押されてしまった。
すかさずお兄様は私を引き寄せる。そうしなければ、無様にもこの場で倒れてしまいそうだったからだ。
さすがにアリスター様の前でそのような醜態は晒せない。
「ありがとうございます」
お兄様にお礼を言うも、内心は冷や汗ものだった。それはどうやら、私だけではなかったらしい。
「相変わらず、目的のためなら手段を選ばない人だなぁ。本当にメイベルが転んだらどうするんですか?」
「あら、私は貴方をそんなやわな人間に育てたわけではないはずよ。それくらいカバーできなければ公爵は名乗れなくてよ」
何を根拠に……、と思わず言いたくなった言葉を胸に仕舞った。今は反論するところじゃない。私の本能がそう言っていた。それはお兄様もまた同じようだった。
「はいはい。そんなわけだから、メイベル。大人しく言うことを聞いてくれるよな」
「……はい」
けれど私は後ろを振り返った。案の定、お母様の瞳が再び鋭くなっていた。相手は勿論……。
「心配かい? アリスターが」
「お母様はどなたに対しても容赦がないですから。特に今回は」
「そうだね。でも、アリスターだって覚悟の上さ。わざわざ嵌めた相手の親に会うんだから」
確かに、と眺めること数秒。お母様が強い口調で何かを指摘したのか、アリスター様はタジタジになっていた。
「ふふふっ。あの姿を見ていると、到底私を嵌めた方とは思えませんね」
「その言葉、そのままメイベルに返すよ。一喜一憂して、まさかもう絆されたのか?」
「なっ! ありえませんわ!」
一気に顔が熱くなるのを感じたが、口から出たのは否定の言葉だった。何故か軽い女だと非難されたように感じたせいだろう。お兄様に他意はなくても。
「本当にお前は母上に似て素直じゃないな。まぁ、アリスターも同じだから、これはこれでいいのか」
お兄様はそういうと、私の頭を撫でた。
***
二週間振りに帰ってきた我が家。
あのような形で婚約破棄された挙げ句、牢屋に入れられた公爵令嬢だというのに、屋敷の雰囲気はとても温かかった。
今まではあまり気にならなかった使用人たちの視線を感じ、そっと盗み見る。すると、安堵の表情をしている者たちばかりが目に入った。
「お兄様。この二週間、我が家はどのような感じだったのですか?」
エントランスを抜け、廊下を歩き始めること数分。私は率直な疑問を投げかけた。何せ、今度はすすり泣く声まで聞こえ出したからだ。
本当に一体、何が……?
「聞きたいか? そうかそうか。まぁ、気になるよな。メイベルも大変だったように、我が家も大変だったからな」
「お、お兄様!? 無理にとは言いません。思い出したくないのであれば余計にっ!」
「いいから聞け」
「はい」
おちゃらけたのかと思えば次の瞬間、圧をかけてくる。お兄様こそ、お母様に似ているのでは? と思わざるを得なかった。
いや、次期ブレイズ公爵となるべく、お母様から直々に習ったのかもしれない。それだけお兄様への期待と教育を、惜しみなく注いでいたからだ。
「そもそも、メイベルが謝罪に行くことを、母上が反対していたことは知っていたか?」
「え? いいえ。ただお父様から行けと言われただけで、お母様からは……」
説教の嵐だった。
『だからあれほど、寝起きを良くしなさいと言ったでしょう! 早めに寝るなり、寝具は……色々やったわね。あとは、睡眠の質を良くしたり、時間を決めたりできたでしょうが!』
思い出しただけでも、ため息を吐きそうになった。
「お前に説教をした後、ようやく頭が冷えたんだろうな。今度はバードランドの所業に再び血が上ったんだ」
『あのクソガキ。断りもなくメイベルの部屋に、しかも朝方! あの子が起きていないことくらい分かるでしょう! これは卑怯ではなくて! 姑息よ! 一国の皇子のやることなの!? 再教育……いえ、廃嫡まで追い込まなければ気がすまないわ』
「もう皇帝の胸ぐらを掴みに行くんじゃないかとヒヤヒヤしたものさ」
やっぱりあの『クソガキ』はバードランド皇子のことだったのね。
「けれど、会いに行ったのですよね。それもバードランド皇子に」
「そうしないと我が家の雰囲気は最悪。鬱憤を晴らさないと、何をしでかすのか分からなかったんだ。一応、俺も同席するから、と頼み込んでな」
「……ということは!」
アリスター様も危ないのでは!?
私は踵を返し、駆け出そうとした。が、お兄様に腕を掴まれた。ふと、その感触に私は動きを止める。
「どうした? そんなに強く掴んでいないだろう? それでも痛かったか?」
「いえ、痛くはないです。ただ……」
「……またアリスターのことか? それなら大丈夫だって言っただろう?」
「えっと、上手く言えないんですが……同じ男の人なのに、違うなって思って」
お兄様も剣を扱うけれど、アリスター様ほどゴツゴツしていない。何が違うのかしら。
「……俺もメイベルと一緒に玄関に行こうかな」
「え? 行ってもいいんですか?」
「うん。俺もアリスターに用事ができたから」
何だろう。行っていいという許可を得たのは嬉しいものの、お兄様を行かせてはいけないような、そんな気がした。