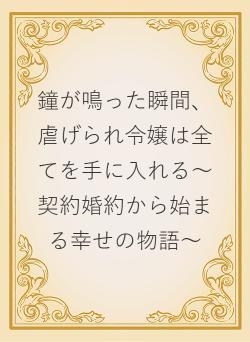実は不安要素はまだまだあった。それは牢屋から出た後のこと。私の帰る場所だった。
「ブレイズ公爵家に帰るしかあるまい」
二週間後、矢継ぎ早に行われた婚約破棄の手続きの後、釈放を告げに来たのは他でもない、アリスター様だった。
契約結婚を申し込まれたあの日から、私を退屈させないようにと、毎日顔を出しに来てくれていたのだ。
表向きはそう言っているが、本当は多分、私の心変わりを心配しているのだろう。バードランド皇子にでも聞いたのか、差し入れはどれも、私の好きな物ばかりだったからだ。
これじゃ益々、私と結婚したいためにバードランド皇子に助言した、といっているようなものだ。いや、すでに勘づかれているから、開き直っているのかもしれない。
だから私も、つい弱音を吐いてしまった。
「首都にある、アリスター様のお屋敷ではダメなのですか?」
婚約破棄の手続きを終えたからといって、本来ならばすぐに次、というわけにはいかない。
しかし、そこにバードランド皇子が介入しているかいないかで変わる。何せ、貴族の婚姻は、皇帝の承認が必要だったからだ。
バードランド皇子が皇帝に頼んでくれたお陰で、今の私はアリスター様の婚約者、ということになっている。
まぁそれが釈放の一番の理由になっているのだから、当然と言えば当然のことだった。
「ブレイズ公爵邸に帰った方と、帰らなかった方。どっちが穏便に済むか、分かって言っているのか?」
「……すみません。どちらにしても、アリスター様に迷惑がかかることなのに。後者を選べばさらに厄介なことになってしまいますよね」
潔癖なお母様のことだ。私だけでなく、アリスター様に対しても容赦なく怒るに違いない。そればかりか、評価もガタ落ち。
下手したら婚約を白紙に戻され、公爵邸から一歩も外に出してもらえなくなる可能性も大いにあった。
「いや、俺の方は構わない。メイベル嬢の言う通りどっちに転んでも、怒ったブレイズ公爵夫人との対面は免れないからな」
「そんな悠長なことを言わないでください。後者だった場合は、アリスター様も叱られるんですよ。あっ、前者でもバードランド皇子との謀がバレていたら……結局は同じことが……」
「言わなかったか? 俺は気が強い女が好きだと」
「え? あれは方便なんだとばかり……。もしかしてアリスター様は、お母様みたいな女性がタイプなんですか?」
物好きですね、と続けて言おうとした言葉を呑み込んだ。今の私は、誰がどう見ても弱腰だ。アリスター様のタイプからかけ離れている。
ダメよ。このままアリスター様に嫌われてしまったら、私の未来さえも完全に閉ざされてしまう。今の私はまさに、前門の虎後門の狼なのだから。
私はギュッと拳を握り締めた。
「さぁな。ブレイズ公爵夫人とは、もう十数年も会っていないから、そうだとはさすがに言いきれん」
「……では、会うのを楽しみにしています?」
「いや、どちらかというと緊張している。何せ俺はバードランド皇子を唆した挙げ句、メイベル嬢の名誉を傷つけたわけだからな。俺も同じく怒られる側だ」
まるで私の危惧を察したかのように話題を元に戻された。けれど、それに安心している自分もいる。
何せ私は、性格だけでなく、顔までもお母様に似ていたからだ。
***
エヴァレット辺境伯家の馬車でブレイズ公爵邸に近づくと、扉の前で仁王立ちしているお母様の姿が目に入った。
私と同じピンク色の髪が、僅かだがその威厳を和らげてくれていた。が、そこから覗く青い瞳は、光っているのかと思うほど鋭かった。
「アリスター様……」
あまりの恐怖に、私は向かい側に座っているアリスター様の名前を呼んだ。さっきまで、嫌われないために強気な姿を、と思っていたことなど忘れたかのように、弱気な声で。
するとアリスター様は立ち上がり、そっと私の隣へやってくる。
「大丈夫だ。まぁ、危ないと思ったら俺の名前を出して、盾にでも何でも好きに使え」
いいな、と頭を撫でられた。子ども扱いされているように感じたが、今はそれが心強かった。
アリスター様によって、この状況が引き起こされたことも忘れてしまうほどに。
馬の嘶きと共に止まる馬車。御者が扉を開ける前に外へ出るアリスター様。それを眺めているであろう、お母様の姿も容易に想像ができた。
お父様の浮気相手を見て「このような方に公爵夫人の仕事が務まりまして? 領地経営も含めて、誰がしていたと思っているんですか?」と言い放った御仁だ。
さらに自分がいなくなった後、ブレイズ公爵家の損害がどれくらいかを述べた挙げ句、「我が公爵家に必要のない者が出て行くべきですわ」とお父様を追い出そうとしたのだ。
すでにお兄様がいたため、公爵家の血が絶えることはない。
このような事態を予め想定していたかのような動きを見せたお母様のことだ。
私が牢屋に入れられた経緯。アリスター様との婚約……はお父様の許可が必要だから、勿論知っているだろう。さらにこれが誰によって仕組まれたことも。
「メイベル嬢」
恐らく、お母様の突き刺さる視線を受けている、であろうアリスター様は、それを物ともせずに手を差し出した。
私は立ち上がり、その手を取る。
大きくて分厚い、ゴツゴツした手。それは辺境の地で、常に魔物や他国からの侵略を防ぐために戦ってくれていた証でもあった。
思わず先ほどのアリスター様の言葉を思い浮かべる。
確かに、歴戦の戦士からすれば、お母様の視線など、可愛いものかもしれない。
そう思ったら、自然とアリスター様に笑いかけていた。
「ブレイズ公爵家に帰るしかあるまい」
二週間後、矢継ぎ早に行われた婚約破棄の手続きの後、釈放を告げに来たのは他でもない、アリスター様だった。
契約結婚を申し込まれたあの日から、私を退屈させないようにと、毎日顔を出しに来てくれていたのだ。
表向きはそう言っているが、本当は多分、私の心変わりを心配しているのだろう。バードランド皇子にでも聞いたのか、差し入れはどれも、私の好きな物ばかりだったからだ。
これじゃ益々、私と結婚したいためにバードランド皇子に助言した、といっているようなものだ。いや、すでに勘づかれているから、開き直っているのかもしれない。
だから私も、つい弱音を吐いてしまった。
「首都にある、アリスター様のお屋敷ではダメなのですか?」
婚約破棄の手続きを終えたからといって、本来ならばすぐに次、というわけにはいかない。
しかし、そこにバードランド皇子が介入しているかいないかで変わる。何せ、貴族の婚姻は、皇帝の承認が必要だったからだ。
バードランド皇子が皇帝に頼んでくれたお陰で、今の私はアリスター様の婚約者、ということになっている。
まぁそれが釈放の一番の理由になっているのだから、当然と言えば当然のことだった。
「ブレイズ公爵邸に帰った方と、帰らなかった方。どっちが穏便に済むか、分かって言っているのか?」
「……すみません。どちらにしても、アリスター様に迷惑がかかることなのに。後者を選べばさらに厄介なことになってしまいますよね」
潔癖なお母様のことだ。私だけでなく、アリスター様に対しても容赦なく怒るに違いない。そればかりか、評価もガタ落ち。
下手したら婚約を白紙に戻され、公爵邸から一歩も外に出してもらえなくなる可能性も大いにあった。
「いや、俺の方は構わない。メイベル嬢の言う通りどっちに転んでも、怒ったブレイズ公爵夫人との対面は免れないからな」
「そんな悠長なことを言わないでください。後者だった場合は、アリスター様も叱られるんですよ。あっ、前者でもバードランド皇子との謀がバレていたら……結局は同じことが……」
「言わなかったか? 俺は気が強い女が好きだと」
「え? あれは方便なんだとばかり……。もしかしてアリスター様は、お母様みたいな女性がタイプなんですか?」
物好きですね、と続けて言おうとした言葉を呑み込んだ。今の私は、誰がどう見ても弱腰だ。アリスター様のタイプからかけ離れている。
ダメよ。このままアリスター様に嫌われてしまったら、私の未来さえも完全に閉ざされてしまう。今の私はまさに、前門の虎後門の狼なのだから。
私はギュッと拳を握り締めた。
「さぁな。ブレイズ公爵夫人とは、もう十数年も会っていないから、そうだとはさすがに言いきれん」
「……では、会うのを楽しみにしています?」
「いや、どちらかというと緊張している。何せ俺はバードランド皇子を唆した挙げ句、メイベル嬢の名誉を傷つけたわけだからな。俺も同じく怒られる側だ」
まるで私の危惧を察したかのように話題を元に戻された。けれど、それに安心している自分もいる。
何せ私は、性格だけでなく、顔までもお母様に似ていたからだ。
***
エヴァレット辺境伯家の馬車でブレイズ公爵邸に近づくと、扉の前で仁王立ちしているお母様の姿が目に入った。
私と同じピンク色の髪が、僅かだがその威厳を和らげてくれていた。が、そこから覗く青い瞳は、光っているのかと思うほど鋭かった。
「アリスター様……」
あまりの恐怖に、私は向かい側に座っているアリスター様の名前を呼んだ。さっきまで、嫌われないために強気な姿を、と思っていたことなど忘れたかのように、弱気な声で。
するとアリスター様は立ち上がり、そっと私の隣へやってくる。
「大丈夫だ。まぁ、危ないと思ったら俺の名前を出して、盾にでも何でも好きに使え」
いいな、と頭を撫でられた。子ども扱いされているように感じたが、今はそれが心強かった。
アリスター様によって、この状況が引き起こされたことも忘れてしまうほどに。
馬の嘶きと共に止まる馬車。御者が扉を開ける前に外へ出るアリスター様。それを眺めているであろう、お母様の姿も容易に想像ができた。
お父様の浮気相手を見て「このような方に公爵夫人の仕事が務まりまして? 領地経営も含めて、誰がしていたと思っているんですか?」と言い放った御仁だ。
さらに自分がいなくなった後、ブレイズ公爵家の損害がどれくらいかを述べた挙げ句、「我が公爵家に必要のない者が出て行くべきですわ」とお父様を追い出そうとしたのだ。
すでにお兄様がいたため、公爵家の血が絶えることはない。
このような事態を予め想定していたかのような動きを見せたお母様のことだ。
私が牢屋に入れられた経緯。アリスター様との婚約……はお父様の許可が必要だから、勿論知っているだろう。さらにこれが誰によって仕組まれたことも。
「メイベル嬢」
恐らく、お母様の突き刺さる視線を受けている、であろうアリスター様は、それを物ともせずに手を差し出した。
私は立ち上がり、その手を取る。
大きくて分厚い、ゴツゴツした手。それは辺境の地で、常に魔物や他国からの侵略を防ぐために戦ってくれていた証でもあった。
思わず先ほどのアリスター様の言葉を思い浮かべる。
確かに、歴戦の戦士からすれば、お母様の視線など、可愛いものかもしれない。
そう思ったら、自然とアリスター様に笑いかけていた。