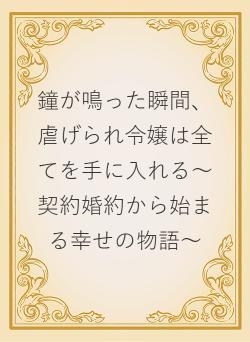ベルリカーク帝国の首都の中で、皇城を除いて一番広大な敷地を有しているのが、ブレイズ公爵家。
その裏手には、小高い丘があった。登り切らなければ、反対側が一面、森になっていることなど、誰も思わないだろう。敢えて、そういう造りにしていた。
森の中には、ブレイズ公爵家に代々仕えてくれた者たちの墓が、隠れるようにして建てられているのだ。
死しても尚、公爵邸の近くに。公爵家もまた、荒らされないために管理している。そんな、ほぼ私有地に近い丘だった。
森に入る手前、山でいうところの頂に、目的地であるガゼボがある。
空の青と下に広がる緑に挟まれた、白い八角形の建物。半年以上も首都を離れていたのにもかかわらず、変わらぬ優美さを保っていた。
思わず駆け寄りたくなったが、私ももう子どもではない。この美しいガゼボに似合う女性でありたい。そう思うだけで背筋が伸びるようだった。
「旦那様」
同じように、ガゼボに見惚れていたアリスター様の腕を引っ張る。
「そうだな。休憩にするか」
「はい。と言いたいところですが、ここに来たかったんです。旦那様と。ですから参りましょう」
「あ、あぁ」
どうやら、ここに連れて来られた理由をまだ分かっていないらしい。察しのいいアリスター様にしては珍しかった。
いや、どちらかというと、私の心配をしつつ思案していた、というところだろうか。けれどまだ、答えを導き出せていないらしい。
私が満面の笑みで腕を引かれていても、アリスター様はただただ困惑していたからだ。
「ふふふっ。たまにはこういうのもいいですね。どうですか? そろそろ思い出してくれましたか?」
「それは意趣返しのつもりか?」
「どうでしょう。たった一カ月くらい前のことを憶えていないのに、十三年前のことを憶えていなかった私に対して、拗ねるような真似をした旦那様ほどではありませんよ?」
「やはり仕返しではないか」
私は軽い足取りで、ガゼボの中に入った。
冬を迎え、落ち葉が充満しているのかと思ったが、足元にあるのは数十枚程度。ベンチにも、さっきここにやって来ました、と謂わんばかりの落ち葉しかなかった。
私はその一枚を手に取る。
よく管理されているから、このまま座っても大丈夫、と思ったが、そこは紳士というか、過保護な旦那様。
すかさず、私が座ろうとした場所を掃いて、ハンカチを置く徹底ぶりだった。
多分、汚れていないと言っても無理なのだろう。私は感謝の言葉を述べて、腰を下ろした。
「では、ヒントを差し上げます。私もいただいたので」
そう言って左手を顔の高さにまで上げた。手のひらを自分の方に向けて。それでも分からないアリスター様に、さらなるヒントを口にする。
「私の妊娠で、挙式のやり直しはもう無理ですが、それでもお言葉だけはほしいんです。勿論、指輪はすでにいただいているので、大丈夫です」
何せ私の我が儘で、急遽このような場面に直面したのだ。用意している方がおかしかった。その配慮で言ったつもりだったのに、アリスター様は懐からある物を取り出す。
「いや、物は領地を出る前に用意していたんだ」
「えっ? えっ? でしたら何故、気づいてくださらなかったんですか?」
今度は私が戸惑う番だった。
「俺も気持ちに余裕がなかったんだ。メイベルのように体に変化があるわけでもない。しかし、父親になる覚悟をいざ目の前に置かれると……」
「お母様に何か言われたんですか?」
「どちらかというと、その姿を見て、俺もあぁしてメイベルを支えねばと思ったんだ」
十分、支えてもらっている。けれど、アリスター様の言葉からは、お世話とか過保護の意味が含まれているように感じた。気の所為だろうか。
「それに、こっそりやろうとしても、俺は首都に明るくなくてな。部屋でやれば、メイベルを抱き兼ねないのもあって。式については俺もやり直したいと思っていたから、メイベルも同じ思いだと知って嬉しかった」
「あっ、ずっと部屋にいたから、それで……」
式についても、確かに話し合っていなかった。私はただ、そうなればな、と思っていただけなのに、話し合ったつもりになっていたなんて……!
「しかし、前もって用意しておいて良かった。それも指輪以外の物を」
アリスター様はそう言うと、長方形の箱からネックレスを取り出した。
「これはアネモネですか? それも赤い……」
「あぁ、メイベルの部屋のカーテンの柄にもあったから、好きなのかと思ったんだが……違ったか?」
「いいえ。考えてみると、私も旦那様の好みを知りません。好きな色や好きな花。好きな場所は知っていますが」
それに赤いアネモネの花言葉は「君を愛す」という意味が込められている。
「ガーラナウム城の展望台。だから、私も好きな場所に旦那様を連れて行きたかったんです。好きな場所で、好きな人に――……」
「その先は俺に言わせてくれ」
「……はい」
「だがその前にこれを……」
赤いアネモネのネックレスを、私の首に着けてくれた。それも前から、屈むようにして。私は着けやすいように髪を横に寄せた。
「メイベル」
座る私の前で跪き、右手を取る。すでに婚姻は済ませているのに、アリスター様の顔は真剣そのものだった。僅かに震える手から、緊張が伝わってくる。
「契約結婚を持ち掛けた時は、何もしなくていいと言ったが、今もその気持ちは変わらない」
「ありがとうございます。けれど私も旦那様や領民のために、何かしたいんです」
「分かっている。メイベルの決意に俺も賛成だ。全力でサポートをする。だから……」
アリスター様は一度口を閉じ、私を見つめる。懇願するような眼差しに胸が締めつけられた。
「俺の傍にいて欲しい。ずっと、一生を懸けて守ると誓う」
「私もです。ずっとお傍にいさせてください」
「あぁ」
最後の返事は、聞き取れないくらい小さな声だった。しかし、唇がすぐに触れてしまうほどの距離だったため、ハッキリと私の耳に届いた。
その裏手には、小高い丘があった。登り切らなければ、反対側が一面、森になっていることなど、誰も思わないだろう。敢えて、そういう造りにしていた。
森の中には、ブレイズ公爵家に代々仕えてくれた者たちの墓が、隠れるようにして建てられているのだ。
死しても尚、公爵邸の近くに。公爵家もまた、荒らされないために管理している。そんな、ほぼ私有地に近い丘だった。
森に入る手前、山でいうところの頂に、目的地であるガゼボがある。
空の青と下に広がる緑に挟まれた、白い八角形の建物。半年以上も首都を離れていたのにもかかわらず、変わらぬ優美さを保っていた。
思わず駆け寄りたくなったが、私ももう子どもではない。この美しいガゼボに似合う女性でありたい。そう思うだけで背筋が伸びるようだった。
「旦那様」
同じように、ガゼボに見惚れていたアリスター様の腕を引っ張る。
「そうだな。休憩にするか」
「はい。と言いたいところですが、ここに来たかったんです。旦那様と。ですから参りましょう」
「あ、あぁ」
どうやら、ここに連れて来られた理由をまだ分かっていないらしい。察しのいいアリスター様にしては珍しかった。
いや、どちらかというと、私の心配をしつつ思案していた、というところだろうか。けれどまだ、答えを導き出せていないらしい。
私が満面の笑みで腕を引かれていても、アリスター様はただただ困惑していたからだ。
「ふふふっ。たまにはこういうのもいいですね。どうですか? そろそろ思い出してくれましたか?」
「それは意趣返しのつもりか?」
「どうでしょう。たった一カ月くらい前のことを憶えていないのに、十三年前のことを憶えていなかった私に対して、拗ねるような真似をした旦那様ほどではありませんよ?」
「やはり仕返しではないか」
私は軽い足取りで、ガゼボの中に入った。
冬を迎え、落ち葉が充満しているのかと思ったが、足元にあるのは数十枚程度。ベンチにも、さっきここにやって来ました、と謂わんばかりの落ち葉しかなかった。
私はその一枚を手に取る。
よく管理されているから、このまま座っても大丈夫、と思ったが、そこは紳士というか、過保護な旦那様。
すかさず、私が座ろうとした場所を掃いて、ハンカチを置く徹底ぶりだった。
多分、汚れていないと言っても無理なのだろう。私は感謝の言葉を述べて、腰を下ろした。
「では、ヒントを差し上げます。私もいただいたので」
そう言って左手を顔の高さにまで上げた。手のひらを自分の方に向けて。それでも分からないアリスター様に、さらなるヒントを口にする。
「私の妊娠で、挙式のやり直しはもう無理ですが、それでもお言葉だけはほしいんです。勿論、指輪はすでにいただいているので、大丈夫です」
何せ私の我が儘で、急遽このような場面に直面したのだ。用意している方がおかしかった。その配慮で言ったつもりだったのに、アリスター様は懐からある物を取り出す。
「いや、物は領地を出る前に用意していたんだ」
「えっ? えっ? でしたら何故、気づいてくださらなかったんですか?」
今度は私が戸惑う番だった。
「俺も気持ちに余裕がなかったんだ。メイベルのように体に変化があるわけでもない。しかし、父親になる覚悟をいざ目の前に置かれると……」
「お母様に何か言われたんですか?」
「どちらかというと、その姿を見て、俺もあぁしてメイベルを支えねばと思ったんだ」
十分、支えてもらっている。けれど、アリスター様の言葉からは、お世話とか過保護の意味が含まれているように感じた。気の所為だろうか。
「それに、こっそりやろうとしても、俺は首都に明るくなくてな。部屋でやれば、メイベルを抱き兼ねないのもあって。式については俺もやり直したいと思っていたから、メイベルも同じ思いだと知って嬉しかった」
「あっ、ずっと部屋にいたから、それで……」
式についても、確かに話し合っていなかった。私はただ、そうなればな、と思っていただけなのに、話し合ったつもりになっていたなんて……!
「しかし、前もって用意しておいて良かった。それも指輪以外の物を」
アリスター様はそう言うと、長方形の箱からネックレスを取り出した。
「これはアネモネですか? それも赤い……」
「あぁ、メイベルの部屋のカーテンの柄にもあったから、好きなのかと思ったんだが……違ったか?」
「いいえ。考えてみると、私も旦那様の好みを知りません。好きな色や好きな花。好きな場所は知っていますが」
それに赤いアネモネの花言葉は「君を愛す」という意味が込められている。
「ガーラナウム城の展望台。だから、私も好きな場所に旦那様を連れて行きたかったんです。好きな場所で、好きな人に――……」
「その先は俺に言わせてくれ」
「……はい」
「だがその前にこれを……」
赤いアネモネのネックレスを、私の首に着けてくれた。それも前から、屈むようにして。私は着けやすいように髪を横に寄せた。
「メイベル」
座る私の前で跪き、右手を取る。すでに婚姻は済ませているのに、アリスター様の顔は真剣そのものだった。僅かに震える手から、緊張が伝わってくる。
「契約結婚を持ち掛けた時は、何もしなくていいと言ったが、今もその気持ちは変わらない」
「ありがとうございます。けれど私も旦那様や領民のために、何かしたいんです」
「分かっている。メイベルの決意に俺も賛成だ。全力でサポートをする。だから……」
アリスター様は一度口を閉じ、私を見つめる。懇願するような眼差しに胸が締めつけられた。
「俺の傍にいて欲しい。ずっと、一生を懸けて守ると誓う」
「私もです。ずっとお傍にいさせてください」
「あぁ」
最後の返事は、聞き取れないくらい小さな声だった。しかし、唇がすぐに触れてしまうほどの距離だったため、ハッキリと私の耳に届いた。