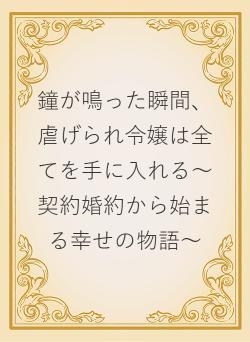「引き受けてくれたのは嬉しいけど、乱暴な真似はダメよ! 聖女を教会に返すだけでいいんだからね」
「分かっているよ。罪人とはいえ、聖女様だからね。姉様の意図だって分かっているつもりだよ」
「そ、そう?」
本当かしら、と疑心の眼差しを、つい向けてしまう。それもまた、クリフにはお見通しだった。
「でも、姉様は優し過ぎるよ。何で恩情を与えるの? 一応エヴァレット辺境伯領の騎士団に所属していたんだから、領主夫人の殺害未遂は見逃せない案件だよ? しかも、姉様は聖女に対して嫌がらせも何もしていない、と言うじゃないか。それなのに……」
「確かに嫌がらせというか、接点そのものがあまりなかったんだけど……。それでも、彼女があぁなってしまったのは、私が原因でしょう。だから、皇后様にお願いしてほしいの。向こうにも責任はあるのだから」
「……間接的でしかないのに? 姉様に当たるのはお門違いの勘違い女じゃないか」
どうしよう。アリスター様と同じようなことを言われてしまった。
そんなに私の提案はおかしいのかな。
「それでも! 聖女という存在を簡単に手離してはいけない気がするの。ほら、国民にとってもね。私が原因で力を失くしたなんて知られたら、非難が向くと思わない?」
「そ、それは……そうかも。あの女のせいで、姉様がさらに被害を受けるのは、勘弁してほしいかな。さすがにそんなことがあったら……」
「えっと、だからね、クリフ。教会にシオドーラを引き取らせてほしいの。聖女の力を戻すように、と皇后様が命じれば、教会も断れないでしょう。今は罪人になっているけど、戻せば聖女だと皇帝が認める、とか言えば尚更」
「確かにね。聖女の力を戻すメリットをチラつかせれば、食いついて来ると思うよ。あぁいう連中は」
「でしょう。うまくシオドーラが聖女の力を取り戻したら、誰も力を失ったなんて思わないわ。聖女だって人間なんだから、疲れてちょっと雲隠れしていました、ということにすればいいんだし」
ど、どうだ! これで納得するか!
私はヒヤヒヤしながらクリフの顔色を伺った。
「つまり、巡り巡っては、姉様のためになるってこと?」
「そ、そうよ。幻滅したかもしれないけれど、私の本心はそうなの。だから、処理なんて物騒な言葉は使わないで。勿論、行動に移すのもね」
「分かった。姉様のためなら我慢するよ」
が、我慢かぁ……。アリスター様も似たようなことを言っていたからなぁ。今は私もこれで満足しないとね。
それでもこれだけは言っておきたかった。
「クリフ。お願いだから、いつまでも私の心のオアシスでいてね」
「……姉様。僕もそうでありたいよ。いつまでも姉様の特別に」
けれどクリフは成長する。否応なしに。
私の方こそ、それを受け止める覚悟を求められているような気がした。
***
翌日。お母様から許可を得たのか、お兄様がやってきた。それも、バードランド皇子と共に。こちらはお母様がお許しになったのかが疑わしいほどである。
しかし、その理由をまさか本人の口から聞けるとは思ってもいなかった。
「公爵夫人から、直々に謝罪しろと言われたんだ」
「婚約破棄の、ですか? 今更?」
「まぁ、子を成したのだから、今更感は拭い切れないが……。公爵夫人にとっては過去の話ではない、ということなのだから仕方がないだろう」
「確かに、そうですね」
お母様にかかれば、バードランド皇子など『クソガキ』なのだ。無駄な抵抗はせず、従った方がいいのは一目瞭然。
私は快く応じることにした。お腹の子のためにも、皇族との揉め事は極力ない方がいいのだから。
「けれど今はバードランド皇子がアリスター様の要求に応じてくださったことに、感謝しています。ですから、謝罪は必要ありません。けれどお母様には、一応したことにしてもらえますか?」
「分かった。しかし、一つだけ確認させてくれ」
「何でしょう」
「メイベル嬢、いやエヴァレット辺境伯夫人か」
「こそばゆいので、名前で呼んでもらえますか? 一応、幼なじみでもあるわけですから」
元婚約者ではあるけれど、そこまで仲違いをして破棄したわけではない。
そんな人物から夫人と呼ばれるのは……嫌というか、変な感じがする。
「何を言っている。これからは公的な場で何度も言うことになるんだぞ。今から慣れておくべきだろう」
「うっ」
「それに、エヴァレット辺境伯も気にする。私が名前で呼んでいたら、変に勘ぐるぞ。それでもいいのか?」
「いいえ」
確かにアリスター様なら、あり得るかもしれない。
「では改めて聞く。エヴァレット辺境伯夫人、そなたは今、幸せか? 私と婚約していた時よりも」
幸せ……。その言葉を聞いて、ふとアリスター様に契約結婚を申し込まれた時のことを思い出した。
バードランド皇子が私のことを「妹のような存在にしか見えない」と言っていたこと。そのため、私に「恋愛感情を抱くことは難しく」「想い人がいるのだとしたら、応援したい」と。
なるほど。だからこそ、ご自分の選択が、本当に正しかったのかどうか。形ばかりの感謝ではなく、私の本心を聞きたい、というわけか。
何だかもう一人、厄介な兄を持ってしまった気分だわ。
でもこういう時、適した返事を私は知っている。
「はい、勿論です」
私は満面の笑みで答えた。すると、安堵したのか、バードランド皇子は表情を和らげる。その顔は、我が家に来る時によく見せる、柔らかい表情だった。
「良かった。本当は心配していたんだ。エルバートから大丈夫だと聞かされていても、この目で見ないことには、な」
確かにバードランド皇子は、婚約者の私を大事に扱ってくれた。お兄様たちほどの過保護ではなかったけれど、過度でない分、それが心地よいと感じるほどに。
しかしその感情が愛ではなかったことに、今更気づかされた。
バードランド皇子に婚約破棄された時、私はさほど傷つかなかったのだ。それよりも、周りが、特にお母様の反応が気になって仕方がなかった。
けれどアリスター様に突きつけられたら? 考えただけでも悲しくて、苦しくなった。そのくらい、愛しているのだ、アリスター様を。
「あと聖女の件も、感謝する。そなたのお陰で、危険な女と結婚させられずに済んだのだからな」
「……でもそれは、私との婚約を破棄した、からですよね」
「まぁ、そうだな。結果的に丸く収まったのだから由としないか。婚約者候補も一から選ぶことになってな。私もお茶会やらパーティーやらで、また忙しくなりそうなんだ」
つまり、ご自分のやったことを水に流したい、というわけか。
「ふふふっ。いいですよ。確かに結果として、バードランド皇子に罰が下ったわけですから」
「実際はそれだけじゃないんだ。父上と母上、さらに公爵夫人にまで怒られた挙げ句、他にも……」
「わ、分かりました。大変、ご苦労されたことが!」
私は声を張り上げて、バードランド皇子のお小言を阻止した。
これがなければ、いい人なんだけどな、と内心、溜め息を吐く。そう、バードランド皇子は主に、愚痴を言いに公爵邸に来るのだ。
「分かっているよ。罪人とはいえ、聖女様だからね。姉様の意図だって分かっているつもりだよ」
「そ、そう?」
本当かしら、と疑心の眼差しを、つい向けてしまう。それもまた、クリフにはお見通しだった。
「でも、姉様は優し過ぎるよ。何で恩情を与えるの? 一応エヴァレット辺境伯領の騎士団に所属していたんだから、領主夫人の殺害未遂は見逃せない案件だよ? しかも、姉様は聖女に対して嫌がらせも何もしていない、と言うじゃないか。それなのに……」
「確かに嫌がらせというか、接点そのものがあまりなかったんだけど……。それでも、彼女があぁなってしまったのは、私が原因でしょう。だから、皇后様にお願いしてほしいの。向こうにも責任はあるのだから」
「……間接的でしかないのに? 姉様に当たるのはお門違いの勘違い女じゃないか」
どうしよう。アリスター様と同じようなことを言われてしまった。
そんなに私の提案はおかしいのかな。
「それでも! 聖女という存在を簡単に手離してはいけない気がするの。ほら、国民にとってもね。私が原因で力を失くしたなんて知られたら、非難が向くと思わない?」
「そ、それは……そうかも。あの女のせいで、姉様がさらに被害を受けるのは、勘弁してほしいかな。さすがにそんなことがあったら……」
「えっと、だからね、クリフ。教会にシオドーラを引き取らせてほしいの。聖女の力を戻すように、と皇后様が命じれば、教会も断れないでしょう。今は罪人になっているけど、戻せば聖女だと皇帝が認める、とか言えば尚更」
「確かにね。聖女の力を戻すメリットをチラつかせれば、食いついて来ると思うよ。あぁいう連中は」
「でしょう。うまくシオドーラが聖女の力を取り戻したら、誰も力を失ったなんて思わないわ。聖女だって人間なんだから、疲れてちょっと雲隠れしていました、ということにすればいいんだし」
ど、どうだ! これで納得するか!
私はヒヤヒヤしながらクリフの顔色を伺った。
「つまり、巡り巡っては、姉様のためになるってこと?」
「そ、そうよ。幻滅したかもしれないけれど、私の本心はそうなの。だから、処理なんて物騒な言葉は使わないで。勿論、行動に移すのもね」
「分かった。姉様のためなら我慢するよ」
が、我慢かぁ……。アリスター様も似たようなことを言っていたからなぁ。今は私もこれで満足しないとね。
それでもこれだけは言っておきたかった。
「クリフ。お願いだから、いつまでも私の心のオアシスでいてね」
「……姉様。僕もそうでありたいよ。いつまでも姉様の特別に」
けれどクリフは成長する。否応なしに。
私の方こそ、それを受け止める覚悟を求められているような気がした。
***
翌日。お母様から許可を得たのか、お兄様がやってきた。それも、バードランド皇子と共に。こちらはお母様がお許しになったのかが疑わしいほどである。
しかし、その理由をまさか本人の口から聞けるとは思ってもいなかった。
「公爵夫人から、直々に謝罪しろと言われたんだ」
「婚約破棄の、ですか? 今更?」
「まぁ、子を成したのだから、今更感は拭い切れないが……。公爵夫人にとっては過去の話ではない、ということなのだから仕方がないだろう」
「確かに、そうですね」
お母様にかかれば、バードランド皇子など『クソガキ』なのだ。無駄な抵抗はせず、従った方がいいのは一目瞭然。
私は快く応じることにした。お腹の子のためにも、皇族との揉め事は極力ない方がいいのだから。
「けれど今はバードランド皇子がアリスター様の要求に応じてくださったことに、感謝しています。ですから、謝罪は必要ありません。けれどお母様には、一応したことにしてもらえますか?」
「分かった。しかし、一つだけ確認させてくれ」
「何でしょう」
「メイベル嬢、いやエヴァレット辺境伯夫人か」
「こそばゆいので、名前で呼んでもらえますか? 一応、幼なじみでもあるわけですから」
元婚約者ではあるけれど、そこまで仲違いをして破棄したわけではない。
そんな人物から夫人と呼ばれるのは……嫌というか、変な感じがする。
「何を言っている。これからは公的な場で何度も言うことになるんだぞ。今から慣れておくべきだろう」
「うっ」
「それに、エヴァレット辺境伯も気にする。私が名前で呼んでいたら、変に勘ぐるぞ。それでもいいのか?」
「いいえ」
確かにアリスター様なら、あり得るかもしれない。
「では改めて聞く。エヴァレット辺境伯夫人、そなたは今、幸せか? 私と婚約していた時よりも」
幸せ……。その言葉を聞いて、ふとアリスター様に契約結婚を申し込まれた時のことを思い出した。
バードランド皇子が私のことを「妹のような存在にしか見えない」と言っていたこと。そのため、私に「恋愛感情を抱くことは難しく」「想い人がいるのだとしたら、応援したい」と。
なるほど。だからこそ、ご自分の選択が、本当に正しかったのかどうか。形ばかりの感謝ではなく、私の本心を聞きたい、というわけか。
何だかもう一人、厄介な兄を持ってしまった気分だわ。
でもこういう時、適した返事を私は知っている。
「はい、勿論です」
私は満面の笑みで答えた。すると、安堵したのか、バードランド皇子は表情を和らげる。その顔は、我が家に来る時によく見せる、柔らかい表情だった。
「良かった。本当は心配していたんだ。エルバートから大丈夫だと聞かされていても、この目で見ないことには、な」
確かにバードランド皇子は、婚約者の私を大事に扱ってくれた。お兄様たちほどの過保護ではなかったけれど、過度でない分、それが心地よいと感じるほどに。
しかしその感情が愛ではなかったことに、今更気づかされた。
バードランド皇子に婚約破棄された時、私はさほど傷つかなかったのだ。それよりも、周りが、特にお母様の反応が気になって仕方がなかった。
けれどアリスター様に突きつけられたら? 考えただけでも悲しくて、苦しくなった。そのくらい、愛しているのだ、アリスター様を。
「あと聖女の件も、感謝する。そなたのお陰で、危険な女と結婚させられずに済んだのだからな」
「……でもそれは、私との婚約を破棄した、からですよね」
「まぁ、そうだな。結果的に丸く収まったのだから由としないか。婚約者候補も一から選ぶことになってな。私もお茶会やらパーティーやらで、また忙しくなりそうなんだ」
つまり、ご自分のやったことを水に流したい、というわけか。
「ふふふっ。いいですよ。確かに結果として、バードランド皇子に罰が下ったわけですから」
「実際はそれだけじゃないんだ。父上と母上、さらに公爵夫人にまで怒られた挙げ句、他にも……」
「わ、分かりました。大変、ご苦労されたことが!」
私は声を張り上げて、バードランド皇子のお小言を阻止した。
これがなければ、いい人なんだけどな、と内心、溜め息を吐く。そう、バードランド皇子は主に、愚痴を言いに公爵邸に来るのだ。